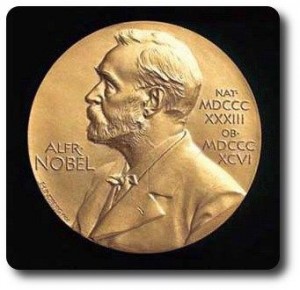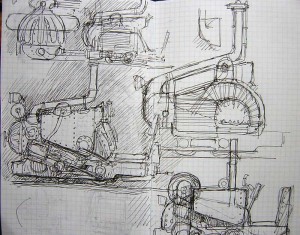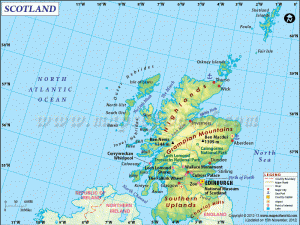長崎にあるグラバー園は第一級の観光地である。なんといっても眺めが良く、建物も非日常的なたたずまいである。その館を建てたトマス・グラバー(Thomas Glover)もまたスコットランド人である。
グラバーは上海にあったスコットランド系の会社ジャディン・マセソン商会(Jardine Matheson Holdings)で働く。マセソン商会は、上海を拠点にしてアヘンの密輸と茶のイギリスへの輸出で巨万の富を得た。それは「アヘン戦争」に深く関わっていた。21歳で来日しやがてマセソン商会の長崎代理店として「グラバー商会」をつくる。
当時、イギリスは世界の貿易をめぐり、フランスとのし烈なライバル関係にあった。徳川幕府を支援していたフランスとの角逐である。「グラバー商会」は、当時船舶、武器弾薬、機械の輸入、さらに茶や貝類、絹織物の輸出で利益をあげていた。亀山社中とも取引があった。製茶工場を造ったり、肥前藩とで高島炭鉱開発に着手するなど商取引を広げていく。薩摩、長州、土佐ら討幕派の雄藩を支援し、日本の近代史の幕開けに貢献する。グラバーは、やがて生麦事件をきっかけに起こった薩英戦争などで悪化した関係修復や強化にも奔走する。
グラバーは商売だけでなく、長州や薩摩の志士を国禁をおかしてイギリスに留学させる。その中に井上馨や伊藤博文らがいた。グラバーは商人ではあったが、先進国の傲慢や優越感にとらわれなかったといわれる。日本文化の良さや利点を学び、それに溶け込もうとした柔軟な精神をもっていたともいわれる。そうした精神構造や適応性は、日本の近代化に参加したスコットランド人に共通した特性といわれる。この点はさらなる検証が必要だと筆者は考える。
日本にやってきたスコットランド人の多くが日本人と結婚している。歌劇「蝶々夫人」のモデルとされるのがグラバーと結婚した談川ツルである。その経緯だが、ツルが格式の高い士族の出身であること、商人である外国人と結婚したことなどが、著者ジョン・ロング(John Luther Long)というアメリカ人小説家の目にとまったようである。西洋の男性にとっては、ゴシップのような話題であったようだ。
 Jardine Matheson Holdings
Jardine Matheson Holdings 長崎市グラバー園
長崎市グラバー園