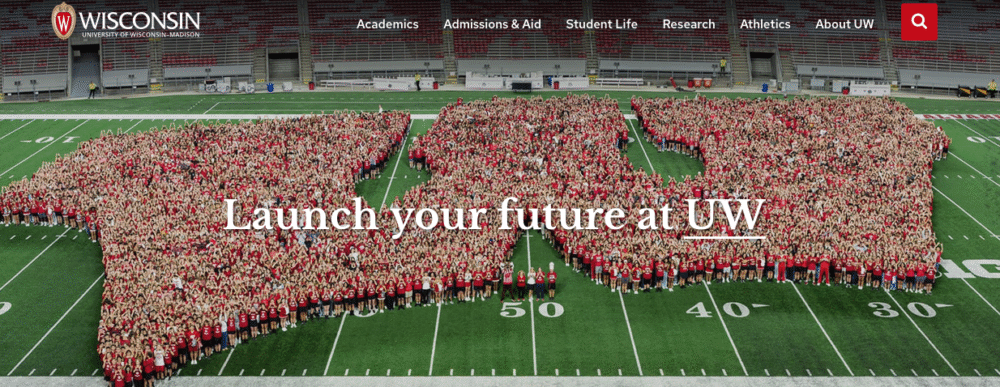主人公、弥生の良人は扶持が十五石の加内三右衛門です。息子は与一郎といって毎日剣術の稽古に励んでいます。弥生の両親は他界しましたが、妹が二人います。小松は百樹家という二百五十石の寄合いの妻に、津留は三百石の家に嫁いでいます。
二人は時々姉のところに遊びにやってきます。ひさしに古雅な青銅の風鈴をみて、この家には色彩がない、調度品もみなくすんでいるなどと指摘します。しきりに姉に対して、もっと華やかで豊かな暮らしをするように云いいながら風鈴を箪笥の引き出しにしまうのです。
「お姉様はこんなにして、一生を終わってよいのでしょうか」
「いつまでも果てしのない縫い張りやお炊事や煩わしい家事に追われ通して、これで生き甲斐があるのでしょうか」
「そしてお姉様は、やがて小さなおばあさまになっておしまいになさるのね」




 三右衛門は火鉢に手をかざしながら、一冊の写本をひらいてみます。妙法寺記というものです。そこに勘定奉行の岡田庄兵衛という老人が訪ねてくきます。そして三右衛門に奉行所へ替わるよう推挙したいと云います。ところが、三右衛門は現在のお役に馴れてもいるし、自分の性に合っていると云いいます。
三右衛門は火鉢に手をかざしながら、一冊の写本をひらいてみます。妙法寺記というものです。そこに勘定奉行の岡田庄兵衛という老人が訪ねてくきます。そして三右衛門に奉行所へ替わるよう推挙したいと云います。ところが、三右衛門は現在のお役に馴れてもいるし、自分の性に合っていると云いいます。
「はじめ御書庫の中で分類朝年代記というものを拝見しておりました」
「飢饉の条のあまりに多いことから思い切って詳しい年表を作ってみようと思いました」
庄兵衛が三右衛門に訊きます。
「然し、そこもとの多忙なからだで、どうしてこんなむつかしいことを始める気になったのだ?」
三右衛門は答えます。
「このように年次表に書き上げますと飢饉のくる年におよそ周期があるのです」
「凶作があって一年めに飢饉の続くことがもっとも多く、次に五年、ないし六年目にくる例が非常に多い、この年次表が完成して周期の波がはっきりわかるとすれば、藩の農政のうえにかなり役立つと思うのですが、」
「たしかに、、」 庄兵衛は大きく頷きます。
「そうすれば冷寒風水による原因もわかって耕作法のくふうもあろうし、荒凶に対する予備もできるだろう、」
ですが、庄兵衛は云います。
「勘定所つとめではさきも知れているし、殊にそこもとの仕事は気ぼねばかりが折れて酬われることが少ない、まったくの縁の下の力持ちで、わしも役替えするほうがよいと思うがな、、」
「役所の事務というものは、どこに限らずたやすく練達できるものではございません、勘定所の、ことに御上納係は、その年々の年貢割をきめる重要な役目で、常づね農民と親しく接し、その郷、その村のじっさいの事情をよく知っていなければならぬ、これには年数と経験が絶対に必要です、単に豊凶をみわけるだけでもわたしは八年かかりました、そして現在ではわたしを措いてほかにこの役目を任すことのできる者はおりません、」
「、、、、それとも誰かわ私に代わるべき人物がございましょうか」
「正直にもうして代わるべき者はない」 庄兵衛はそう呟きます。
三右衛門はこう続けます。
「その人たちには、私が栄えない役を務め、いつまでも貧寒でいることが気の毒にみえるのです、なるほど人間は豊に住み、暖かく着、美味をたべて暮らすほうがよい、たしかにそのほうが貧窮であるより望ましいことです、」
「貧しい生活をしている者は、とかく富貴でさえあれば活きる甲斐があるように思いやすいのです」
「然しそれでは思うように出世をし、富貴と安穏が得られたら、それでなにか意義があり満足することでできるでしょうか」
「たいせつなのは身分の高下や貧富の差ではない、人間と生まれてきて、生きたことが、自分にとってむだではなかった、世の中のためにも少しは役だち、意義があった、そう自覚して死ぬことができるかどうかが問題だと思います」
隣で二人の会話を聞いていた弥生は身震いをします。
「そうだ、少なくとも良人や子どもにとってかけがえのない者にならなくては、、」
箪笥にしまっていた風鈴を弥生は思い出します。それを吊ると久しく聞かなかったチリンチリンという澄んだ音が響きわたります。