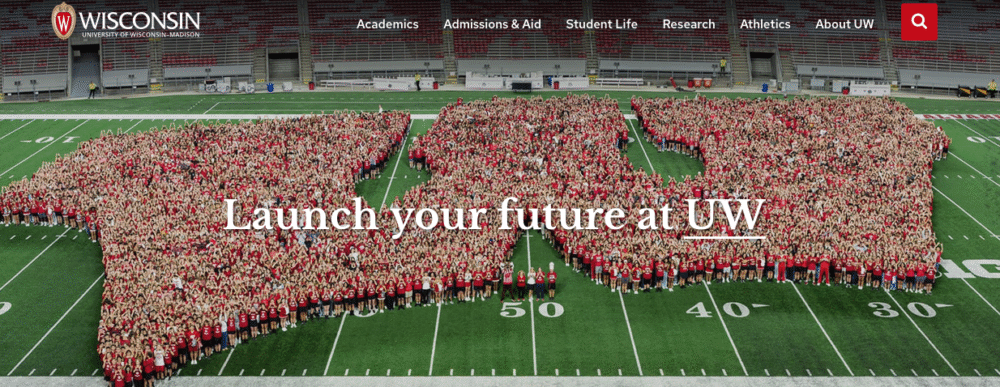江戸における興業の後ろ盾になろうとした妻、お京の親の援助も退けて、作品の価値だけで認められる自立した浄瑠璃作家になることを目指す中藤冲也です。依怙地なくらいに作品の独自性を求め、江戸を離れて大坂、金沢と、各地を転々とします。さすらう女「おけい」の献身的な介護があります。どこの土地でも認められることのない遍歴を続けます。
大坂にでて片岡仁左衛門という役者から、金沢でなら冲也の江戸浄瑠璃を上演してくれるのではと言われます。そして口入れ屋の仲山新平という者へのことづけての手紙を受取り金沢に向かいます。苦難の末、冲也は単身、金沢に着きます。口入れ屋仲山新平に会おうとします。何日も待たされて冲也は不安にかられ、四日間酒を飲み続けます。新平に会う当日はろれつさえ回らず、からだの自由さえききません。設けられた席でも、ろくに三味線も弾けず皆の笑いものになって玄関から放り出されてしまうありさまです。



 そこへおけいが追ってきて、大坂に帰ろうと勧めます。だがもう彼には帰る場所はない状態です。ですが二人で雪の北陸路を大坂に向かいますが、途中で冲也は今庄という小さな町の旅籠で病に倒れます。それを介抱したのはおけいです。おけいは江戸から一緒についてきたもと芸妓です。冲也の端唄を聴いて自分が変身するような経験をして冲也の芸に傾倒し、兄妹のように尽くすのです。宿では別々に寝て、食事ではお京の陰膳をすえるような女でありました。
そこへおけいが追ってきて、大坂に帰ろうと勧めます。だがもう彼には帰る場所はない状態です。ですが二人で雪の北陸路を大坂に向かいますが、途中で冲也は今庄という小さな町の旅籠で病に倒れます。それを介抱したのはおけいです。おけいは江戸から一緒についてきたもと芸妓です。冲也の端唄を聴いて自分が変身するような経験をして冲也の芸に傾倒し、兄妹のように尽くすのです。宿では別々に寝て、食事ではお京の陰膳をすえるような女でありました。
冲也は自分を鼓舞するかのように、自分の遍歴や放蕩じみた旅を次のように振り返ります。
「たいていの人間が、一生にいちどは放蕩にとらわれるものだ。同時に、その大部分の者がそこからぬけだし、ちょうど病気の恢復したあと、しばしば以前よりも健康になる例があるように、放蕩の経験のない者よりもはるかにしっかりした、堅実な人間になる場合が少なくない」
おけいの看病を受けながら大坂に戻ろうとしますが、病床で冲也は呟きます。
「こうしてはいられない」
「おれはこんなことをしてはいられないんだ」
暫くして、また冲也は囁きます。
「このままでは死にきれないんだがなあ」
「男が自分の仕事にいのちを賭けるということは、他人の仕事を否定することではなく、どんな障害にあっても屈せず、また、そのときの流行に支配されることなく、自分の信じた道を守りとおしてゆくことなんだ」