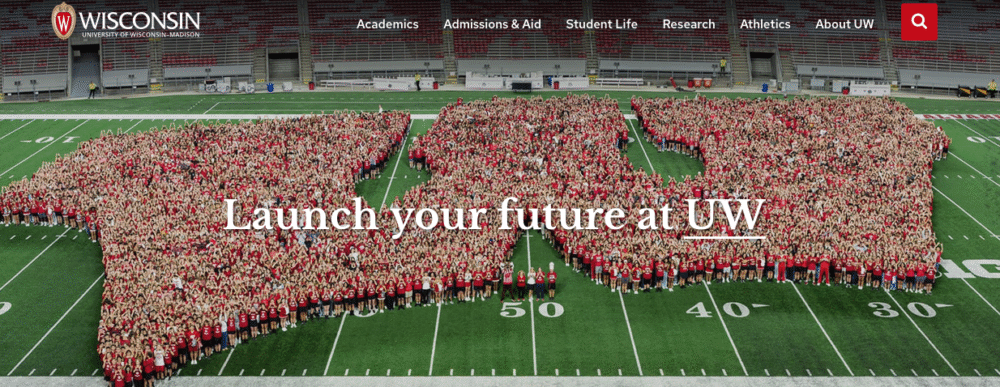大晦日に「赤ひげ」「椿三十郎」「用心棒」など三船敏郎が出演する黒澤明監督尾作品をみました。養生所の頑固な医師、寡黙で豪快なサムライのキャラクターが三船と黒沢のモノクロの作品で圧倒的な存在感をみせていました。
さて、山本周五郎の「西品寺鮪介」という作品を紹介する二回目です。
鮪介は五十石をもって士分に取り立てられ、村の名をとって姓を西品寺、名は鮪介となり城下に家を貰って住みます。周りの者は、「ご覧なさい。あれ、あすこを通る勇士、鮪介とかいう百姓の倅でござる。あの馬鹿天狗が通ります。」というようにたちまち綽名が広まります。勇士どころか挨拶もろくに出来ぬ田舎ものです。悪童どもも「やあーまた馬鹿天狗が針を割りよるぞ」とはやしたてる始末です。ですが鮪介は石のように感じません。
 あるとき、鮪介が大工町筋にさしかかると二人の武士が土器商人にいいがかりをつけるのを目撃します。
あるとき、鮪介が大工町筋にさしかかると二人の武士が土器商人にいいがかりをつけるのを目撃します。
「ま、ちょくら待たっしゃれ」
「何だ、何か用か」
「へえ、おらはへ通りがかりのものだが、商人が無礼をしたとか、邸へ連れていかっしゃると聞いて、及ばずながら、はあ止めに入りやした。おらが商人になり代わって詫びるため、どうか勘弁してやってくらっしゃれ」
「貴公がこやつになり代わる、面白い」
「この場で勝負しよう」
「そりゃせっかくだが駄目ですが、」
「なに、何が駄目だ、」
「勝負をしてはやまやまだが、おらお殿様から立ち会いを禁じられているだ」
「貴公、姓名は?」
「西品寺鮪介と申しやす」
あ、馬鹿天狗と思わず一人が呟きます。

@ÖJñcÖÌQÁðÄÑ|¯é|X^[BÚ¯ÍôƵÄißçê½POA·ì§¢qºÌÖJñ½aLOÙ
「しからば御上意で勝負がならぬとあれば是非もござらん」
「格別の我慢をもって我ら他に望を致そう」
「どうすればいいだが、」
「我ら両名、貴公の頭を五つずつ殴る、それにてこの町人を赦して遣わそう」
「土百姓、分際を知れ!」と罵りながら、拳が空を切って鮪介を力まかせに殴るのです。
かっと眼を見開いた鮪介、空を睨んで一言、「分かった、これだ!」
呻くように叫ぶとぱっと起つなり駆け出します。度肝を抜かれた一同、「や、馬鹿天狗の気が狂った」と叫びます。
鮪介は家に戻ると水をざぶざぶと浴び、据物術の用意をします。しばし瞑目してやおら刀を上段に構え振り下ろします。「かーつ」
刃は見五に命中。縫い針は二つに割れるのです。
「分際を知れば心に執念も利欲もない。針を割るごときはすでに末の末である。これで十分だ。」
急いで許嫁のお民の家にやってきます。
「あれ、鮪さでねか」お民は云います。
「おらあ針を斬り割っただ。それでお民との約束を果たすべとやってきたんだ」
「その鍬をこっちに貸せよ、これからこの土地全部を因幡さまの上地にしてみせるだぞ」
「どりゃ、おらの仕事ぶりを見せべえか」
鮪介は侍をやめて百姓に戻ります。
それから二年後。池田光政が鮪介の畑を通ります。
「私がたの田より反辺り十二表を収穫し、大豆は五十石止まりのところを九十石も上げあした。本願を達したとは申せませぬが、いま二、三年もすればどうやら半人前の百姓になれようかと存じまする」
「あっぱれ、よくぞ申した」光政は膝を叩いて
「あっぱれ、本願成就ときけば、定めし針を割ったことを申すであろうと存じたが、収穫の自慢をいたすところ、真の極意を会得した証拠だ、光政満足に思うぞ!」
一人の百姓は百人の西品寺鮪介よりも尊い国の宝であると光政は述懐するのです。