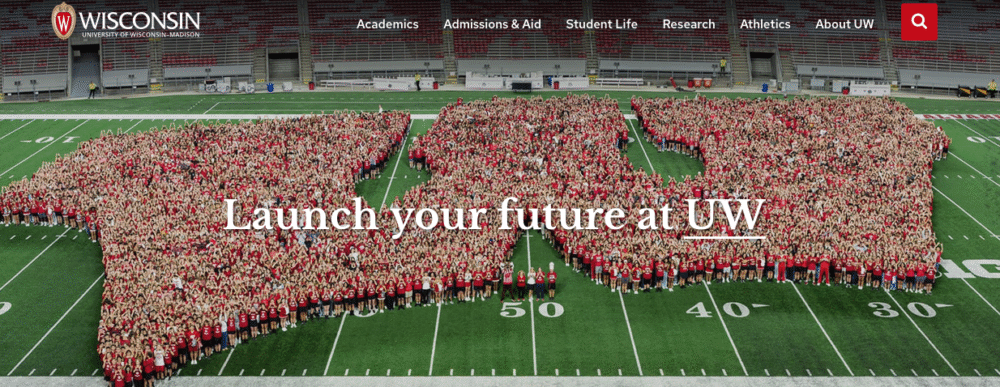藤沢周平の「蝉しぐれ」を数回にわたり紹介していきます。彼の作品は時代小説とか歴史小説といわれるようですが、内容や雰囲気からするとどうも新しい時代小説のようです。「蝉しぐれ」という原題ですが、蝉が亡骸を残し、晩秋の降ったりやんだりする小雨から、なんとなく憂うつな雰囲気が漂います。そして街の描写、自然のうつろい、主人公の住まいや身分などが丁寧に描かれます。なにかが起こる前兆を読者に期待させるのです。


 藤沢周平の作品の中には、川や橋がよく登場します。江戸期の「橋」を舞台とした小話があります。橋は対岸へと渡るためだけではなく、人生が交差する場として描かれます。歳月が流れた橋の上で男が昔の幼馴染みにいう場面もあります。「綺麗になった。」というのです。
藤沢周平の作品の中には、川や橋がよく登場します。江戸期の「橋」を舞台とした小話があります。橋は対岸へと渡るためだけではなく、人生が交差する場として描かれます。歳月が流れた橋の上で男が昔の幼馴染みにいう場面もあります。「綺麗になった。」というのです。
「蝉しぐれ」の冒頭では、次のような自然が描写されます。
いちめんの青い田圃は早朝の日射しをうけて赤らんでいるが、はるか遠くの青黒い村落の森と接するあたりには、まだ夜の名残の霧が残っていた。じっと動かない霧もあさの光をうけてかすかに赤らんで見える。そしてこの早い時刻に、もう田圃を見回っている人間がいた。
舞台は山形の海坂藩です。主人公の牧文四郎、そして小和田逸平、島崎与之助は、十五六歳の若者です。この三人が人間として成長し、また現実の厳しさに直面していきます。やがて、三人はの郡奉行、藩校の教授、御書院目付となっていきます。御書院とは藩主の身を守る防御任務のことです。
文四郎の家の隣に小柳甚兵衛の娘ふくがいます。文四郎の3歳年下です。お福は藩主正室の寧姫に仕えるため、江戸に向かうことになります。その直前に牧家を訪ねて文四郎に思いを伝えようとするのですが、あいにく文四郎は外出していて会うことができません。
「小柳のふくさんがたった今帰ったばかりだけど、、、、そのあたりで出会いませんでしたか」と落ち着かない顔で文四郎の母はいいます。
「いや」 文四郎の胸にあかるいものがともります。ふくの名前を聞くのはひさしぶりだったのです。
「それがね、、急に江戸に行くことになったと、挨拶にみえたのですよ。」
「明日、たつのだそうです。江戸屋敷の奥に勤めることになったとかで、、その話はあとにして、、、、」 母は指で外をさすのです。
「ちょっと追いかけてみたらどうですか。まだその辺にいるかも知れませんよ。」
「わかりました」
文四郎はふくが帰りそうな道を探します。そしてあげくは川岸の道まで行きますがふくの姿は見えません。