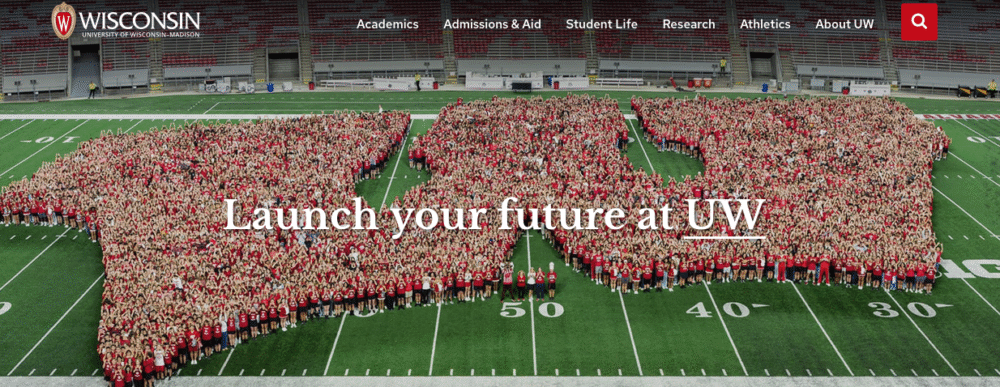原田甲斐は常着のまま、袴もはかず、編み笠をかぶった姿で長徳寺の門前で茂庭主水と逢います。主水は伊達家重臣で松山の館主、周防定元の子です。定元は甲斐や安芸と共に伊達兵部の陰謀を防ぐために奔走してきたのです。主水もまた単衣の着流しで、やはり編み笠をかぶり、片手に釣箱と餌箱をもっています。
「父は私に遺書をのこしました」と主水は云います。
「それで一度おめにかかりたいと思っていたのです」
「会えと書いてありましたか?」
主水はそこでちょっと口ごもります。
「あなたに悪評が立ち、不審と思えるようなことがあっても、あなたを信じておれ、そして、もしもあなたからなにか頼まれたら一命を賭してやれ、という意味でした」
「父の遺書はどういう意味なのでしょうか?」主水は訊きます。
「話しましょう」
「誰かおります」主水がそういって片方をさします。一人の老人がすっとたちあがります。
「誰だ、」と老人が呼びかけます。
「ここは無用の者がくるところでない、、」
視力は全く失っているようです。甲斐は近寄りながら、穏やかな声で云います。
「久方ぶりだな、十左衛門、わたしだ、」
「船岡どのか」その老人、里見十左衛門が云います。
十左衛門はかつての伊達家家臣です。兵部の専横が強まり、これを批判した奉行家老奥山大学を失脚させます。十左衛門は甲斐を通じて兵部に諫言したため、失脚させられます。伊東七十郎という重臣伊東新左衛門の義弟と友達でした。七十郎は文武両道の才人といわれ、伊達の家来ではありませんでしたが、義兄を助けて十左衛門と共に兵部に敵対してきた男です。



 「松山の主水どのが一緒だ」
「松山の主水どのが一緒だ」
「ここで話したいことがあって案内を頼んだ、ちょうどいいおりりだ、十左衛門にも聞いてもらうこととしよう」
こうして、二人は甲斐から仙台藩取り潰しの全体像を教えられるのです。
「わたしにはそのまま信じられません」十左衛門が云います。
「ことに仙台藩という由緒ある大藩に幕府が手をつける、などということがあるでしょうか」
「十左衛門が納得しかねるのもむりではない、だが、事の起こりから考えてみれればわかる」
「まず綱宗さまにたいする殆ど無根拠な譴責と、跡目をきめるについての難題だ」
「そして同時に、二方面に手がうたれた、一つは酒井候が一ノ関の兵部に与えた三十万石分与の密約であり、もう一つは幕府閣老の某候が、茂庭周防を呼んでひそかにその密約を告げてきたことだ」
「よもや風聞ではごあいますまいな」
「酒井候と一ノ関とで交わした証文があり、仔細あってその一通を私が持っている」
「紛れのないものですか?」
「紛れのないものでだ」甲斐が答えます。
「幕府閣老の某候がひそかに周防を呼んで、そういう密約があることを告げたのだ」
「某候とは誰びとです?」
「名は云えない」
「名は云えないが、将軍家お側衆で、当代十善人のひとりと評された人だ」
十左衛門は俯向くのですが、すぐに「久世大和守、、、」と口の中で呟き顔をあげます。