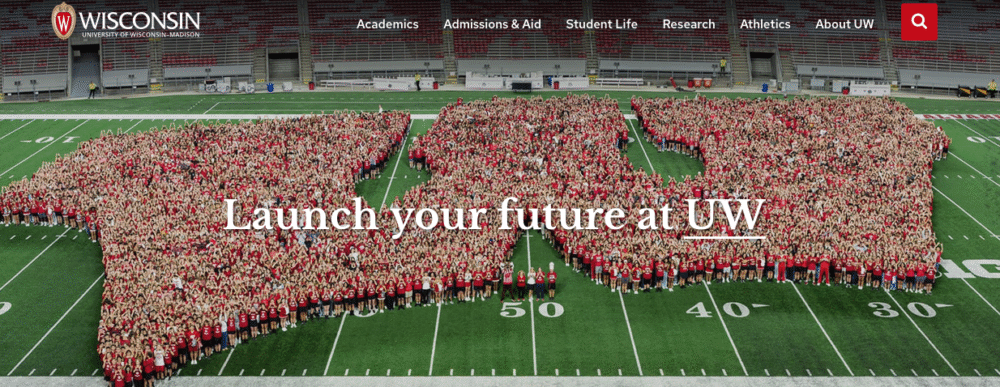サブカルチャーのメインカルチャーへの挑戦は至るところに現象として現れた。当然のように文化と考えられた歴史とか古典に対する強い関心と畏敬は、サブカルチャー(大衆文化)の側からすると一種の審美的文化観とされて、時に「マニア」、「おたく」といった独特な行動様式として揶揄することもある。しかし、おたくの本人は「伊達や酔狂」と自負するようなところがあって、むしろ孤高のような存在感を楽しむようなところもあるようだ。
サブとメインの境界が曖昧になったということは、その逆転現象がうまれてきたということでもある。例えば、活字文化は今もそうかもしれないが、メインカルチャーの旗頭であった。だが、なにもかも電子媒体としてメディア界に急速に広がるのが現在。書籍の売り上げた伸びないのは、電子媒体の流通と普及があるともいわれる。多くの書類、卒業論文、研究論文は電子媒体で提出しなければならない。悔しいことだが、手書きの論文は受け付けてくれない。
「子どもたちは夏目漱石や森鴎外を読まないのではない。読めないのだ」ともいわれる。漢字能力の低下が一因だというのである。手書きできない。それで電子辞書を使い携帯電話サイトから「ケータイ小説」をつくる。「書く」のではない。漢字が書けなくても小説が書けるという時代になった。「話し言葉が中心なので親近感があり、一文一文が短く読みやすい」という新しい文化観もそこにある。
技術革新に伴う諸々の変化は、もはや後戻りができない。革新が続くだけだ。だが、電子媒体にも寿命がある。記録したデータを保持できる期間は有限である。読み込みの処理がなくとも経年により媒体は劣化していく。そしてデータが読めなくなったり消失したりする。自分もその苦い経験はある。もっとも機械的な寿命の問題だったが、。
活字文化がサブカルチャーか、メインカルチャーかという議論はすまい。だが分かっていることは、サブとメインの逆転、そのまた逆転も起きうることである。今や「アングラ」も「ヌーヴェルヴァーグ」もという表現も目にすることはない。文化の論争は意味がなくなっているからだろう。
活字文化プロジェクトが各地で盛んになり、活字文化推進会議とか活字文化推進機構もできた。電子媒体文化とのせめぎ合いのようだが、両者が共存することも文化ではないかと思うのである。