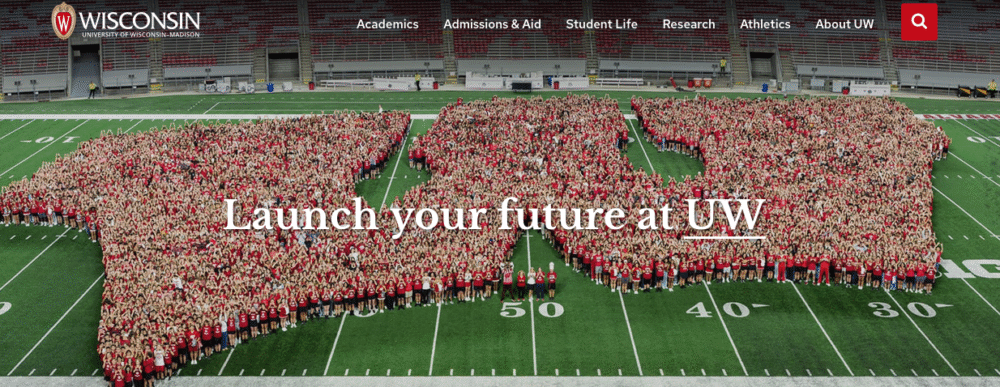文四郎は牧家に養子にきて育てられたのです。つましい牧家の暮らしながら、養父、養母から暖かい愛情をそそがれて成長します。世継ぎを巡る閥に巻き込まれた養父は、詰め腹を切らされることになります。
「しかし、わしは恥ずべき事をしたわけではない。私の欲ではなく、義のためにやったことだ。おそらくあとには反逆の汚名が残り、そなた達が苦労することは目に見えているが、文四郎はわしを恥じてはならん。そのことは胸にしまっておけ、、登世をたのむぞ、、、、」 登世は文四郎の養母です。



 「夜が明けると、日はまた昨夜の嵐に現れた城下の家々と木々にさしかけ、その日射しは、六ッ半(8時)に達する頃には、はやくも堪えがたい署熱の様相をむき出しに見せ始めた。そして五ッ半になると牧文四郎の家に城から使者がきた」
「夜が明けると、日はまた昨夜の嵐に現れた城下の家々と木々にさしかけ、その日射しは、六ッ半(8時)に達する頃には、はやくも堪えがたい署熱の様相をむき出しに見せ始めた。そして五ッ半になると牧文四郎の家に城から使者がきた」
「藩に対する反逆の罪により、牧助左衛門には切腹を。牧家は家禄を四分の三に減じ、普請組を免じて、家は長屋に移す。」 使者は文書を読み上げます。
「自裁し終わった遺骸は、それぞれの家で引き取って貰う。できれば荷車を支度するように」
文四郎 「何刻までに参ったらよろしゅうございますか?」
使者 「始まるのは四ッ半、助左右衛門どのは昼過ぎになろうが、昼までには寺にきておるほうがようかろう」
予期していたように、むしろをかけられた父親の荷車は行く先々で人々の冷たい視線を集めます。軒下にたっている人々が一語も出さず、しんとして自分を見送るのを文四郎は痛いほど感じるのです。
「さあ、押してくれ!」
助けにきてくれた道蔵に一声かけると文四郎は最後の気力を振り絞って、横たわる父親の荷車を押してのぼりになる坂をはしり上がります。その姿は「蟻のごとく」、車はそれほど重かったのです。喘いで車を押す文四郎の眼に、組屋敷から小走りにかけつけて来る少女の姿が映ります。確かめるまでもなく、それはふくです。文四郎の側までくると、荷車の上の遺体に手を合わせ、文四郎に寄り添って梶棒をつかみ、涙がこぼれるのをそのままに一心な力をこめて梶棒を曳くのです。