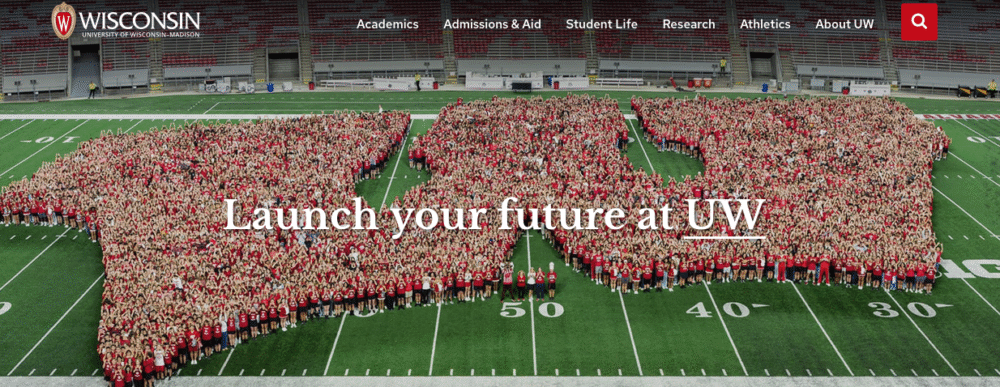小説日本婦道記にある最後の作品「二十三年」は1945年10月の「婦人倶楽部」に掲載された作品といわれます。この雑誌は講談社から創刊され、「主婦の友」や「婦人公論」と並んで読まれたといわれた月刊誌です。
主人公は、新沼靭負という会津蒲生家の武士です。”靭負”は”ゆきえ”と呼ばれます。靭負は御蔵奉行に属し、食録は二百石余りでした。まじめで謹直なところが上からも下からも買われて、平凡ながら極めて安穏な暮らしをしてきます。しかし、主家の改易があり、下野守忠郷が病没すると嗣子がないことが原因で会津蒲生家は改易となります。多くの者は寄る辺を頼り、また他家へ仕官して、思い思いに城下から離散していきます。1611年に起こった会津地震も藩内を大きく揺さぶります。
 下野守の弟にあたる蒲生忠知が伊予の国松山藩で、二十万石で蒲生の家系をたてているというので、会津藩の人々は松山藩に召し抱えられたいと希望します。靭負もその中の一人です。靭負は妻のみぎを亡くし乳飲み子を抱えています。貯えも多くはないので、家士や召使いには皆暇を遣りますが、「おかや」という婢は独りどうしても出て行きません。おかやには両親はいませんが、兄の多助はおかやに度々、良縁があるからお暇を頂くようにと云ってきます。おかやはまだ早すぎると答えるばかりです。
下野守の弟にあたる蒲生忠知が伊予の国松山藩で、二十万石で蒲生の家系をたてているというので、会津藩の人々は松山藩に召し抱えられたいと希望します。靭負もその中の一人です。靭負は妻のみぎを亡くし乳飲み子を抱えています。貯えも多くはないので、家士や召使いには皆暇を遣りますが、「おかや」という婢は独りどうしても出て行きません。おかやには両親はいませんが、兄の多助はおかやに度々、良縁があるからお暇を頂くようにと云ってきます。おかやはまだ早すぎると答えるばかりです。
仲間が欠けていくのを見送りながら靭負は独りで松山に行くことに決めます。
「松山にお供させて頂きます」 とおかやは云います。
仕官の見通しもなく、浪人の身で給金さえ遣りかねるときがくるといって靭負はおかやへ家へ帰るように云います。
「ではせめて坊さまが立ち歩きをなさるようになるまで、、、」
靭負は多助に家に戻るよう申し訓えてくれるように頼みます。多助の訓が功を奏したのか、おかやは案外すなおに云うことをききます。靭負は牧二郎を抱いておかやと多助が出て行くのを見届けます。しかし、おかやは八幡様の崖の下で倒れているのが見つかり、戸板に乗せられて靭負の家に運び込まれます。医者は「脳の傷みがひどく、ひと口でいえば白痴のようになっている」と云います。