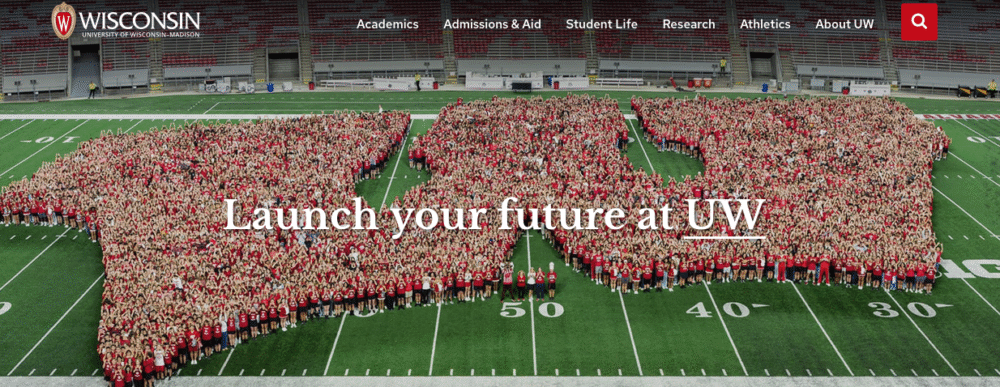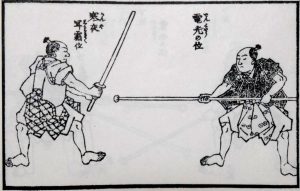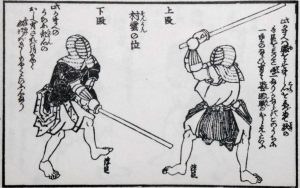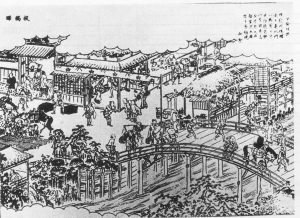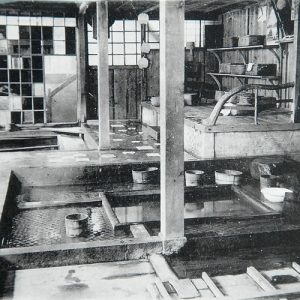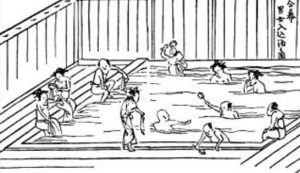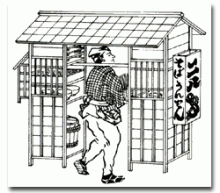「やぶからし」という野草は道端や荒れ地、フェンス際、その他どこにでも生える多年草です。茎は弾力があり、高い木々に絡まり伸びていきます。植栽を覆って枯らしてしまうほど旺盛に生育します。厄介な野草で、別名ビンボウカズラともいわれます。
山本周五郎がなぜこのような題名を付けたのかは、この作品を読むとわかるのですが、皆から嫌われるほどどん欲な生活をしたり、時に狡猾な為政をして、市井で貧しく生きる人々を苦しめる者がこの世の中に多いことを主張したかったからでしょう。
主人公は十六歳になって細貝八郎兵衛とさちの家に嫁いできた「すず」です。本当の父と母は四歳のとき亡くなり、常磐家に引き取られて育ちます。常盤家三百石ばかりの扶持で、旗本を編制した部隊に所属する大御番でした。きびしい家風と家族のあいだの不思議な冷ややかさがあって、すずは本当の家とは感じないで生きてきました。

 すずは、なぜか細貝玄二郎という放蕩な生活をしてきた男と祝言をあげます。初夜から大酒を飲み、すずに乱暴を働きます。それが毎夜続く始末です。しかも無頼の仲間と喧嘩をし傷つけたり借金を溜め込むために、細貝家はとうとう玄二郎を勘当します。
すずは、なぜか細貝玄二郎という放蕩な生活をしてきた男と祝言をあげます。初夜から大酒を飲み、すずに乱暴を働きます。それが毎夜続く始末です。しかも無頼の仲間と喧嘩をし傷つけたり借金を溜め込むために、細貝家はとうとう玄二郎を勘当します。
見かねた細貝八郎兵衛とさち女は、はすずに郷に帰るようにと言い聞かせます。
「すずは細貝家の娘です。この家の他に郷などはございません」
佐波久弥という書院番の男を八郎兵衛は夕餉に招きます。二十六歳で背丈は高く立ち振る舞いがのびやかです。酒はあまり飲みません。八郎兵衛とは親しくしていて、すずに嫁がせようとするのです。この二人は謡を唄うという趣味があります。その頃すずは鼓を習っていたので、食事の後に三人で唄うのです。
すずは久弥と再度の祝言をあげ、やがて二人の子供に恵まれます。娘のこずえを宮参りにつれていったとき、昔の良人、玄二郎にであいます。玄二郎はそこで過去の生活を語り、あげくにすずに五両を無心するのです。それが二十両になり、すずは一人で悩んだ末にとうとう懐刀をもって玄二郎の指定する場所にいきます。玄二郎を殺め、自分もその後を追っても、良人や子供たちは仕合わせに暮らせると決心したからです。
玄二郎はやくざ者たちによって始末されます。自らの手でかつての良人を殺めることがなかったことにすずは安堵するのです。