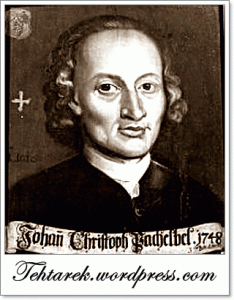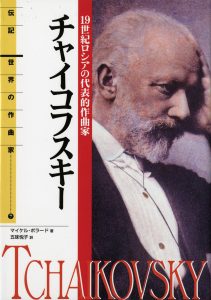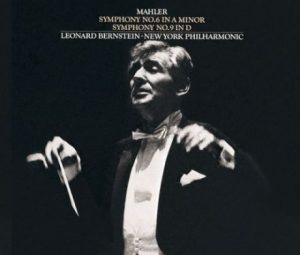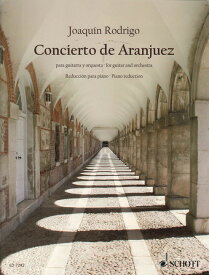ケンタッキー州(Kentucky)といえば、スティーブン・フォスター(Stephen Foster)が作詞作曲した「ケンタッキーの我が家」(My Old Ketucky Home)を想い出します。60代以上の人なら誰もが聞き口ずさんだことのある哀愁味漂う曲です。フォスターは他にもスワニー河(Swanee River)、オールドブラックジョー(Old Black Joe)、夢見る人(Beautiful Dreamer)など150曲余りを作りました。彼は「アメリカの音楽の父」と呼ばれています。
ナンバープレートには「Bluegrass State」とあります。草原を遠くから眺めると青紫色のつぼみが一面広がり、「青い草」に見えたので名付けられたとあります。ブルーグラス・ミュージック(Bluegrass Music)です。スコットランドやアイルランドの音楽を基にしています。アップテンポの曲が時代と共に多くなり、速弾きなどのインプロヴァイズ(即興演奏)もあります。お隣テネシー州でもこの音楽は盛んです。
ケンタッキーはイリノイ、インディアナ、オハイオ、ミズリー州に囲まれ、オハイオ川とミシシッピー川で州境をなしています。東側にはアパラチア山脈が聳えていて、豊かな自然に恵まれています。この州はなんといっても「ブルーグラスの州」と呼ばれ、肥沃な土壌からの多くの農産物がとれます。州都はフランクフォート(Frankfort)。最大の都市はルイビル(Louisville)となっています。
ケンタッキーは馬の生産地でも知られています。ケンタッキー・ダービー(Kentucky Derby)開かれるのこの地です。バーボン・ウイスキー(bourbon whisky)の一大生産地でもあります。その他タバコの生産も盛んです。ケンタッキーには自動車産業も盛んです。フォード、GM、トヨタの工場があります。トヨタはアメリカで最もポピュラーな車「カムリ」をここで組み立てています。