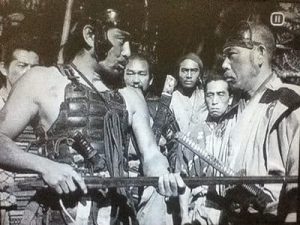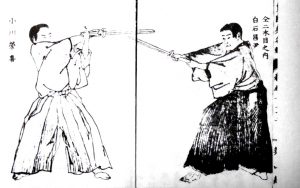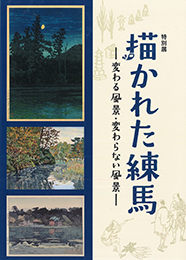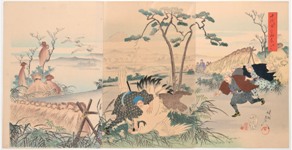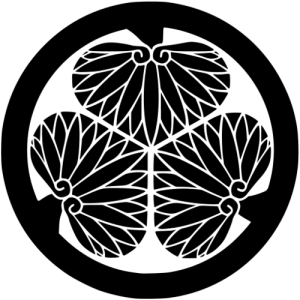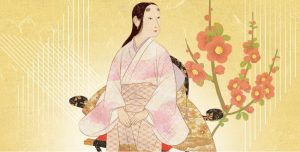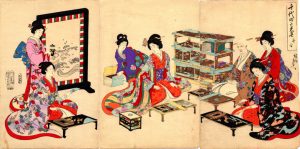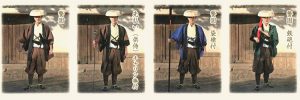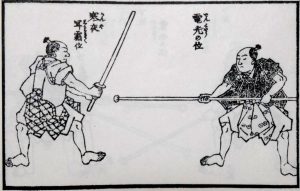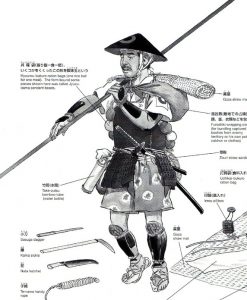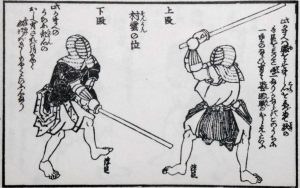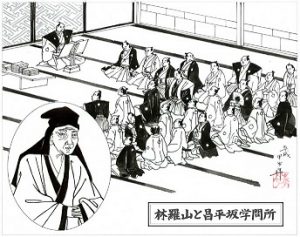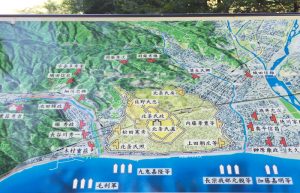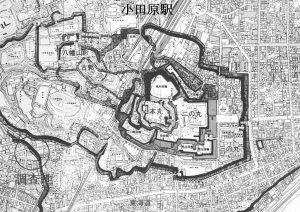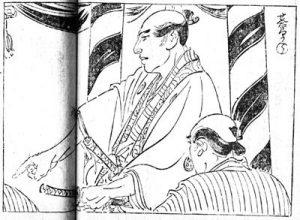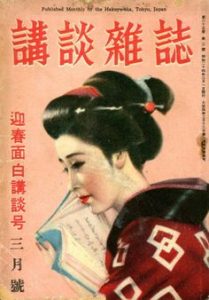ジョージア州(Georgia)のナンバープレートには桃(peach)がデザインされています。この州はスイカ、メロンなどの果物が多いのです。特に桃は有名なので「Peach State」、「桃の州」と呼ばれています。ここの桃は、日本の桃とは違い、少し堅めの肉感がします。甘みも結構ありますが、日本の桃とは比べられません。そのかわり安価で助かります。ナンバープレートのデザインは明るくのどかなものです。ジョージア州のモットーに「南部の帝国」(The Empire of the South)というのもあります。
ジョージア州名は、植民地設立の勅許をイギリスの軍人ジェームズ・オグルソープ(James Oglethorpe)に与えたイギリス国王ジョージ二世(George II)に由来します。悲劇もあります。1830年、アンドリュー・ジャクソン大統領(Andrew Jackson)がインディアン移民法に署名します。そして東部にいた多くのインディアンを現在のオクラホマ州にあった居留地に移住させる決定をします。これにはジョージアにいた全ての部族も含まれていました。1835年にチェロキー族(Cherokee)連合に対して行われた強制移住です。約15,000名のチェロキーのうち4,000から5,000名が途上で死亡したといわれます。この逃避行は「涙のトレイル」(Trail of Tear)と呼ばれました。その途中でインディアンは「Amazing Grace」という讃美歌を歌って気分を高めたともいわれます。
ジョージア州の居住パターンは、物理的な地理と同じくらい多様性に富んでいます。州の先住民族は、1500年代初頭のヨーロッパ人との接触の時点で、すでに豊かで複雑な村ベースの文明を確立していました。1700 年代にイギリス人入植地はマスコギー(Muskogee)と呼ばれていた先住する先住民部族との文化的対立を引き起こし、その世紀後半から1800年代初頭にかけて白人入植者が着実に西に移動するにつれて激化しました。元々の英国植民地の1つであり、最初に合併した州の1つであるジョージア州は、アメリカ独立戦争後に、米と綿花を栽培し、増加する黒人奴隷人口に大きく依存するプランテーション社会として台頭しました。
20世紀になると、ジョージア州の主要都市が拡大し、ジョージア州の人口は徐々に田舎の性格を失います。1980年代から90年代にかけて、州の南西部と中央部にある古い綿花地帯の多くは人口が減少していきます。しかし、これらの損失は、80kmも離れたアトランタ郊外での大幅な利益によって大幅に相殺されていきます。大西洋岸のサバンナ(Savannah)とブランズウィック(Brunswick)周辺の地域も急速な成長を遂げています。南部諸州の中で、ジョージア州は1970年代以降、フロリダに次ぐ人口増加が一般的となり、1990年代にはその増加はフロリダを上回りました。
ジョージア州等の南部の諸州は「バイブル・ベルト」(Bible Belt)という名称で呼ばれます。「福音派プロテスタント」というキリスト教の宗派が社会と政治において特に強い役割を担っている地域のことを指します、住民も一般的に社会に対して保守的であり、他の地域の人々よりも教会への出席率が高いのです。主にプロテスタントであり、アフリカ系アメリカ人コミュニティでは特にバプテスト教会とメソジスト教会が強い州となっています。
南部のアトランタ(Atlanta)はジョージア州最大の都市であり州都です。21世紀初頭には、州の繁栄は主にサービス業を基盤とするようになります。その中心は、アトランタとその周辺がその大部分を占めます。特にアトランタは、州の主要な公益企業、銀行、食品・飲料、情報技術産業の本拠地であり、企業本社の立地としてはまさに国内有数の都会となっています。アトランタの先進的なイメージと急速な経済・人口成長に後押しされ、ジョージア州は20世紀後半には、全体的な繁栄と全国的な社会経済規範の浸透で、深南部(Deep South)の他の州を大きく引き離していきます。コカコーラやCNN、保険会社アフラック(Aflac)の本社などがあることでも知られています。
ジョージア州は映画の舞台でもあります。「風と共に去りぬ」(Gone with the Wind)を書いたマーガレット・ミッチェル(Margaret Mitchell)の記念館-The Margaret Mitchell House-がダウンタウンにあります。マーチン・ルーサー・キング(Martine Luther King Jr.)牧師が説教していたエベネゼル・バプティスト教会(Ebenezer Baptist Church)、そして師の功績を称えるThe King Center博物館は必ず立ち寄るべきところです。政治では第39代大統領となったジミー・カーター(Jimmy Carter)がでたところです。
大西洋側に前述したサバンナの港町があります。植民地時代は、サバンナは綿花のヨーロッパへの輸出港でした。今も貯蔵倉庫が建ち並び、多くのレストランなどに改装されています。マスターズ・トーナメント(Masters Tournament) のゴルフ大会が開かれるのがオーガスタ(Augasta)です。メンバーは世界中に約300名、会員になるためには数10年程待たなければならないそうです。
ちょっと寄り道ですが、コーカサス山脈(Caucasus Mountains)に囲まれ、黒海に面する国に「ジョージア」があります。もともとはソ連邦の一部で「グルジア」(Gruziya)と呼ばれていました。合衆国のジョージア州とは全く関係がありません。一度、ネブラスカ大学の友人からメールが来て、「今、ジョージアにいて学生に特別講義をしている」というものでした。てっきり南部のジョージア州だと思いましたが、首都のトビリシ(Tbilisi)にいるとのことで了解しました。
グルジアは1783年にロシアの保護を求め、1801年にロシア帝国に併合されます。1917年のロシア革命(Russian Revolution)の後、この地域は短期間独立します。1921年にソビエト政権が樹立され、1936年にグルジアはソビエト連邦の正式加盟国となります。1990年、ソビエト・グルジアで史上初めて行われた自由選挙で非共産主義連合が政権を獲得し、1991年にグルジアは独立を宣言し、海外からは「ジョージア」と呼ばれるようになります。2003年にジョージアのエドゥアルド・シェワルナゼを大統領辞任に追い込んだ暴力を伴わない革命が起こります。これは通称「バラ革命」と呼ばれます。現在はロシアとの対立路線をとることが多いといわれます。独裁者ヨセフ・スターリン(Joseph Stalin)は「グルジア」の出身でした。
ジョージアは黒海(Black Sea)の南東海岸、コーカサス山脈内に位置している共和国です。グルジアは1783年にロシアの保護を求め、1801年にロシア帝国に併合されました。1917年のロシア革命(Russian Revolution)の後、この地域は短期間独立しました。1921年にソビエト政権が樹立され、1936年にグルジアはソビエト連邦の正式加盟国となりました。1990年、ソビエト・グルジアで史上初めて行われた自由選挙で非共産主義連合が政権を獲得し、1991年にグルジアは独立を宣言します。
私は、アメリカ留学のために英語の研修を2か月受けました。その場所はジョージア州のステイトボロ(Stateboro)という小さな町にあるカレッジです。家族を引き連れての2か月の滞在でした。国際ロータリー財団(Rotary International Foundation)からの50名くらいの奨学生と一緒に、短期間でしたが南部の人々の親切さ(Southern Hospitality)と温暖な気候を満喫しました。
ジョージアに来て始めていろいろなことを知りました。コンビニもそうで、セブンイレブン(Seven-eleven)が大きなスーパー店の側にあるのです。タバコの競り市に行ったときです。人々がしゃべっていることが全く分かりません。南部訛り(Southern Drawl)というのを体験しました。いわば南部アクセントです。南部訛りは、ゆっくりとした話し方で、母音を引き伸ばすように話します。アクセントの配置にも特徴があります。例えば「police」の発音は、「ポ・リース」と、リースの部分を伸ばして発音するのが一般的です。イギリス英語と少し似ていて、carやfarの最後のrをはっきりと発音しない特徴もあります。そのせいもあってか、私の英語には南部訛り(Southern Drawl)があるようです。
毎日3時頃になると決まってスコールが通り過ぎます。市営ブールで遊ぶ子ども達はプールから出なければなりません。それと、午後にはスイカやメロン、ピーチを積んだトラックがきます。スイカはラクビーボールのような形です。滞在していたアパートの前にピーカン(peacon)の木がありました。くるみに似ているナッツで、始めて賞味しました。実に美味しかったのを覚えています。
(投稿日時 2024年2月25日)