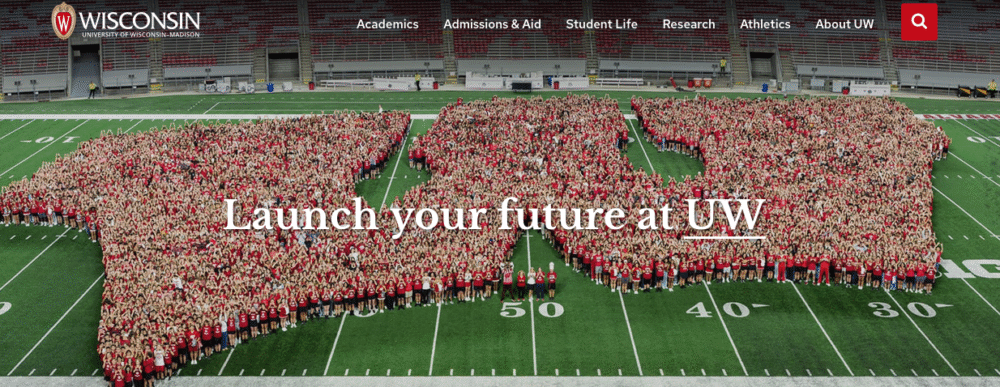佐伯泰英の時代小説に「吉原裏同心」というシリーズものがある。この小説の舞台は江戸の吉原である。ここに暮らす人々の夢と欲望、汚れさと純真さ、嫉妬と愛情などが描かれている。
天下御免の色里、吉原の頂点にいるのが花魁である。一見華やかな太夫、花魁の世界。その背景には、売られ買われる女性がいる。それを取り巻く大勢の人が吉原で暮らす。例えば、吉原の秩序を保つ江戸町奉行の与力や同心、廓内での騒ぎをまとめる頭取や小頭、さらに医者、仕出し屋、職人、商人、芸者がいて吉原という集団を形成している。
愛欲が渦巻く遊里にはいろいろな事件が起こる。しかし、幕府公認のこの色里には廓内のきまりがあり、それによって自治や治安が保たれるという不思議な世界である。
筆者がこの時代小説に惹かれるのは、吉原という共同体に受け継がれる行動のパタンやその背後にある価値観という文化なのである。この文化を考えるには、その文化に縛られる吉原という場を設定する必要がある。そうでなければ、吉原という「場」をステレオタイプ(固定観念)でとらえてしまう。この観念に対抗する視点を持たなければ、なぜ裏同心という存在が重要になるかがわからない。
江戸文化というと一見、茫漠としているが、それは人々が手を加えて形成してきた衣食住をはじめ、歌舞音曲、作法、詩歌など生活様式と内容という総体のことである。この総体を意識すると、吉原に暮らす人々の日常性のなかに少々大袈裟であるが、文化ということになにか原理的な意味を見つけられるような気がしてきている。