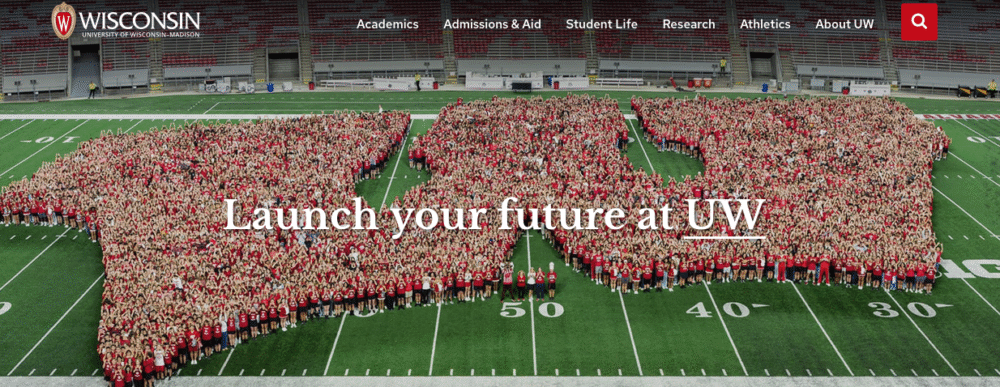主人公は佐野藤右衛門という紀州徳川家の年寄役と女達です。藤右衛門は千石の禄をもらっています。64歳となり老年をいたわる思し召しで藩譜編纂役となり、下から上がってくる素稿を点検する仕事で、以前のような煩雑な日常から解放されています。「松の花」とは烈女節婦の伝記や紀州家中、古今誉れの高き女性たちを収録したものです。これを手直しするのが藤右衛門の仕事です。
藤右衛門の妻、やす女は重態で伏せています。
「申し上げます、父上申し上げます」長子、格之助の声がします。
「病間へおいでください、母上のご様子が悪うございます」


 格之助と嫁のなみ女、次男の金三郎、婢頭のそよ、皆せきあげて泣いています。
格之助と嫁のなみ女、次男の金三郎、婢頭のそよ、皆せきあげて泣いています。
「まことにお安らかな眠るようなご往生でございました」
脈をとっていた医者がそう云うのをききながら、藤右衛門はしずかに枕元に坐ります。そして妻の唇にまつごの水をとってやります。夜具のそばになみ女の手が少しこぼれ出ているのをみて、それを入れてやろうとそっと握ります。まだ温みがあるその手がひどく荒れてざらざらしているのに気がつきます。
半通夜がおわり、弔問客は帰って行きます。
「格之助と金三郎で伽をする、遠慮無くさがるように」と若侍や女達に云います。しばらくしても誦経の声が響きます。家氏のしもべの女房らが一夜の伽をしたいといって奥に座っているのです。亡き妻を実の親のように慕っていたのです。藤右衛門は自分の知らなかった妻の一面を知ります。
葬儀の後も、夜ごと夜ごと、彼の耳に母屋のほうで音をしのばせて誦経する人声がかすかに聞こえます。むせぶような念仏の声も伝わります。仕えていた女房たちです。その声は肺腑をしぼるようで、嘆きがこもっています。どうして妻はあれぼどの嘆きを彼らに与えるのか、彼らにとって妻はそれほど大きい存在だったのかと藤右衛門は校閲の筆を休めて、想いに耽ります。
格之助に、妻やすの形見を女房たちにわけるように命じます。女房頭のそよが箪笥をあけ引き出しからつぎつぎと衣類を取り出します。それはみな着古した木綿物です。洗い抜いて色がさめたもの、継ぎをあてたものばかりです。藤右衛門はなかばあきれて訊きます。
 「そのほかもうないのか、まったくこれでお終いなのか、、」
「そのほかもうないのか、まったくこれでお終いなのか、、」
「、、、はい、お納戸の長持にはまだお古着もありますが、継ぎはぎもならぬほどの品です」
「人の目に触れれば恥ずかしいゆえ、おりをみて焼き捨てよ、との仰せでござりました」
あまりに粗末な品々です。藤右衛門は呆然とした気持ちで格之助の顔を見ます。
「これではいかにも見苦しすぎると思うが、どうか、、」
「母上が身におつけになった品ですから、お遣わしになってよろしいかと存じます、わたしもなみに一枚頂戴いたします」
そよはすり寄って衣類を敷居ぎわに運び、平伏している女房達に云います。
「旦那様のおぼしめしで、亡き奥様のお形見わけをいたします、、」
「ここにあるのが、紀州さまご老職、千石のお家の奥様がお召しになったお品です、わたしたちには分にすぎたくだされものをあそばしながら、ご自分ではこのようなお品をお召しになっていたのです」
「、、この色のさめたお召し物をよく拝んでください、継ぎのあたったこのお小袖をよく拝んでください、」
そよの喉へ嗚咽がせき上げます。女房たちも声をころしてむせぶのです。
藤右衛門は格之助に云います。
「やすはどうしてあのような見苦しいものを身につけていたのだ、わしは少しも気がつかなかった、本当にあんなものしか持っていなかったのか?」
「母上はつましいことがお好きでございました」
「母上はいつかこのように仰せられていました、、、、武家の奥はどのようにつましくとも恥にはならぬが、身分相応のご奉公をするためには、常に千石千両の蓄えを欠かしてはならぬ、、」
「それをおまえに云ったのか?」
「いえ、なみを娶ったとき、あれにそうお諭しくださったのを隣の部屋で聞いたのです」
皮膚の荒れた手とつましい暮らしを知ったとき、これほどのことにどうして気がつかなかったのだろうかと、藤右衛門は妻のやす女に向かって呟きます。
「おまえは、わしに世にあらわれざる節婦がいかなるものかを教えてくれたぞ、、」
そして稿本の「松の花」を再び開きしずかに朱筆をとりあげます。