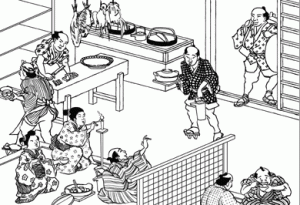山本周五郎の「荒法師」を紹介します。
武蔵の国にある臨済宗の古刹に昌平寺があります。そこに荒法師と呼ばれていた俊恵という僧がいました。もと土地の貧しい郷士の子で幼いとき孤児となり昌平寺に引き取られます。十八歳になり京へのぼり、最古の伽藍である東福寺にはいり建仁寺からさらに鎌倉の円覚寺で修行します。六尺近い体格、一文字を引いた眉、光る眼、全てが逞しい姿の僧になります。「いかにも荒法師という風だ」とその名が近在に広がります。
俊恵の修行は、生死超脱という難題に向き合ったことです。俊恵は云うのです。いちど死に逢うやすべてあとかたもなく消え去る。この世にあって存在の確かなるものは、まさに「死」においてほかにない。かくて死はすべての消滅でありながら、しかも唯一のたしかな存在である。この矛盾をどう解すべきか、、、、、



 あらゆる生物はやがて死滅する。同時にあらゆる生物が生ききるのも事実ではないか。生物は死ぬるまで生きる。死が否定しがたいものであるなら、生もまた否定できない。死が必ず現前するものだとすれば、むしろ生きてあることを肯定し、そのまさしい意識を把握すべきだ、生死の超脱は生きることのうえに成り立たなくてはならない、俊恵はその一点に向けて修行していきます。
あらゆる生物はやがて死滅する。同時にあらゆる生物が生ききるのも事実ではないか。生物は死ぬるまで生きる。死が否定しがたいものであるなら、生もまた否定できない。死が必ず現前するものだとすれば、むしろ生きてあることを肯定し、そのまさしい意識を把握すべきだ、生死の超脱は生きることのうえに成り立たなくてはならない、俊恵はその一点に向けて修行していきます。
武蔵国に石田三成の軍勢が攻めてきます。忍城という北条の出城が昌平寺の近くにありました。三成の指揮下にあった浅野軍の使者が昌平寺を本陣に使いたいと申し出ますが、慧仙和尚は断ります。そのため昌平寺は焼き払われます。昌平寺の近くに住む花世という娘が俊恵のもとにきて、討ち死にした人々を弔ってほしいと云ってきます。俊恵は出掛けて数珠をつかみながら読経していきます。形容し難い惨状の前で俊恵は唱えます。
「、、なお十万の諸仏、仰ぎ願わくは愛護の御手を垂れて、、、、」俊恵は念仏唱名しながら一人ひとり供養していきます。
一人の武者の前に立ち、静かに経文を唱えはじめると、ふいにその武者が「御坊無用だ、、、、」と激しい口調で云います。微かに呼吸があります。
「もうながくない、もうそのときはみえている、」
「しかし経文は読むに及ばないぞ」
「なぜ経文は無用だと仰しやる?」
「おれは、、、」
「おれは成仏するつもりはないからだ、、、」
「生きて命のある限り、死ねば悪鬼羅刹となって十たびも、十たびも人間になって生まれかわり、あくまで父祖の国土は守護し奉る、これがもののふの道なのだ、おれだけではないぞ、、」
「断じて成仏せず、、」
俊恵はかっと眼をひらき叫びます。「そうだ、これだ、ここにあった。」武士の信念に生死超脱の境地をみるのです。
「唯今のご一言、肝に銘じました。こなたには及ばぬまでも御遺志を継いで城に入ります。ぶしつけながら鎧を借り受けます。」
俊恵は忍城に入り、攻撃する浅野の軍勢に向かいます。真一文字に突っ込むさまは凄く、群がる人数の中でも一歩もひかず奮戦した闘い振りも類の無いものでした。浅野軍の兵たちも後に「あれはたしかに名のある武士だったに違いない」と云います。「あとにもさきにもあれほど大胆不敵な闘いぶりをする者を見たことがない、敵ながら全く惜しい武士だった」と振り返るのです。