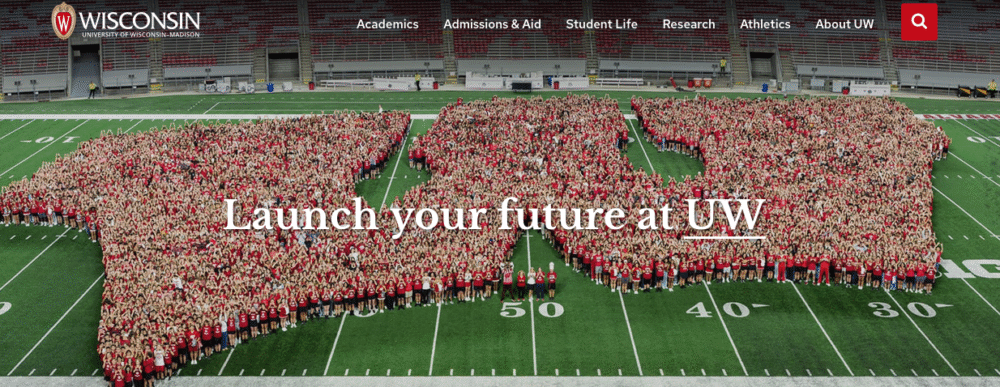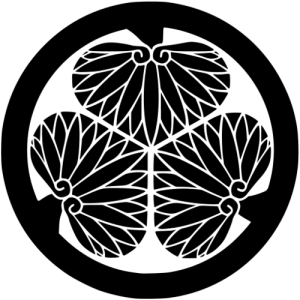吉村弥十郎は九百五十石の中老で、槍組と鉄砲組を預かっています。頭がよく、容姿も抜きんでいます。十四歳のとき、論語の講義を受け一年間の講義が終わった時は短刀と銀二十五枚をもらいます。十五歳になって「みちあけの式」が済んでからは、すべてに磨きがかかってきます。
「みちあけの式」は吉村家に伝わる独特の家法です。事前になにも知らされず、式の間という部屋に寝かされます。闇の中で寝ているとやがて女がきて、同じ夜具の中にはいります。
「わたしのするとおりなさいまして、ようございますね」
「さあ、ゆったりとなすって」
初めての夜、女はそう囁きます。そして夜の明ける前にでていきます。
弥十郎は学問と同時に武芸にも身を入れ、めざましく上達しますが、決して他人に気づかれず、総試合のときもつねに中軸の位置を保ちます。弥十郎に北島という家との縁談話がおこります。ところが祝言を間近にして、娘の健康がすぐれないので、祝言を延ばしてもらいたいといってきます。弥十郎は他から紹介されたことでもあり、急ぐこともないので了承します。
中村座に「ゆき」という年増の女中がいます。弥十郎は茶屋に時々でかけます。ゆきが一人の女を紹介します。そして云います。
「川西という茶屋があります、そこにお越し下さい」
「わたしのお仕えするお嬢様でお名は千夜と仰います」
「どうぞおらくにあそばして、、」
弥十郎は川西で千夜と七たび会います。二人の間はだんだんと密になります。「もうおまえの他に妻を娶る気持ちはない」
「どんなことをしても約束のほうは破談にする」
「うれしゅうございます」千夜は囁き返して云います。
二人は再会を約束するのですが、それ以来、千夜はぴたりと消息を絶ちます。
弥十郎が仕える藩主は信濃守政利です。十七歳で結婚するのですが、夫人や側室が二、三人いても四十七歳まで子どもがいません。やがて藩公に世子が生まれたという知らせがまわります。「ひなというお部屋様の手柄だ、、」と藩の重臣たちは喜びます。ひなはやがてその一字をとって「奈々の方」と呼ばれるようになります。しかし、世子が藩主の胤であるかどうは疑わしかったのです。
弥十郎はやがて「奈々の方は千夜と同じ人ではなかったのか、」と思うようになります。吉村家には藩公の血が続いているという父親の言葉が弥十郎をとらえます。