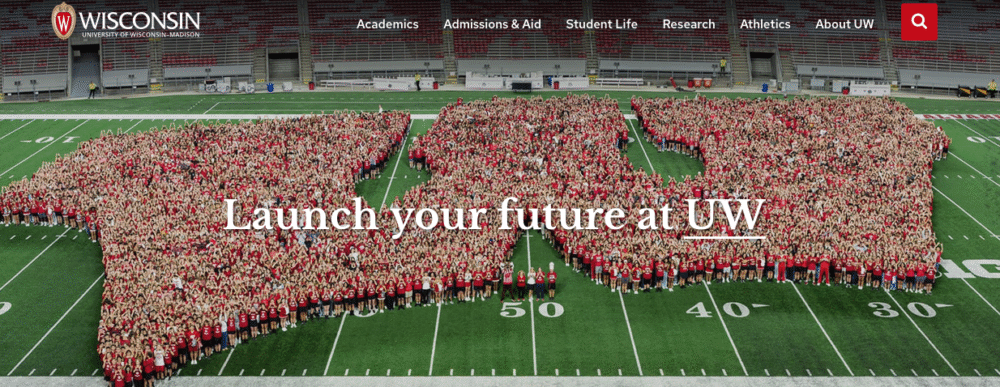この時代、理念政治は大政党ではなく、小政党によって代表されました。反メーソン党(Anti-Mason Party) は、権力者の陰謀とされるものを一掃することを目的としていました。労働者党(Workingmen’s Party)は、「社会正義」を唱えました。ロコフォコ党(Locofocos) は民主党の分派で、1835年から1840年代にあった党です。内外の独占主義者を糾弾し、敵対勢力によって暗くなった会場で最初の会合を開いたときに使ったマッチにちなんで名付けられたといわれます。
様々な名前の民族主義政党は、群小政党とよばれます。こうした小政党は、異口同音にローマ・カトリック教会のあらゆる悪事を告発し、自由党は、奴隷制の拡大に反対します。これらの政党は、本来の有権者に加え、多くの有権者を惹きつけるような幅広いアピールをすることができなかったため、どれもはかないものとなりました。
民主党とホイッグ党は、その日和見主義にもかかわらず、また日和見主義であるがゆえに、アメリカの有権者の現実的な精神をよく反映して繁栄して、1828年結成の民主党と1854年結成の共和党となっています。結党当初は民主党が保守派、共和党が進歩派に位置付けられていましたが、20世紀始めに逆転しています。
1830年から1850年にかけての時代を歴史家は「改革の時代」と呼びました。ドルの追求が熱狂的になり、それを国の真の宗教と呼ぶ人もいた時代です。何万人ものアメリカ人が精神的、世俗的な向上を目指す様々な運動に参加していきました。なぜ、前世紀末に改革運動が起こったのかについては、まだ意見が一致していません。プロテスタント福音主義の暴走、イギリスやアメリカ社会全体を覆う改革精神、啓蒙主義の完璧主義的な教えに対する遅れ、19世紀の資本主義の特徴である世界的な通信革命など、いくつかの説明が挙げられますが、いずれも決定的なものではないようです。
女性の権利、平和主義、禁酒、刑務所改革、借金による投獄の廃止、死刑廃止、労働者階級の待遇改善、国民皆教育制度、私有財産を捨てた共同体の組織化、精神異常者や先天性障害者の待遇改善、個人の再生などが、この時代の熱狂的な人々を刺激するさまざまな改革運動を北アメリカで同時に盛んにした原因でありました。
アメリカ人の生活で注目すべきことは、経済的な飢餓と精神的な努力の組み合わせということです。どちらも、未来はコントロールし、改善することができるという確信の上に成り立っていたことです。辺境での生活は過酷だったはずですが、人間が置かれた状態は必ず良い方向に変化するという強い信念があったことです。かつてカルヴァン主義が予言したように、神の意思を個人の意思や行動で左右することはできなく、無条件で救われるという確信です。
フリーメイソン(Freemasonry)は、16世紀後半から17世紀初頭に結成された友愛結社で「全人類の兄弟愛という理想の実現」「文明というものがもつ真正で最高の理想実現」等を目的とすると謳っています。後のロータリークラブ(Rotary Club)やライオンズクラブ(Lion’s Club)の前身といわれます。