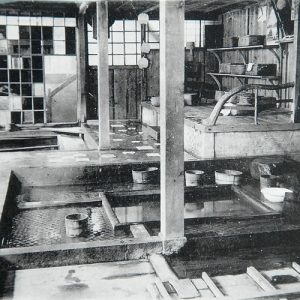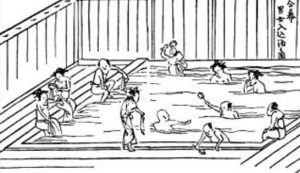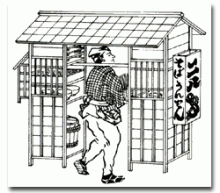雪の北陸路、今庄という小さな町の旅籠で冲也は、病床から呟きます。
「おれは浄瑠璃で生きる決心をし、一生を賭けても自分の浄瑠璃を仕上げようと、そのことにぜんぶを打ち込んでやって来た、これからも、生きている限りやりぬいてゆくだろう、――だが、この道には師もなければ知己もない、師にまなび、知己に囲まれているようにみえても、つきつめたところは自分ひとりだ、誰の助力も、どんな支えも役には立たない、しんそこ自分ひとりなんだ」
「おれは自分にできる限りのことをした」と冲也はまた云います。
「自分の力でできる精いっぱいのことをした、それがこんなことになってしまった、こんなみじめなざまに、――どうしてだ、どこで間違ったんだ、おれのどこがいけなかったんだ」



 「男が自分の仕事にいのちを賭けるということは、他人の仕事を否定することではなく、どんな障害があっても屈せず、また、そのときの流行に支配されることなく、自分の信じた道を守りとおしてゆくことなんだ」
「男が自分の仕事にいのちを賭けるということは、他人の仕事を否定することではなく、どんな障害があっても屈せず、また、そのときの流行に支配されることなく、自分の信じた道を守りとおしてゆくことなんだ」
おけいは江戸にいるお京へ急飛脚をの手紙を出します。冲也の容態が非常に悪くなってきたからです。夜半ごろ、おけいがまだ寝床へ入る前に、名を呼ばれたように思います。いってみると、冲也は眼を大きくみはり口を開けて囁いています。
「なにかおっしゃって、」
「ああ、」といって眼が一点に向けられたまま動かなくなります。
冲也が亡くなって三日目、お京と冲也の弟子、常磐津由太夫が遺骸を引き取りにやってきます。その宿でお京とおけいが対面します。おけいは冲也の浄瑠璃に対する凄まじい執念と意志、どんなことであろうと本気でやろうとしたこと、人のおもわくなんぞ気にせず生き抜いてきた冲也を尊敬してきました。
「苦労したのね」
「できないことだわ、あたしなんかその半分もできやしないわ、、」お京がおけいに云います。
「なにか遺言のようなものはなかったかしら、、」
おけいはちょっと考えて、立ち上がって三味線をとり、調子をあわせながら遺言というのではないが、と断ってから唄いだします。
「いい唄だわ、」
「、、でもこうなってみると、しょせんうちの人は端唄作者だったのね」
おけいは口をあけ、眼をみはります。
「失礼ですが、、」とおけいは感情を抑えます。
お京は長旅で疲れたと云って宿に戻ります。おけいは遺骸に向かった座り直します。
「、、、いまのお京さんの云ったことをお聞きになりましたか、しょせんあなたは端唄作者だって、」
「ひどい、あんまりだわ、あなた、あんまりじゃありませんか」
冲也の死顔の目尻から涙のようなものが一筋、糸をひいたようにしたたり落ちます。