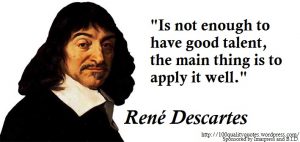原題は「Im Westen nichts Neues」、英語は「All Quiet on the Western Front」という小説です。作者はドイツ人エーリヒ・レマーク(Erich Remark)。第一次世界大戦が始まったのは1914年8月です。それらか4年間の戦いで集結しますが、フランス、ドイツ、イギリス、カナダ、アメリカらの兵士や市民あわせて326万人が犠牲となります。



 この小説は、兵士達の勇敢で英雄的な行為を賛美するものではなく、兵士達が置かれた過酷な状況を描いています。絶え間ない砲撃や爆撃の不安、戦いの間の単調な時間、食糧難、訓練不足の兵士の消耗や生死が語られます。主人公はポール・ボイマー(Paul Baumer)というドイツ軍兵士です。学校の教師から従軍するようにかきたてられて入隊するのです。作者レマークも従軍し負傷して戦線を離脱してからこの小説を書いたといわれます。ポールとはレマークのことのようです。22か国語に翻訳され250万部も売れたといわれます。
この小説は、兵士達の勇敢で英雄的な行為を賛美するものではなく、兵士達が置かれた過酷な状況を描いています。絶え間ない砲撃や爆撃の不安、戦いの間の単調な時間、食糧難、訓練不足の兵士の消耗や生死が語られます。主人公はポール・ボイマー(Paul Baumer)というドイツ軍兵士です。学校の教師から従軍するようにかきたてられて入隊するのです。作者レマークも従軍し負傷して戦線を離脱してからこの小説を書いたといわれます。ポールとはレマークのことのようです。22か国語に翻訳され250万部も売れたといわれます。
西部戦線は、ドイツとフランスの国境沿いのことです。ルクセンブルグ(Luxembourg)、ベルギー(Belgium)をまたぐフランスの重要な防御線です。この西部戦線ではドイツとフランス軍が対峙し、一進一退の突撃や塹壕線が続きます。この膠着状態を打開するために始めて毒ガス、飛行機や戦車が投入されます。
ポールはある時、偵察を志願しそこでドイツ兵と白兵戦になり始めて相手を殺すのです。長く苦しむ兵士を目の当たりにして、彼のうえに悔いや良心の呵責、そして赦しの感情がこみ上げてくるです。