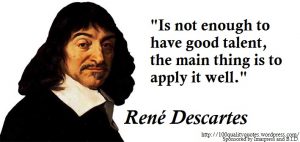Last Updated on 2024年12月31日 by 成田滋
フランスの思想家は日本人に知られ、思想界に広く影響を与えてきたように思えます。その代表といえばジャン・ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau)、ヴォルテール(Voltaire)、シャルル・モンテスキュー(Charles Montesquieu)などの啓蒙主義を代表する人物です。さらにミッシェル・フーコ(Michel Foucault) 、オーギュスト・コント(Auguste Comte)など多彩な思想家を生んだのがフランスです。
どうしてこうした思想家が輩出したのでしょうか。それはフランスの教育制度にあるような気がします。フランスの学校は基礎知識を徹底的に教え込むのです。そして考える力や文章力をつけるということを指摘したのは「遙かなノートルダム」の作者森有正氏です。「方法序説」の原題はフランス語ですが、英語では「Discourse on the Method」とあります。「方法に関する講話」とでも訳しておきましょう。
デカルト(Rene Descartes)は少しでも疑わしいものは一応真理でないとして退け、まったく白紙から始めようと提案します。これは私にとって非常に興味をかきたてられる言葉です。彼はさらに言います。「違う文化を見るべし」とか「常識を無条件に受け入れるな」と。ところが、どうしても疑えない真理として彼に残ったのは、自分が疑っているという事実であり、疑うところの「わたし」の存在でありました。こうしてデカルトは「わたしは考える。だからわたしは存在する」ということを哲学の第一原理として宣言します。ここにデカルトの偉大な貢献があります。
「方法序説」は、デカルトの哲学を概略的に理解できる格好の書物です。彼の思想的な発展のあとをたどることができ、その考え方は現在にもに通じ応用することができるという意味で、この本の価値は大といえます。そのことを少しだけ解説してみましょう。
デカルトは自分自身の論理は、次の4つに集約されると主張します。
1) 真実だと明白に認識しない限り、真実とは受け取らない。
2) 問題は常に小部分に分解して解決する。
3) 単純なものから、複雑なものに順を追って解決する。
4) 思考に落ち度がないかどうか、確証を得る。
「われわれは嬰児として理性をよく使えないうちから、感覚するものについて真偽さまざまに判断をくだしているし、そうして出来てしまった多くの考えが、いま真理を知るさまたげとなっている。そういう考えからまぬがれるためには、いつか一度、少しでもたしかでないと思われるものは、みんな疑ってみるよりほかに仕方がないように思われる。」