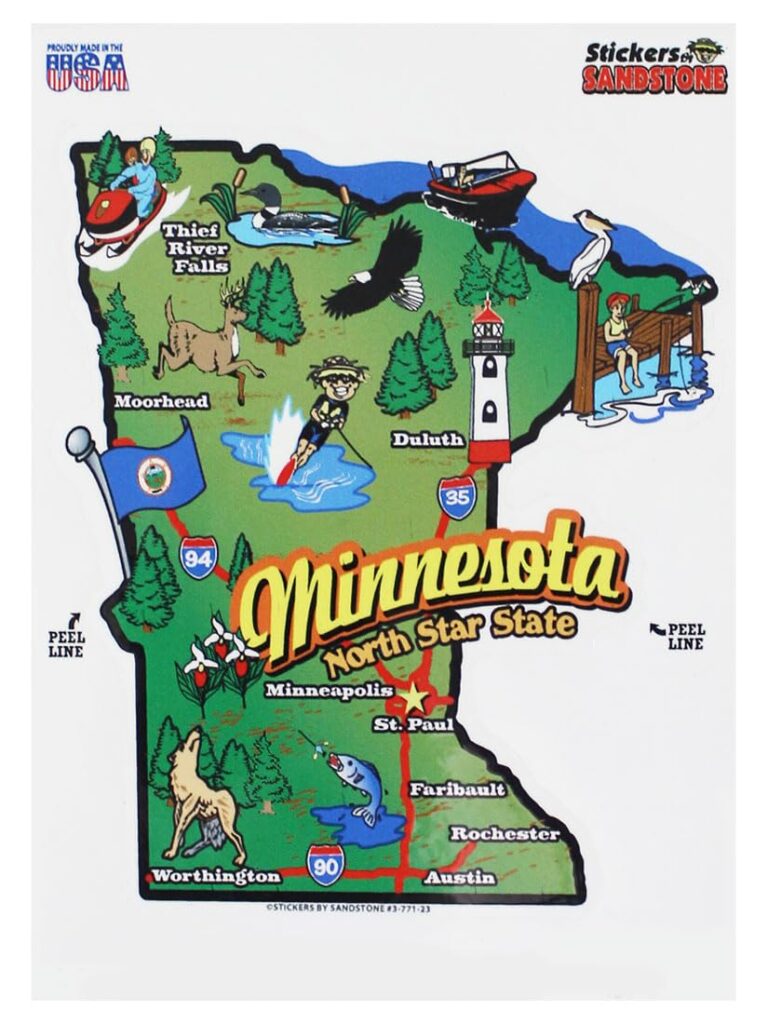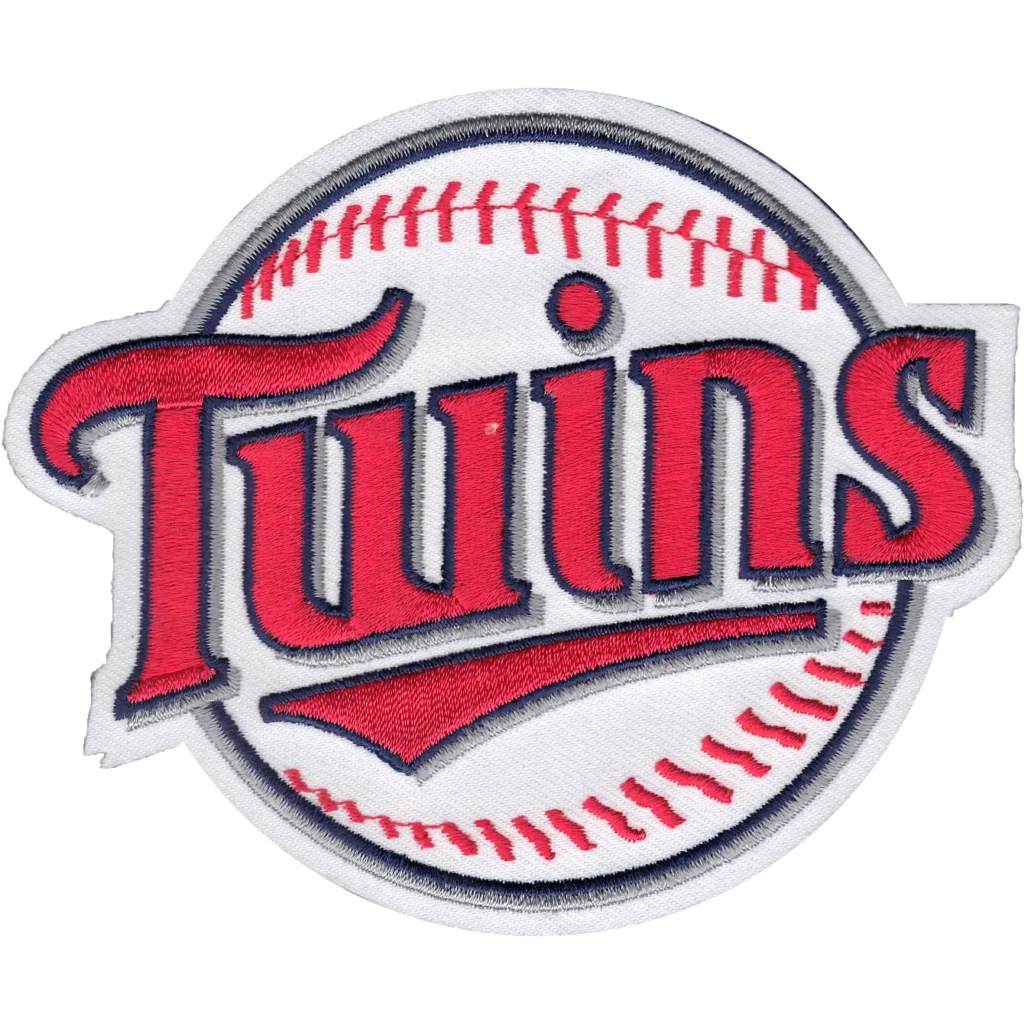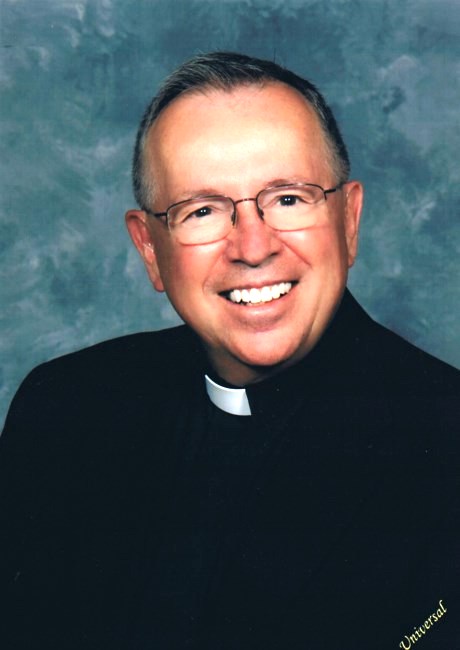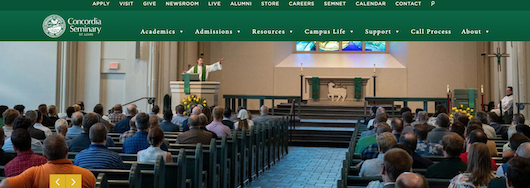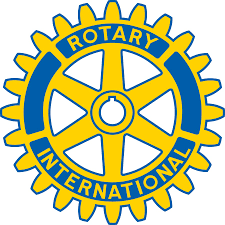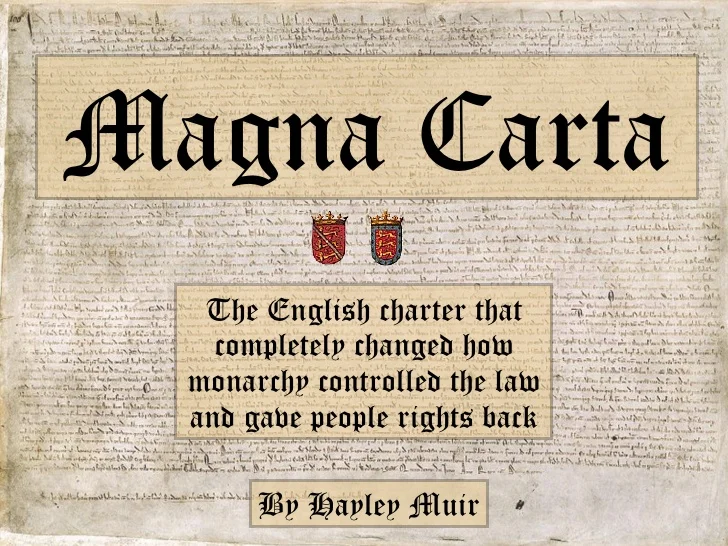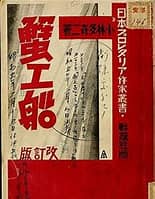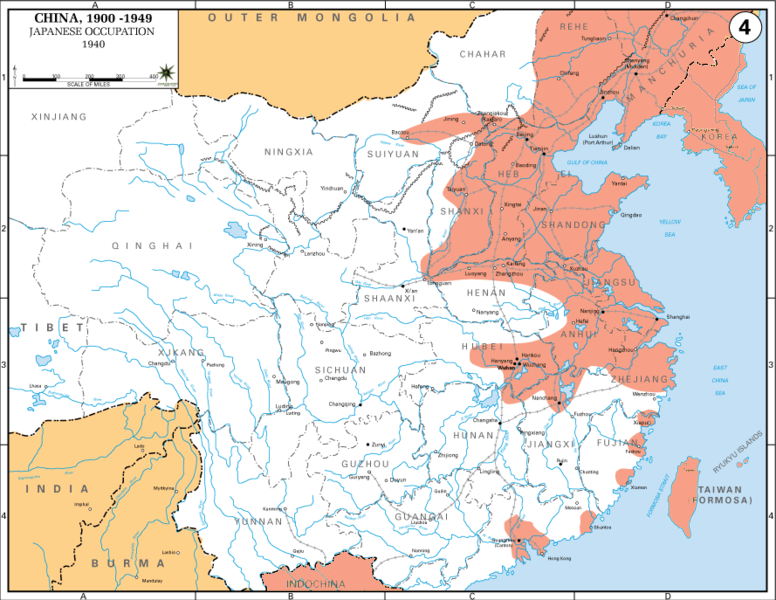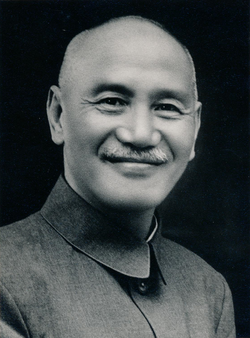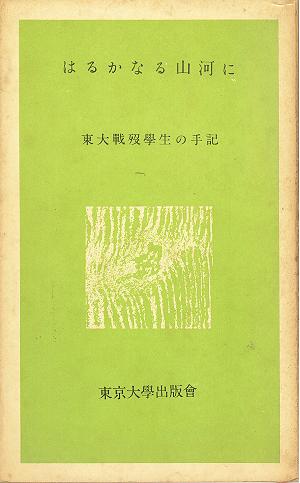ウィスコンシン大学ではいろいろな先生から指導を受けました。そのお一人が今回紹介するジェームズ・マッカーシー教授(James McCarthy)です。この先生のご専門は障がい児教育の評価と測定といういわば統計学です。特に単一被験者とか少数被験者の教育や実験計画(single subject experimental design)で得られたデータの分析です。行動科学などの分野での研究では統計が重要視されます。数量的なデータを処理し、何らかの結論を導き出す必要がある場合が多いのです。数量的なデータの処理とは、単純な集計のように事実を数値で要約することか、児童生徒の行動観察やテストの結果から成績表をつけるということもあるでしょう。
障がい児教育の分野では、障がいのない子どもと異なり、子どもの数が少ないのです。例えば、ある科目において1学年遅れのある子どもは、母集団と呼ばれる全2年生の15%位だろうと察します。母集団の成績は、グラフで表すと釣り鐘の形をします。これは通常正規分布といいます。母集団の成績のデータには、最頻値、中央値、算術平均があります。しかし、学習に困難を示す子どものある特性は、正規分布からかなり離れていることが多いのです。
一例として、ある県における自閉症的傾向を示す子どもの出現率は男子、女子の比は4:1であるとします。そうすると、日本全国にいる同じような行動上の特徴を示す子どもの出現率も4:1での割合で推測できるかもしれません。このような判断をするのを推測統計といいます。別な例で言いますと、2025年7月20日の参議院議員選挙で、投票所での出口調査の結果、投票が締め切られた瞬間に当選確実、と発表できるのは推測統計によるからなのです。この場合の出口での投票者数は標本と呼ばれ、全投票者数は母数と呼ばれます。つまり、標本の結果は母数の結果とほぼ一致するのです。ただし、この場合、標本と母数の誤差は5%以下といわれます。このような統計手法は、『母数による検定』、別名パラメトリック法(parametric) といいます。
しかし、標本数が限られている場合は、『母数による検定』は使えません。そこでそれに代わる検定として『母数によらない検定』、別名ノンパラメトリック法(non-parametric) があります。マッカーシー教授は『母数によらない検定』の基本的な前提、手法、検定の仕方を詳しく院生に教えてくれたのです。すこし、統計的検定のことを説明します。検定とは、ある種の仮説についての検定であり、この仮説を採択すべきか、棄却すべきかを調べます。その判定基準は適当に定めた確率である危険率によるのです。危険率とは通常.05とか5%が使われます。5%とは20回のうち1回は間違いを起こすことがあるが、それは無視してよいというのが統計です。
マッカーシー教授の講義で思い出深いのは、講義の他に統計手法の使い方の実習時間をとってくださったことです。通常、大学では講義で終わりなので、実習時間をとってくれることはありません。それも朝の8時からなのです。必ずベーグルとかクロワッサンを持参して院生に振る舞ってくださるのです。この日は、院生は朝食抜きでやってくるのが通例でした。その他、ミルウォーキー(Milwaukee)での学習障害の学会にも院生を同伴してくださったり、夏はマディソン郊外でのシェークスピア(William Shakespeare)の野外劇にも連れて行ってくれるなど、実に気さくで面倒見の良い先生でした。マッカーシー教授には博士論文の審査委員のお一人にもなっていただきました。後に就職した国立特別支援教育総合研究所時代に『障がい児教育のための統計情報処理入門ーノンパラメトリック法を中心に』という120ページの小冊を刊行できました。これも先生の薫陶によるお陰です。2012年4月に逝去されたことを大学のWebサイトで知りました。