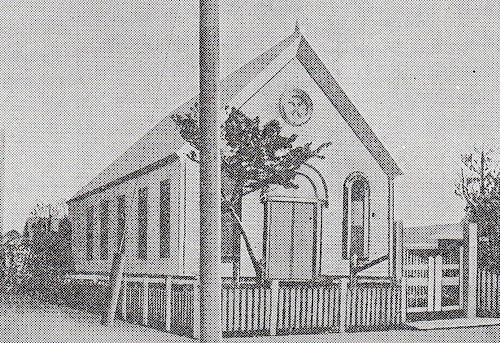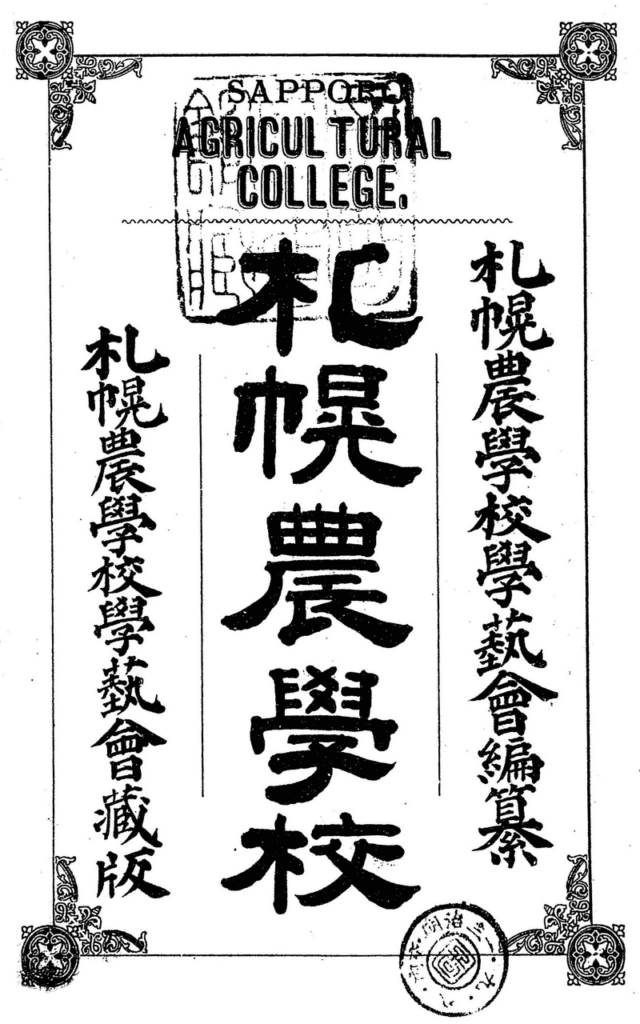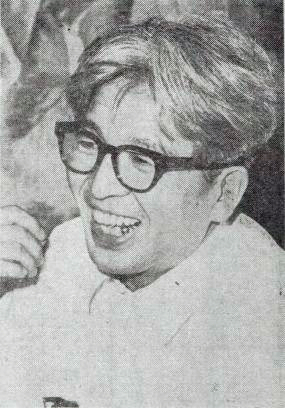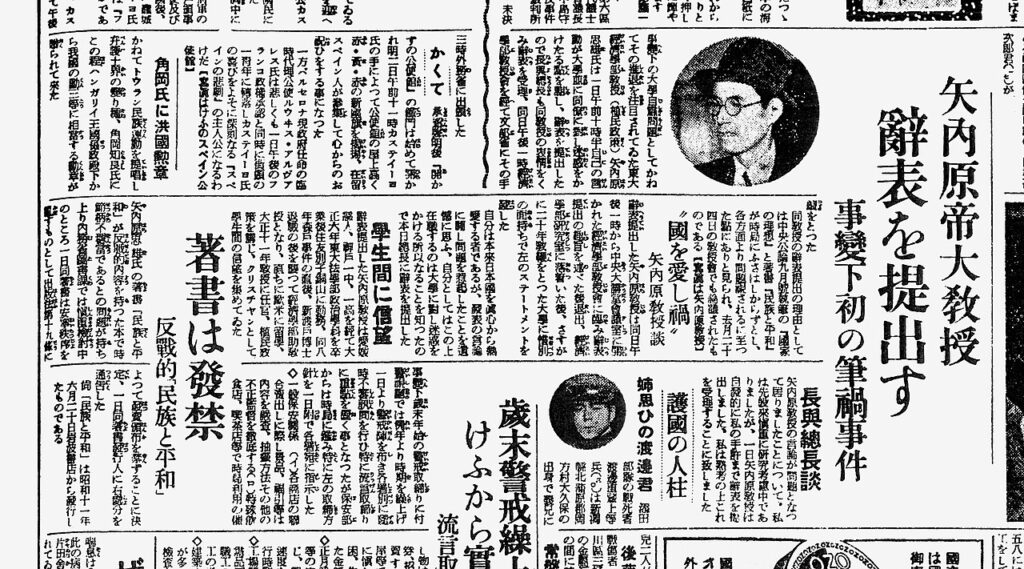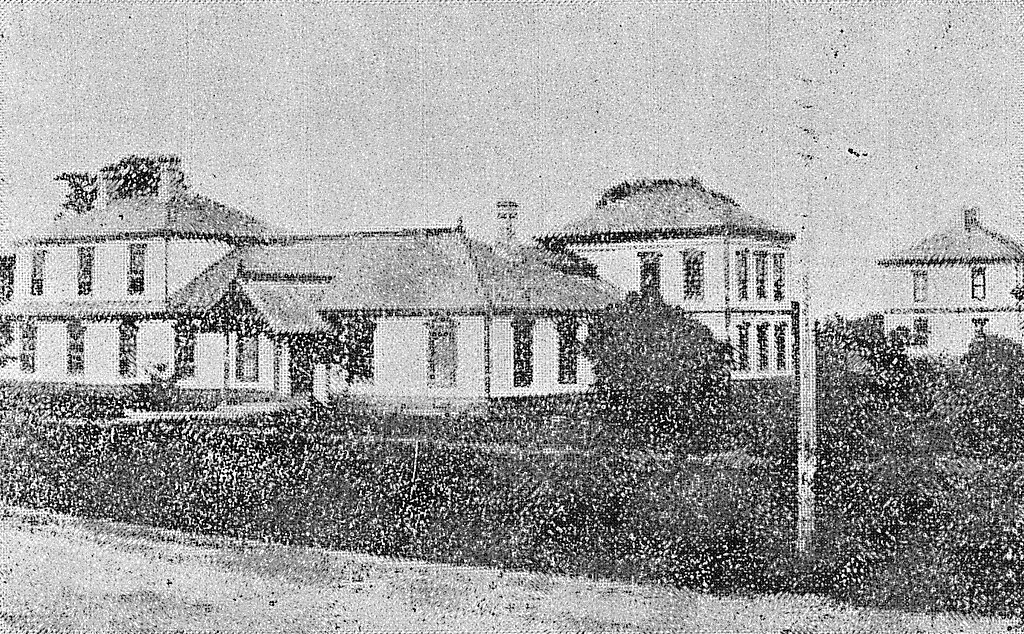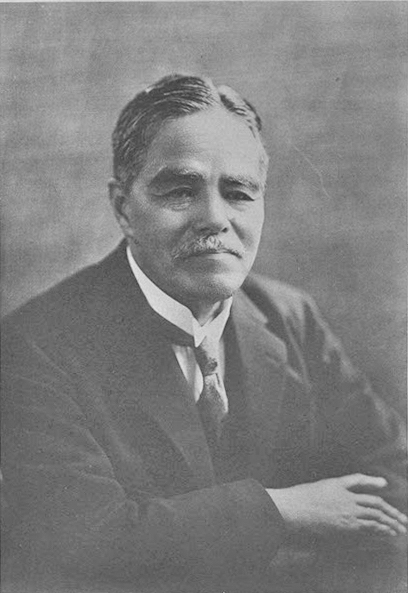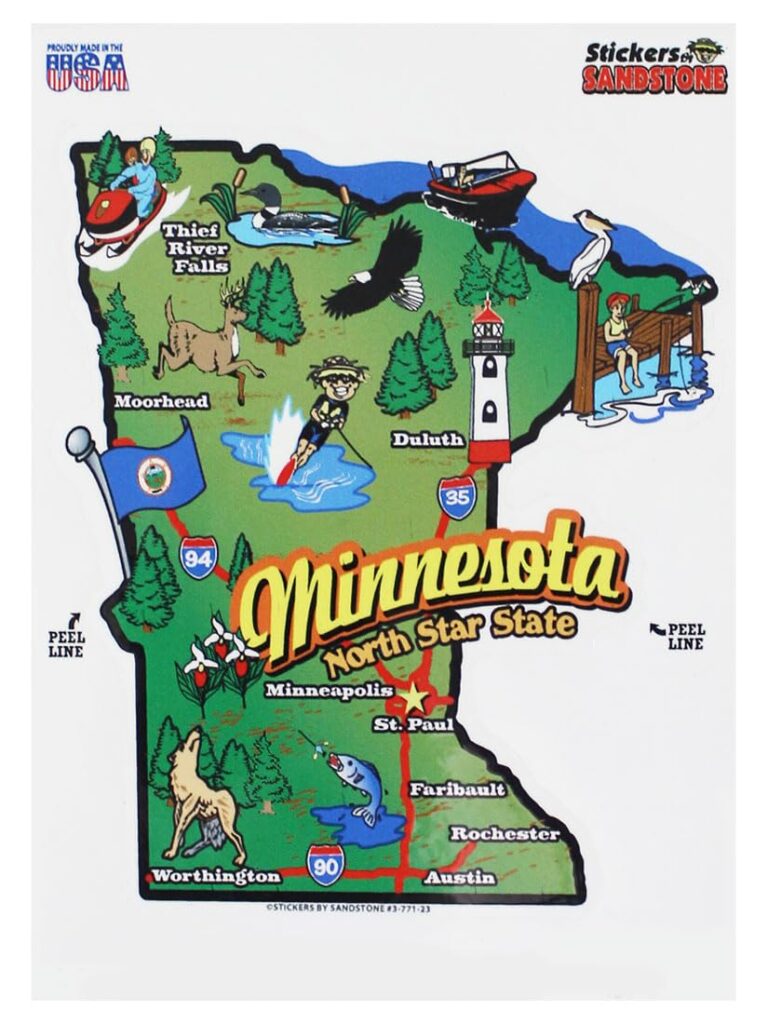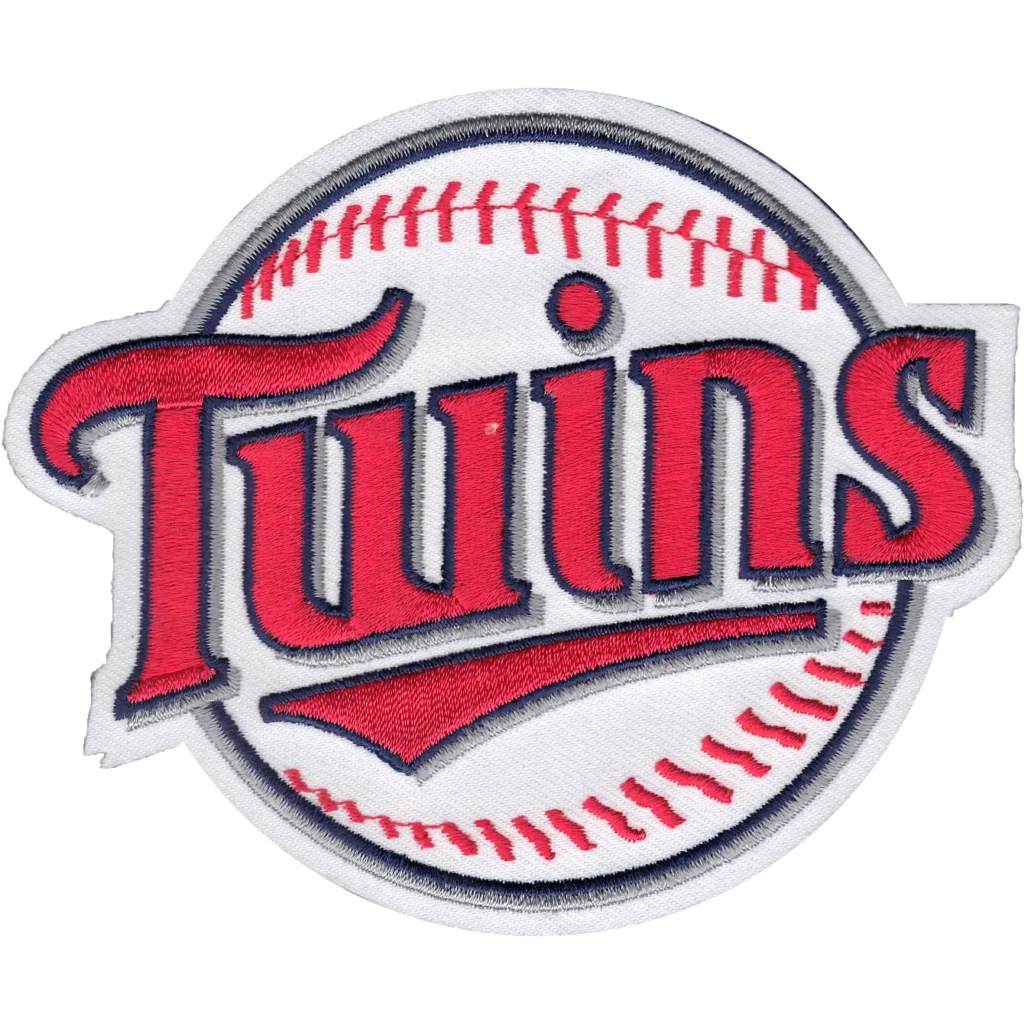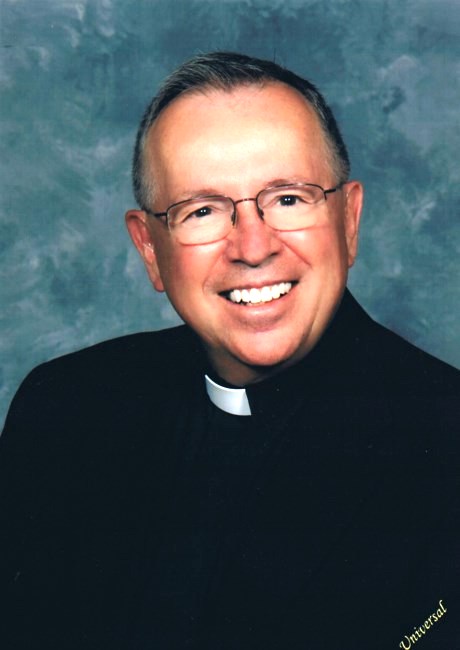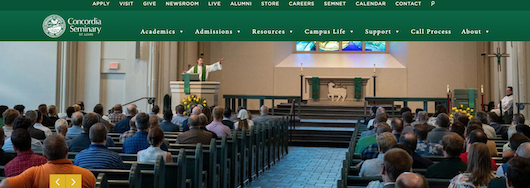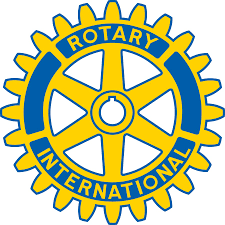『内村鑑三信仰著作全集』は全25巻からなります。そのうちの19巻に「余の北海の乳母ー札幌農学校」というエッセイがあります。19巻は95篇の論説からなり、信者にとって最も重大な関心事である信仰生活の諸問題について内村がいかに考え、いかに対処したかたを語っています。内村が信仰生涯を論じ、それを語るにあたって、教義や信条に基づいて思考した結果ではなく、自分自身の体験に基づいてそのまま語り、説いていることがわかります。
内村は、札幌農学校から多くのことを学んだと述べています。例えば、「農学校は余に多くの善き事を教えてくれた。馬について、牛について、豚について、じゃがいもについて、砂糖大根について教えてくれた。これみな貴い知識であることは明らかである。」しかし、私たちにとって次のような驚くような記述もしています。「しかしながら、農学校は最も善き事を教えてくれなかった。」と述懐するのです。
さらに、「余は札幌農学校の卒業生である。そのことは事実である。しかしながら、余は札幌農学校の「産」ではない。」卒業はしたが、産ではないというのです。そして「神について、キリストについて、永生については、少しも教えてくれなかった。これは余が札幌農学校以外において学んだ事である。」と書いています。これは興味ある記述です。
内村は次のようにも言います。「余の札幌農学校に対する関係は、子がその母に対する関係ではない。乳児がその乳母に対する関係である。札幌の地を去って、マチューセッツの地、ペンシルヴァニアの丘において、人に由らざる教えを受けた。札幌は余をこの世の人にしてくれたかもしれない。しかしながら、神の子たるの資格を世に授けてくれたところは札幌ではない。余が札幌農学校の産ではないというのは、これがためである。」
札幌農学校を乳母に譬えて、内村は農学校を女性名詞を使います。
「彼女を囲む天然は日本国第一等である。彼女の南にそびゆるエニワ岳、彼女の東を流るる石狩川、彼女の北を洗う日本海、彼女の西をさすテイネ山、彼女を見舞う渡り鳥、彼女を飾る春の花と秋の実、これありて、余は彼女を囲む天然に養われたる者である。」
「しかしながら、余は摂理の神が余を、余の乳母、札幌農学校に託したまいしを感謝する。余は余の青春時期を北海の処女林の中に経過するの機会を与えられしを感謝する。」
内村は札幌農学校に育てられたとは言わず、むしろ農学校を囲む自然に養われた者だ、というのです。このような述懐は、内村が農学校の教育に傾倒し心酔していた、という一般の見方を変える必要があると思われます。