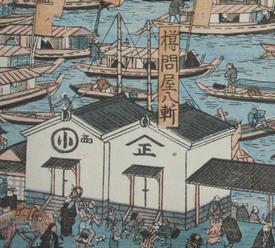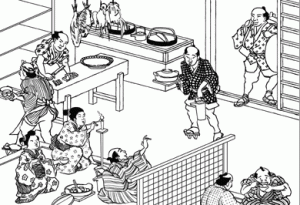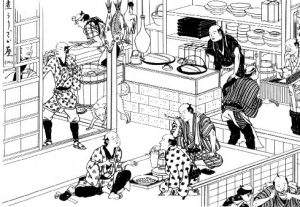加代と直輝という夫婦と姑の物語です。加代は歌作りに励んでいます。あるとき「寒夜の梅」という歌を作ります。直輝の母、かな女が数冊ある短冊を見ながら云います。
「みごとにお詠みなすったこと、本当に美しくみごとなお歌ですね」
「でももうお歌はこのくらいにして、またなにかほかの稽古ごとをおはじめなさるのですね、」
直輝は加代のようすがいつまでも沈んでみえるのに気がつきます。ある夜、そっと妻の部屋にいくと、加代は灯のかげで歌稿を裂き捨てています。
「どうしたのだ、、」
加代はだまって悲しげな眼をあげ、すがるように良人を見上げます。直輝はその眼をみて事情を了解します。
「母上が仰しゃったのか、、」
「、、、はい」
「加代は不束者でございますから、母上さまのお気に召すようには甲斐性もございませぬ、、、」
「体が弱いためお子をもうけることもできませぬし、、」
「もうおやめ、それ以上はわかっている」
直輝はやさしくさえぎります。


 母の気性がと云いかけたまま、ややしばらく黙っていた直輝はやがて妻を励ますように云います。
母の気性がと云いかけたまま、ややしばらく黙っていた直輝はやがて妻を励ますように云います。
「ほかの事とはちがい、おまえの和歌の才だけはかくべつだ、、わたしからそれとなく母上にはなし申してみよう」
加代は良人の温かい気持ちを胸一杯にかんじながら、裂き残した歌稿をつつましく集めるのです。
明くる夜、直輝は隠居所をおとづれます。端ぎれを綴り縫いしている母はそれを仕上げているところです。なにがお出来になりましたときくと、加代にやる肩蒲団だと答えます。
「あの寝部屋は冷えますからね、それにあの人はあまりお丈夫ではないから、、、」
「それはさぞ珍重に存じましょう」
あくる朝、梅の蕾がおよそ四分がた、一斉に咲きだしています。かな女は加代を部屋に呼び入れます。
「今日はわたしの思いでばなしを聴いていただこうと思いましてね」
 「はい、うかがわせて戴きます」
「はい、うかがわせて戴きます」
「自分の口からこう云っては、さぞさかしらに聞こえることでしょうけれど、わたしは茶の湯の稽古でたいそう才をみとめられました、お師匠さまからも折り紙をつけられるところまでいきました、そのときわたしは茶の湯をやめました」
「良人も惜しんでくれました、、、つぎに笛のお稽古を、笛のつぎには鼓を連歌や詩、絵などもお稽古を始めました、でもわたしはどれも奥底まではゆかず、九分どおりでやめてしまったのです」
「加代さん、わたしが芸事をつぎつぎに変えたのは移り気からだとお思いになりますか?」
「学問諸芸にはそれぞれ徳があり、ならいおぼえて心の糧とすれば人を高めます、けれどその道の奥をきわめようとするようになると「妻の心」に隙間ができます、妻が身命をうちこむのは、家をまもり良人に仕えることだけです」
「わたし、あやまっておりました」
「、、、加代さん」
「もう仰るな、年寄りのぐちがいくらかでもお役にたてばなによりです、そしてそこの覚悟さえついておいでなら、歌をおつづけなすっても結構なのですよ」
やがてかな女は加代に云います。
「こんなものを作りました」
端切れを継いでつくった肩蒲団をとってそっと嫁のまえに押しやります。
「あなたのお寝間は冷えますから、これを肩にかけておやすみなさい、」
その日、城から帰った直輝は妻の顔色が見違えるように冴え冴えとしているのにおどろきます。