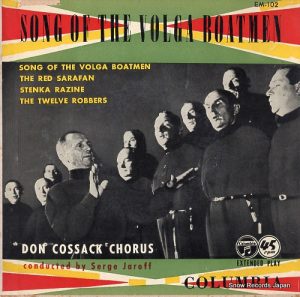ステッラは、1950年代から1960年代に活躍したイタリアの代表的な歌手です。彼女の活躍した時代には、二人の巨星といわれるソプラノ歌手がいました。マリア・カラス(Maria Callas)とレナータ・テバルディ(Renata Tebaldi)です。少し割を食ったのが、ステッラを含めた同じ世代のソプラノ歌手といえそうです。ステッラは、NHKイタリア歌劇団公演で3度にわたり来日しています。
女性の声の種類は、ソプラノ、メゾソプラノ、そしてアルトに分けられます。ソプラノにはいくつかの種類があります。よく聞くのがコロラトゥーラ(coloratura)で、歌いが速くコロコロと転がすような装飾が付くのが特徴です。もう一つはスピント(spinto)といって、情熱的で激しい感情をあらわす声のソプラノです。スピントのソプラノ役柄は例えば、「カヴァレリア・ルスティカーナ」(Cavalleria Rusticana)、「トロヴァトーレ」(Trovatore)、「ドン・カルロ」(Don Carlo)といった歌劇でしょう。
ステッラもマリアカラスもスピントの歌手といえそうです。19世紀中頃からのロマン派オペラから多く現われています。ヴェルディ(Giuseppe Verdi)やプッチーニの歌劇での歌唱で知られています。