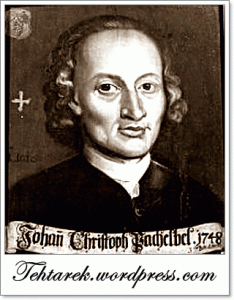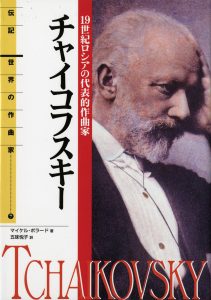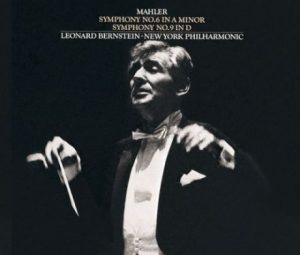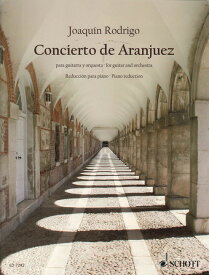ゾルタン・コダイ(Kodaly Zoltan)は1882年生まれのハンガリーの作曲家です。民俗音楽学者、教育家、言語学者、哲学者でもあります。両親は熱心なアマチュア音楽家で、父はヴァイオリンを、母はピアノを弾いていたそうです。コダイは子どもの頃からヴァイオリンの学習を始め、聖歌隊で歌いますが、系統的な音楽教育を受けることはありませんでした。
1900年、コダイは現代語を学ぶためにブダペスト大学(Budapest University) に入学し、同時にブダペストのフランツ・リスト音楽院(Franz Liszt Akademie)で音楽を学び始めます。そこでドイツ人でブラームスの音楽を信奉する保守的な作曲家といわれたハンス・ケスラー(Hans Koessler)に作曲について師事します。
1905年からコダイは、ハンガリーの北西部の辺境で民謡の収集を始めます。その結果をハンガリー民族学会で発表します。民謡について真摯に取り組んだ初期の研究者として、ハンガリーにおける民俗音楽学の分野における重要人物と称されるようになります。さらに1907年にはフランツ・リスト音楽院の教授に就任します。