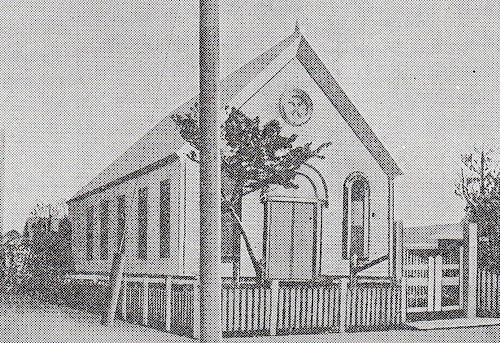内村鑑三が札幌農学校に入学した時には、ウイリアム・クラーク(William Clark) はすでに日本を離れていたので、直接の師弟関係はありません。クラークが札幌農学校に在任したのは1876年のわずか8か月間でした。ですが彼は学生たちにキリスト教的道徳観と「高潔な志を持て」という信念を強く植え付けたといわれます。その象徴が「Be gentleman」、「Boys, be ambitious」という言葉です。内村はこの言葉とその精神を先輩たちから聞き、強く感化されていきます。
クラークは札幌農学校でキリスト教の集会を行い、多くの学生を洗礼に導きます。彼の影響で、札幌農学校には「バイブルクラス(聖書研究会)」や信仰共同体が形成されており、内村が在学した頃にもその雰囲気が濃厚に残っていたといわれます。クラークが残した「イエスを信ずる者の契約」に一期生佐藤昌介らとともに署名します。佐藤は日本初の農学博士で後に北海道帝国大学初代総長となります。内村はこの環境の中でキリスト教に接し、1878年にメソヂスト監督教会のメリマン・ハリス(Merriman Colbert Harris)より洗礼を受けます。この経験は後の内村の「無教会主義」や独立した信仰姿勢の基礎となったといわれます。彼の生涯を貫いた「良心の自由」や「自己の信仰に忠実に生きる」という姿勢は、クラークの残した理想主義に通じます。
一期生の佐藤昌介らは、自主独立の教会を持ちたいとの気運が高まります。彼らが教会の独立に熱心だったのは、教派への反抗ではなく、独立することが信仰の自由のために本質的に必要だと考えたのです。当然ながら教会は外国宣教団に依存せずに、日本人信徒による独自の宣教活動を始めます。これが世に言う「札幌バンド」です。
内村鑑三は札幌農学校卒業後、農商務省等を経てアメリカへ留学します。1885年、アマースト大学(Amherst College)の三年次に編入し、ジュリアス・シーリー学長(Julius H. Seelye)らの指導で回心を体験し、福音主義信仰に立っていきます。後に同志社大学を創立する新島襄もアマースト大学で学んでいます。帰国後の1890年に第一高等中学校嘱託教員となります。1891年に教育勅語奉戴式で拝礼を拒んだ行為が不敬事件として非難され退職を余儀なくされます。以後著述を中心に活動していきます。
1900年に『聖書之研究』を創刊し、聖書研究を柱に既存の教派によらない無教会主義を唱えていきます。日露戦争時には非戦論を主張します。田中正造が中心となって反対運動を展開した足尾鉱毒事件では、内村鑑三もその運動を支援します。主な著作は1894年の『日本及び日本人、1895年の『余は如何にして基督信徒となりし乎』を英文で刊行します。その後精力的に著作や伝道活動に専心します。