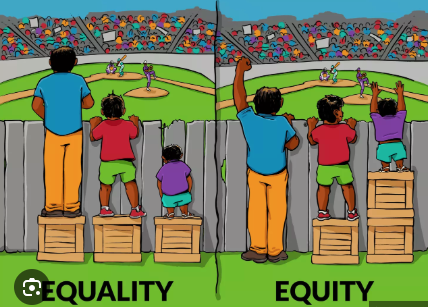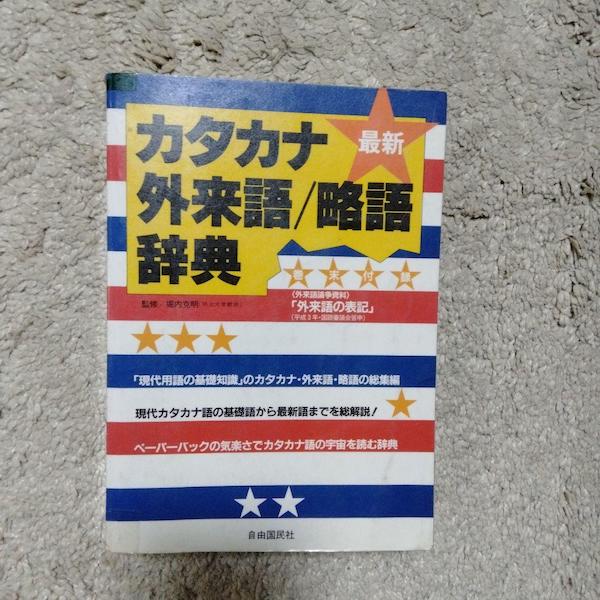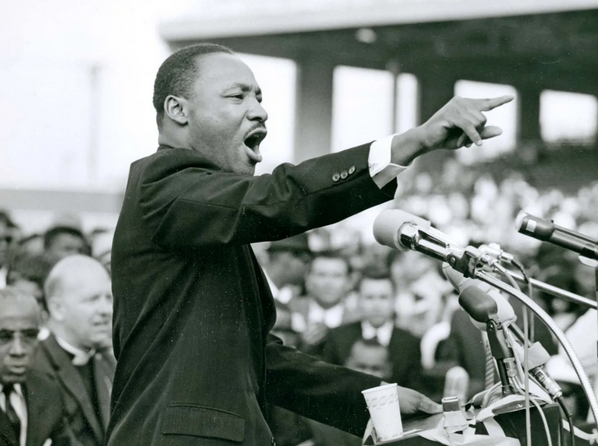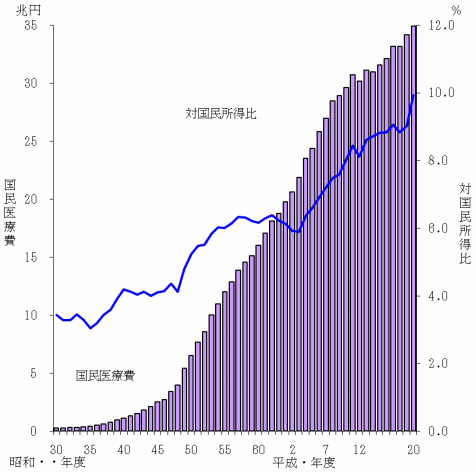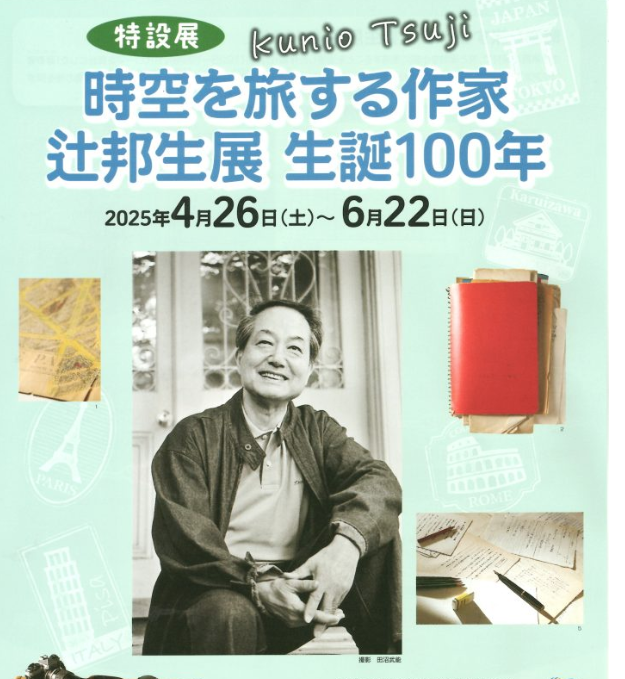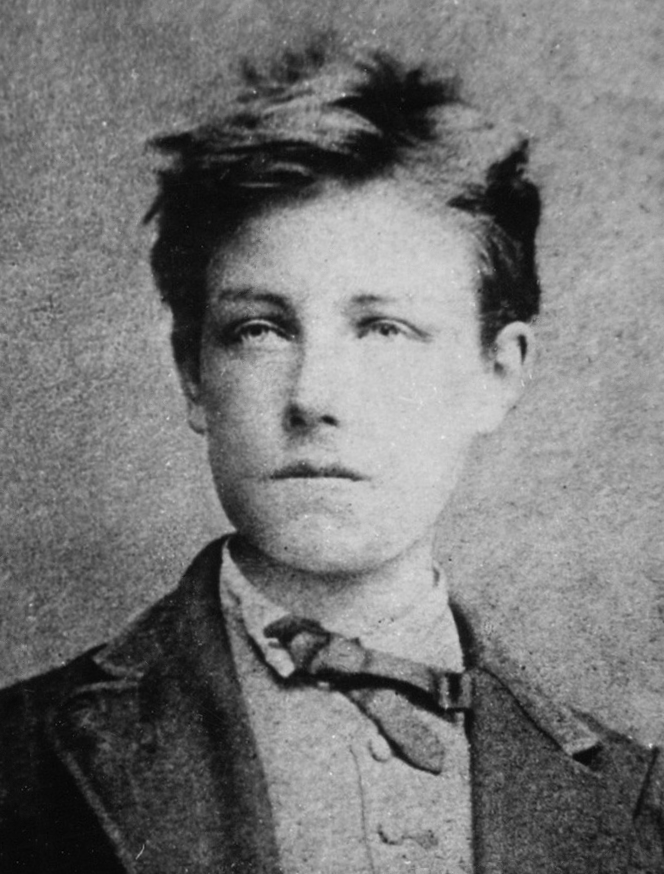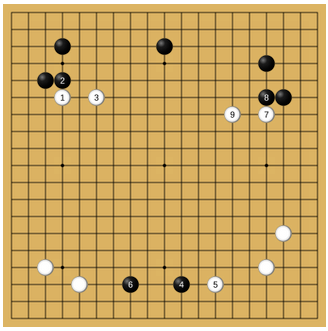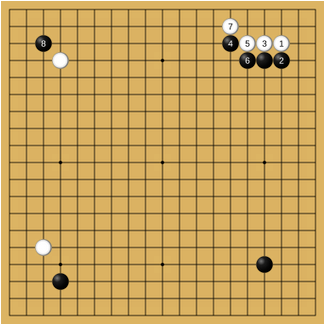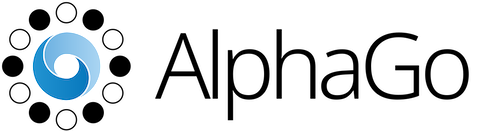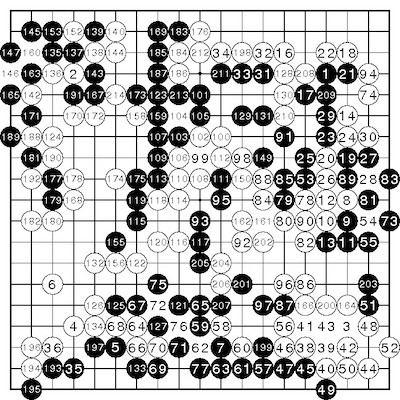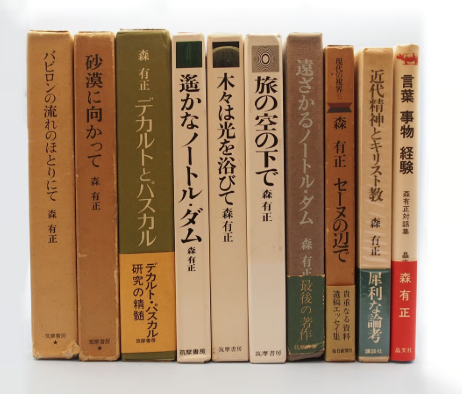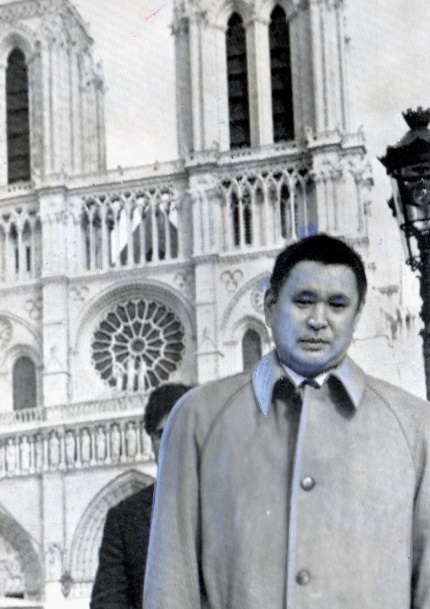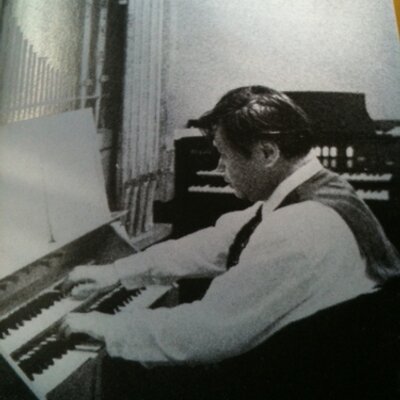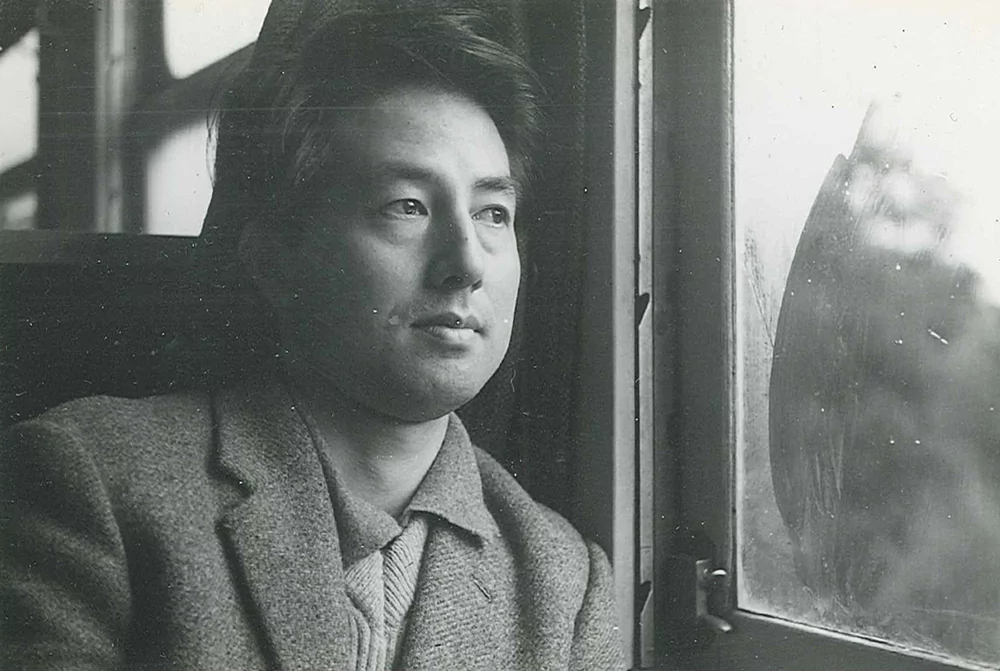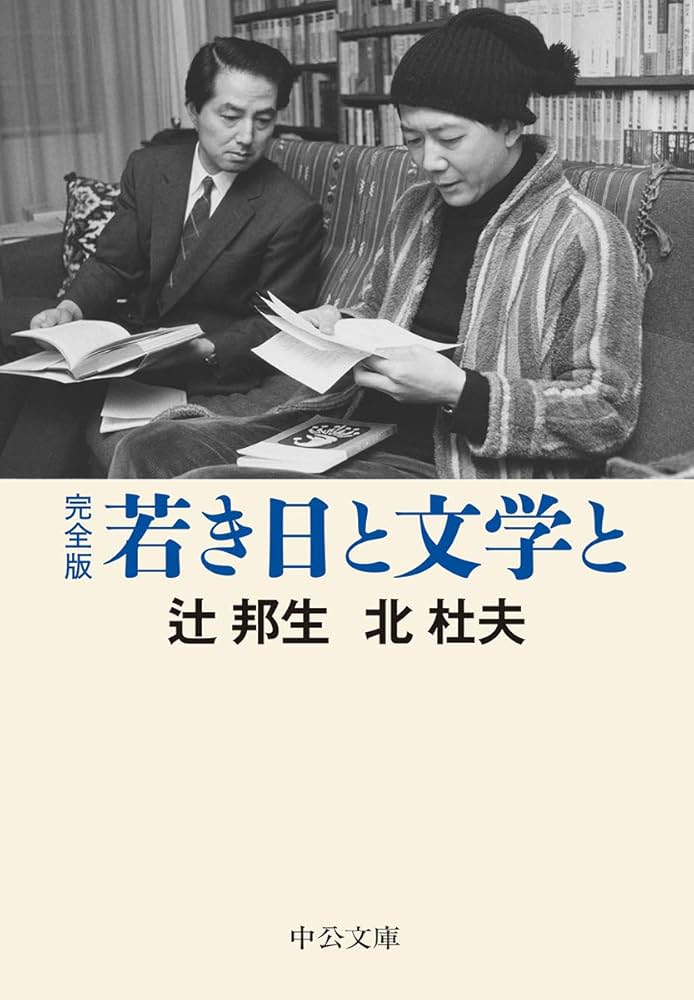「事実に基づく報道」というフレーズをしばしば耳にします。公共放送の綱領はそのように謳っています。しかし、このような常識については立ち止まって考える必要があります。本稿はメディア界の常識を考えることにします。
メディアの常識にはいろいろあります。まず「ニュースは事実を中立・客観的に伝えている」とか「意見が対立する問題では多角的に論点を提示する」といわれます。これは多くの人が無意識に信じている前提ですが、かなり怪しいのです。何故かといえば、報道には必ず次のような工程が入ります。何をニュースにするかという選択、誰が記事を書くのか、次にどの順番で伝えるかという順位、そしてどんな言葉や表現を使うか、最後に誰のコメントを載せるかという手続きです。このような過程では、すでに編集という価値判断が入っています。

メディアの常識の第二は、「専門家のコメントは信頼できる」という神話です。いろいろな報道や討論系番組が調査や特集型の報道番組があります。よくある構図ですが、そこには特定の立場に近いメディア向けに「使いやすい」人が繰り返し招かれています。政策に近い専門家が呼ばれ、政策を批判する専門家が登場しないのです。テレビ局は「バランスはとった」と主張するようですが、いつも「お抱え」、「お気に入り」のような人間が登場します。このような「常連」からは、論点の深さや前提は検証されないと感じるのです。
メディアの常識の第三は、「数字やデータは嘘をつかない」というフレーズです。これも強力な常識です。例えば、「2024~2025年時点の政府債務残高対GDP比は250%超で、主要先進国の中で群を抜いて世界最高水準にある」という説明です。しかし、政府の持つ資産を差し引いた「純債務」で見ると、OECD基準では日本はイタリア等より低いのです。つまり、どの数字を使うか、比較対象を何にするかによって見方は異なるのです。
日本の国会議員は多すぎる、公務員数が多すぎる、公務員の給与は高すぎる、公共投資が多すぎる、といった常識は、国際比較をすれば間違いであることは明らかなのです。「失業率は改善している」という報道があったとします。この場合、非正規や短時間労働を含めると実態は不確実ではないかという疑問が浮かびます。「支持率◯%」と報道されても調査方法や標本の選び方、その母数、質問文の内容が分からないと失業率の報道は信頼できません。
メディアの常識の第四は、「報道機関は権力を監視する存在である」といわれることです。確かに理念としては正しいようですが、現実はかなり複雑です。報道機関は、政党や政府の監視を受けています。例えば、過激な報道をすると「放送権を取り上げる」と脅されることもあります。結果として本質的に危険な話題は避け、対立を「分かりやすい対立構図」に単純化する傾向が生まれます。
メディアの常識の第五は、記者クラブ制度による報道内容の均一性ということです。記者クラブは日本の官公庁や企業に大手メディアが常駐し、情報提供や記者会見を独占する特権的構造が、閉鎖的で権力との癒着を招いている問題です。フリーランスや新興メディアを排除し、発表中心の「発表報道」による監視機能低下が問題視されています。取材機会の不平等も長年批判されています。さらに報道機関は、視聴率やクリック数企業や広告主との良好な関係を保たないと番組のスポンサーから降りられます。こうした利益誘導によって迎合的な姿勢をとってしまいます。
「常識を疑う」とは、メディアを敵視することではなく、距離をとることです。なぜ今これを報じているのか?、誰かの視点が欠けていないか?、逆の立場から見るとどうなる?、というように立ち止まって自問自答することです。いわゆるクリティカル・シンキング(critical thinking) が大切です。