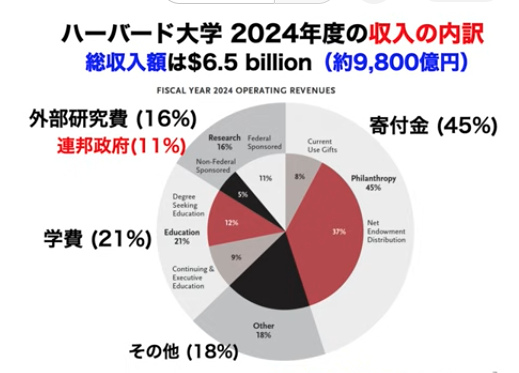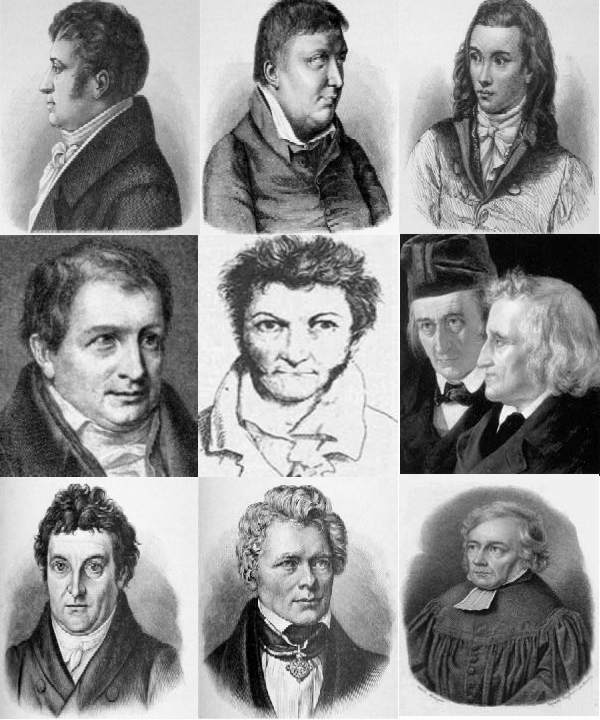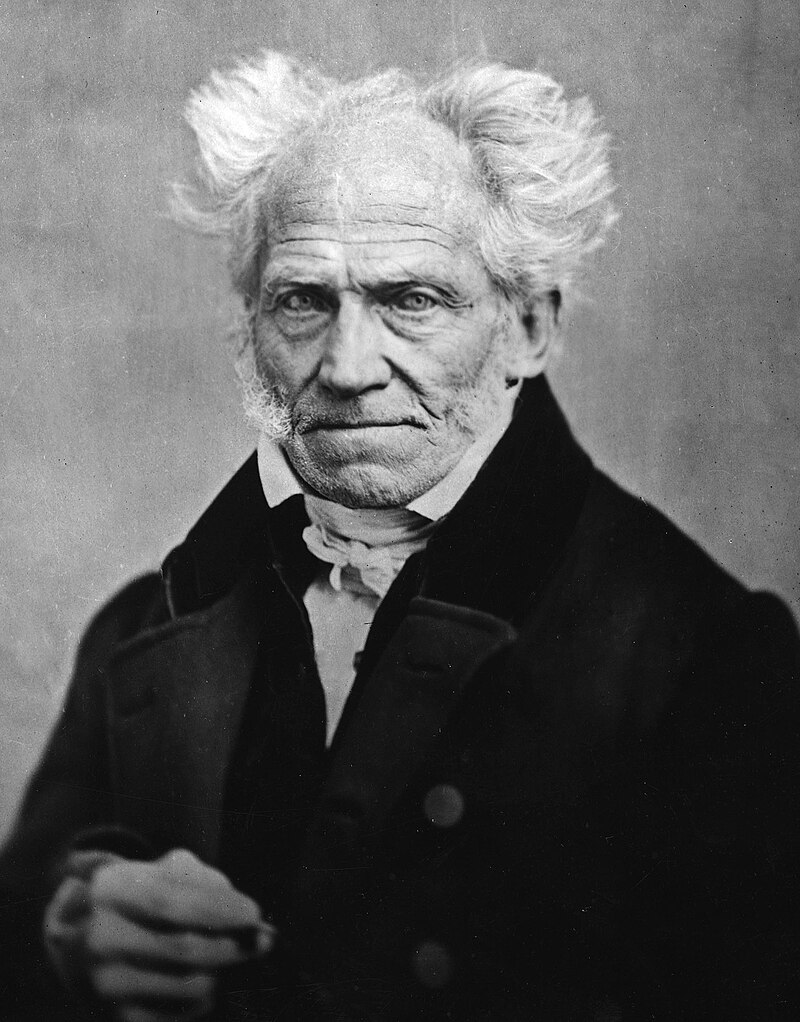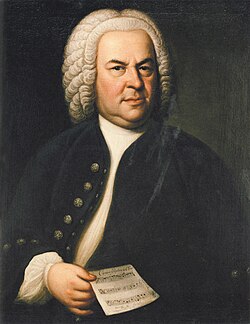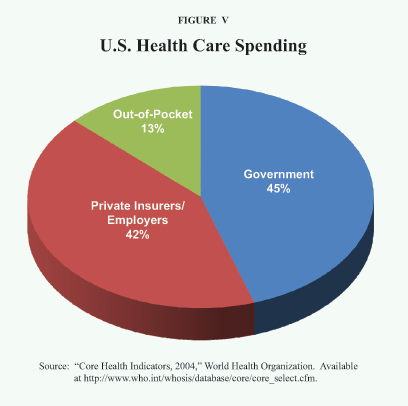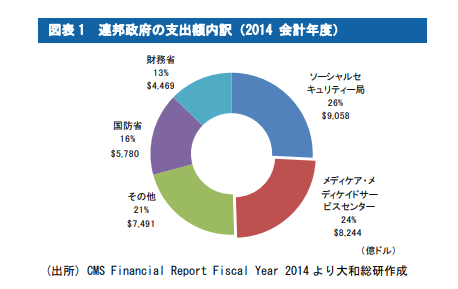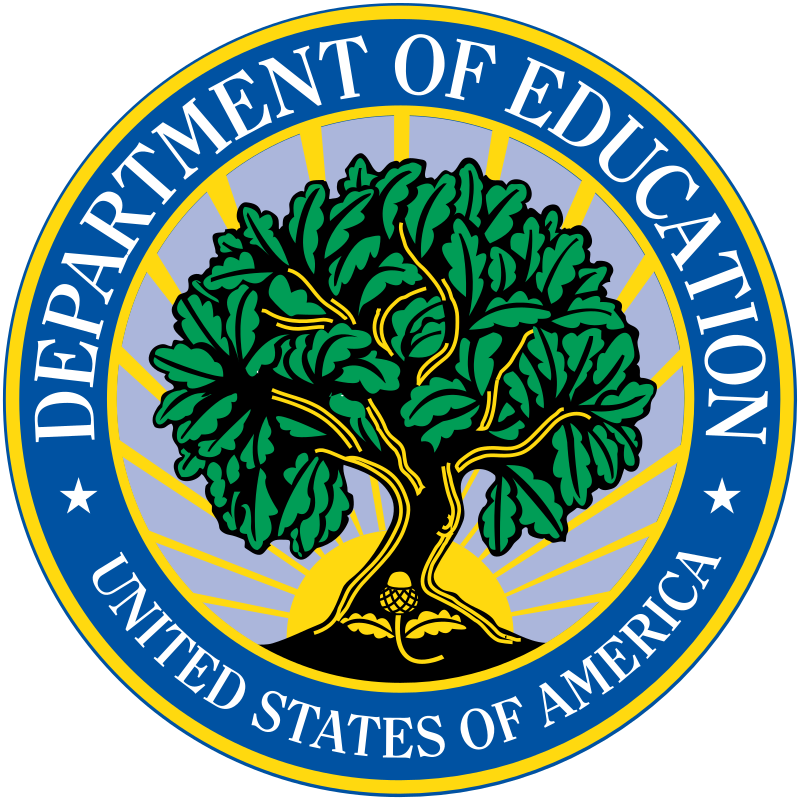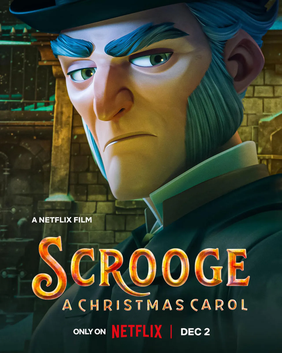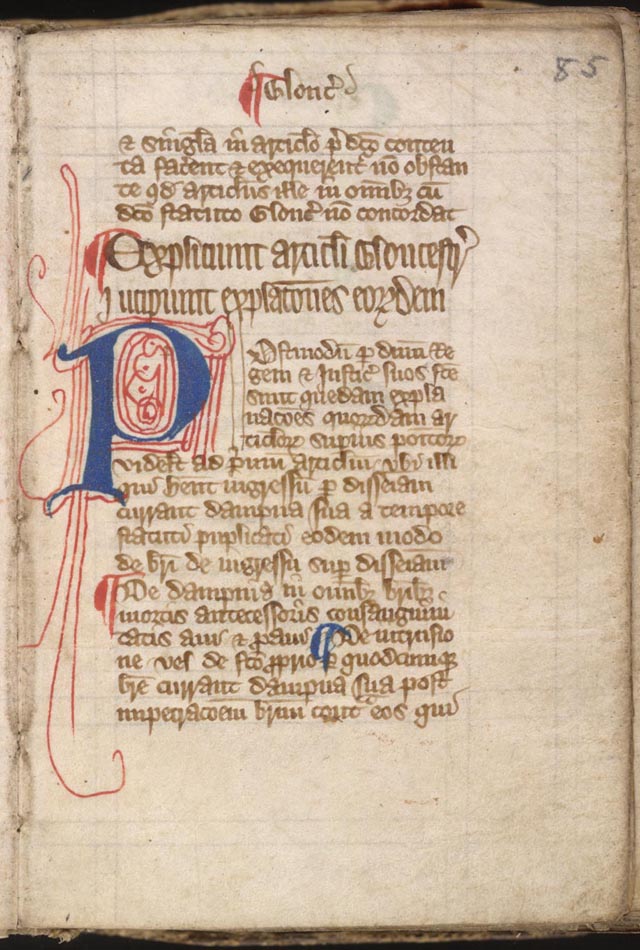アメリカの最も大事な記念日であり祝日の一つが「Memorial Day」です。戦没将兵追悼記念日といわれています。今年のMemorial Dayは、5月の最終月曜日の26日でした。アメリカのために命を捧げた軍人・軍属を追悼する日です。20世紀では戦没将兵は、第二次大戦、朝鮮戦争、ヴェトナム戦争、アフガン戦争で命を落としました。この日はアメリカ全土で国旗が半旗に掲げられ、軍人墓地や公園では追悼式典やセレモニーが行われました。各地ではパレードが開催され、退役軍人(veterans)やその家族が中心となって、国のために尽くした人々への感謝と敬意を表します。最も盛大なパレードはニューヨーク市のブルックリン(Brooklyn)で、毎年開催されます。1867年以来続き、これをアメリカ最古のパレードといわれています。
2000年に連邦議会は国民追悼の法(National Moment of Remembrance Act)を可決し、午後3時に立ち止まって追悼するよう人々に呼びかけました。Memorial Dayの日には、国旗が掲揚され、正午まで厳粛に半旗に下げられます。その後、その日の残りの時間は全譜面に掲げられます。国立メモリアルデー・コンサートNational Memorial Day Concert は、合衆国議会議事堂(Capitol)の西芝生で開催されます。これは必見ものです。是非クリックして楽しんでください。
街の通り沿いにや家には星条旗が掲げられ、商業施設の広告にも「Memorial Day Sale」の文字が見えます。報道では、退役軍人のインタビューや追悼関連の特集が組まれます。「Remember and Honor(戦没将兵を忘れず敬意を表しよう)」というメッセージが多く見られます。このようにアメリカでは、戦没者の追悼が社会的に“見える形”で行われます。日本とは違い、軍服を着た人が日常に溶け込んでいます。さらに退役軍人が地域のヒーローのように扱われます。学校でも子どもたちは、国旗の意味や国家への忠誠心を学んでいます。小学生から国歌を教えられます。
我が国には「終戦記念日」があります。静かに追悼を行う日という印象が強いです。全国的に大きく盛り上がることはありません。その理由は敗戦という歴史のためと思われ、Memorial Dayとは違った響きや内容がとなっています。沖縄には「慰霊の日」があります。沖縄戦での日本軍の組織的な戦闘が終わったとされるためです。「慰霊の日」と「Memorial Day」の違いは、国家に尽くした個人への敬意を表す日ではなく、主に沖縄の庶民や軍属の戦没者に特化した祈りの日であることです。
Memorial Dayは他方で、アメリカでは夏の始まりを告げる祝日でもあります。家族親戚が集まってバーベキューを楽しむ「家族で過ごす週末」としての意味合いも強いです。この「国のために戦った人への敬意」と「家族や日常の自由を大切にすること」が同居しています。「祈り」と「自由を楽しむ」ことが矛盾ではなく、「自由には代償がある」という歴史的な意識が根付いているのかもしれません。
アメリカの社会学者のロバート・ベラ(Robert Bellah)は、合衆国には、いかなる宗教宗派や見解にも属さない世俗的な「市民宗教」(civil religion) があり、それがMemorial Dayを特別な行事として取り入れていると解釈します。その源は南北戦争で、それを契機に、死や犠牲、そして再生という新たなテーマが市民宗教に加わったというのです。Memorial Dayはこれらのテーマを儀式的に表現し、人の生と死の動機が国家目標の達成と一致するようにしたのがMemorial Dayのようです。