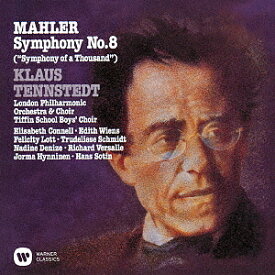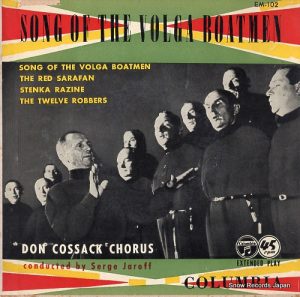メンデルスゾーン(Felix Mendelssohn) は、ドイツ・ロマン派の作曲家、指揮者、ピアニスト、オルガニストです。1809年生まれです。父Abraham Mendelssohnは銀行家、有名な哲学者Moses Mendelssohnの次男です。母Leaはプロイセン(Prussia)宮廷の宝石細工の娘でした。3歳のときベルリンに移住し、両親の慎重な教育計画にそって育てられます。9歳のときにすでにピアノ奏者として公衆の前で演奏し、神童の一人とも云われていたようです。
メンデルスゾーンの家には、詩人、音楽家、哲学者、科学者が集まり、私的な音楽会を開いたり、芸術論をたたかわせるサロンのような状況であったようです。こうした環境でメンデルスゾーンは音楽や文芸的な素養が育まれたと考えられます。1816年に家族全員が改宗しルーテル教会信徒となります。ユダヤ系ドイツ人としての葛藤があったようです。1819年に1821年にはワイマール(Weimar)でゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)にも会います。1829年にイギリスを訪問し、イギリスの聴衆がメンデルスゾーンの音楽に対して共感を示します。旅先で「フィンガルの洞窟」を作曲します。
1830年からヨーロッパ中を駆け巡る旅が始まります。ミュンヘン、ウィーン、ナポリ、ローマ、パリ、ロンドンなどの都市で演奏します。その頃、ベルリオーズ(Louis Berlioz)やリスト、ショパンなどと知遇をえます。交響曲「スコットランド」、「イタリア」などの着想を得たといわれます。後に「宗教改革(Reformation)」と呼ばれる交響曲第5番を作曲します。数多い詩篇やカンタータではバッハの手法を学んでいます。オラトリオ「聖パウロ(St. Paul)」、「エリア(Elijah)」ではヘンデルから影響を受けたようです。聖歌のモチーフを使用し、宗教への関心の深さを示しています。交響曲第2番「賛歌」の終楽章では声楽を用い、ベートーヴェンの合唱付きの影響を受けたことがわかります。