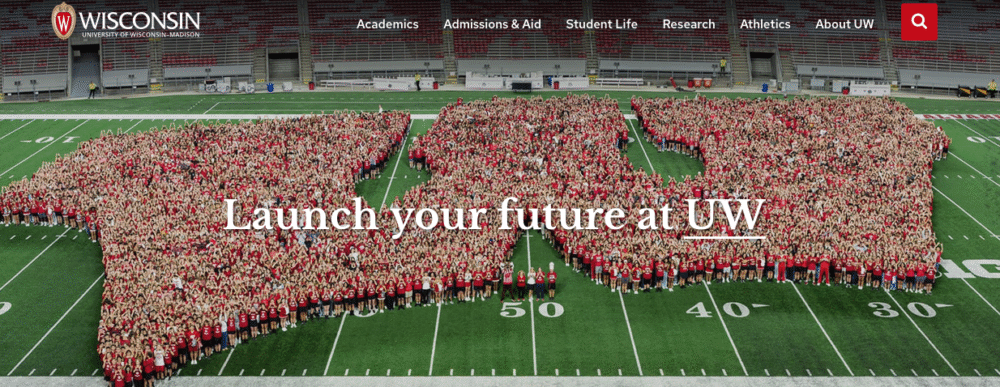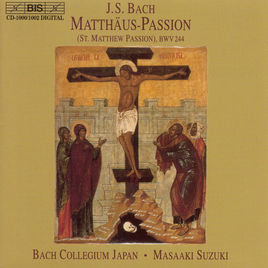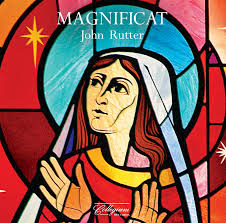「タンホイザー」(Tannhäuser WWV.70)ワーグナー(Richard Wagner)が作曲した全3幕のオペラです。正式な名称は『タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦』(Tannhäuser und der Sangerkrieg auf Wartburg)といいます。このオペラで良く知られているのは序曲(Overture)、第2幕のエリザベート(Elizabeth)のアリア(Aria)、「大行進曲」などで個別でもよく演奏されています
ところで、ワーグナー作品目録は、Wagner-Werke-Verzeichnis(WWV) といわれています。作品目録は1番から113番までの番号が付されています。バッハの作品の目録である「BWV」と同じです。
「巡礼の合唱」(Pilgrim’s Chorus)ですが、中世のドイツでは、騎士たちの中で吟遊詩人(Minstrel)となって歌う習慣があったといわれます。騎士の1人であるタンホイザーは、テューリンゲン(Thüringen)の領主の親族にあたるエリザベート(Elizabeth)と清き愛で結ばれていたのですが、ふとしたことから官能の愛を求めるようになります。
我に返ったタンホイザーは自分の行為を悔やみますが、領主はタンホイザーを追放します。そして領主はタンホイザーにローマに巡礼に行き教皇の赦しが得られれば戻ってきてよいと云います。彼は巡礼に加わりヴァルトブルク(Waltburg)城を去ります。
ヴァルトブルク城近くの谷。タンホイザーが旅立ってから月日がたちます。エリザベートは、タンホイザーが赦しを得て戻ってくるようにと毎日祈り続けます。やがてローマから巡礼の一行が戻ってきます。エリザベートはその中にタンホイザーを探すのですが、彼はいません。このとき歌われるのが「巡礼の合唱」です。