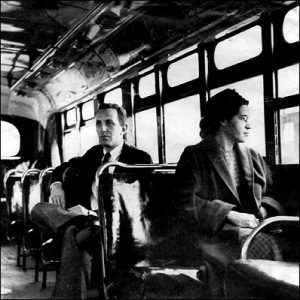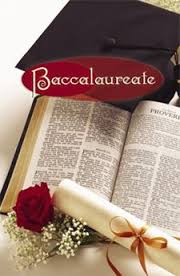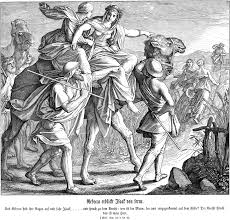アメリカでは高校は義務教育です。学校はどのようにして支えられているかをご存じでしょうか。アメリカの学校の大半は市町村立か私立です。市民の税金が学校を支えています。州立高校というのはありません。
アメリカでは高校は義務教育です。学校はどのようにして支えられているかをご存じでしょうか。アメリカの学校の大半は市町村立か私立です。市民の税金が学校を支えています。州立高校というのはありません。
小さな町や村は、郡単位となって学校を運営します。人々の税金によって学校の建物を維持し教師を雇っています。もし、中途退学者が増えようものなら、市民は「学校は一体なにをやっているのか、教育長 (superintendent)や校長を代えよ、」と叫ぶのです。こうした記事は地方の新聞でよく見られます。市民には税金の使いみちと教育の成果は最も関心の高い話題の一つです。教育委員は公選です。教育委員会を統括するのですから、教育長や校長は教育委員会の下で教育行政に従事しなければなりません。教育長は教育委員が選ぶ仕組みとなっています。振り返って、日本では教育委員長(board of directors) や教育委員はなんの権限もなく、教育長の下に位置するという体たらくです。
学校税(school tax)というのがあって、自分たちの税がどのように使われているかがガラス張りとなっています。校長は、「スクールカウンセラーを雇いたい、PCを買い換えたい」などの提案を市民集会(Town Meeting)で説明します。ビジョンを持つ校長は市民にたいして、もう少し学校税を負担して欲しい、必ず教育の質を高める、と訴えるのです。
それでも資金が不足すると、校長は学校債権(school bond)の発行を提案して市民に学校への支援をとりつけます。債権ですから満期になると元金と利息を市民に返します。教育委員会から予算を獲得できるかが、校長の能力なのです。さらにロータリークラブ(Rotary Club)やキワニスクラブ(Kiwanis Club)といった地域の経営者団体や福祉団体から寄付を集めるのも校長の仕事なのです。校長は地元の営業マン、ウーマンです。校長の権限と責任は大きいこと、市民の期待が高いのがアメリカの学校なのです。
[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]