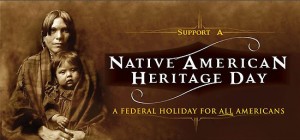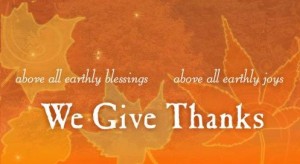アドベントリース(Advent wreath)には樅の木の枝が使われる。しなやかなので丸いリースを作りやすい。樅の木は、「Christmas Tree」とも呼ばれる。クリスマスのデコレーションに使う木である。有名なのは、ニューヨーク市のロックフェラーセンター(Rockefeller Center)前に立てられものだ。毎年その点火がニュースとなる。今年は本日12月3日に点火式が開かれるという。このセンター前の広場ではさまざまな催し物が演じれる。
樅の木に戻る。この常緑樹は強い生命力の象徴とされる。また「知恵の樹」とも呼ばれる。沢山の種類の飾り物がとりつけられる。子供たちの楽しみでもある。もともとはリンゴとかナッツなどの食べ物が枝にくくられたそうだ。そしてろうそくとなり今は豆電球で飾られる。ベツレヘムの星(Bethlehem)やガブリエルの天使(Gabriel)の飾りも目立つ。
樅の木がクリスマスの木として使われるようになったのは15世紀頃といわれる。ドイツ、Selestatにある St. George’s Churchがその起源とか。ブリタニカ百科事典(Encyclopedia Britannica)によると, 樅の木は常緑樹(evergreen trees)として、エジプト人や中国人、ヘブル人などが永遠の命を象徴する木として崇めていた。こうした信仰はヨーロッパの非キリスト教徒(pagan)らにも広まり、やがてスカンジナビアや西ヨーロッパに広まり、家々や納屋に立てられた樅の木は魔除けとしても、また鳥の止まり木としても飾られるようになったという。
樅の木の代わりに”Paradise Tree”という常緑樹もクリスマスでは飾られたといわれる。中世のミステリ劇に登場する。それによると12月24日はアダムとイブ(Adam & Eva)と命名された日として祝われる。そこに飾られる木には禁断の実とされたリンゴが供えられた。さらに、種なしの薄焼きパンーワッフル(wafer)も付けられた。ワッフルには聖餐(Eucharist)とか贖罪、救済(Redemption)の意味があった。