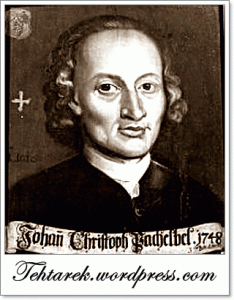チャールズ・スタンフォード(Charles Stanford)は、1852年生まれのアイルランドの作曲家です。幼いときから作曲し、その才能はすでに開花していたといわれます。
ケンブリッジ(Cambridge)のトリニティ・カレッジ(Trinity College)で学びます。1873から92年まで同カレッジのオルガン奏者や大学音楽協会の指揮者となります。1882年、29歳で王立音楽大学創設メンバーの一員として教授に就任します。その後生涯にわたって同大学の作曲科で教鞭をとります。1887年からはケンブリッジ大学(University of Cambridge)の音楽科教授も兼任します。
グスタフ・ホルスト(Gustav Holst)やリーフ・ヴォーンウイリアムズ(Ralph Vaughan Williams)らのすぐれた弟子を育てます。イギリス音楽の再興を果たし、ナイトの称号を与えられます。「イーブニング・サーヴィス」 、「闇を照らせ」、「今こそ主よ、僕を去らせたまわん」という曲をお楽しみください。
作品はドイツロマン派の様式を備えています。職人的ともいえる作曲技法で、アイルランドやイングランドの民族的な色彩を反映する曲を作ります。作品は交響曲、協奏曲、宗教曲、歌曲などにまたがります。