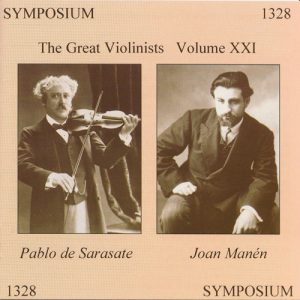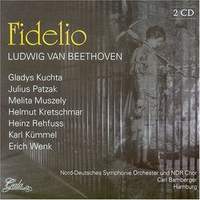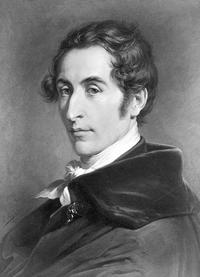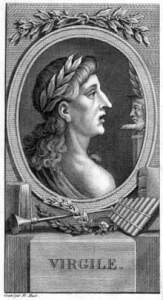少し時代を遡って、中世のヨーロッパに転じます。15世紀から16世紀の時代です。後期フランドル楽派(Flemish School)最大の作曲家といわれるのがラッソ(Orlando di Lasso)です。ラッスス(Orlandus Lassus)とも表記されます。後述するパレストリーナ(Giovanni Palestrina)と共に、後期ルネッサンスを代表する巨匠といわれます。
後期ルネサンスでは最も多作な世界的作曲家であったのがラッソといわれます。全部でゆうに1,200あまりの作品を書き、ラテン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語の声楽曲があらゆるジャンルにわたって作曲しています。その内訳は、4曲の受難曲(Passion)、540曲のモテット(Motet)、100曲の聖務日課のための曲、200曲のマドリガル(Madrigal)とヴィッラネッラ(Villanella)、150曲のシャンソン(Chanson)、90曲のリート(Lead)です。ラッソ作の器楽曲が存在するかは厳密には分かっておりません。
マドリガルとはイタリアの世俗声楽曲で 5 声部無伴奏の合唱のことです。ヴィッラネッラも同じくイタリアの田舎風の声楽曲で3声部から成ります。ラッソの代表作の一つに「シビュラの予言」(Prophetiae Sibyllarum)があります。半音階的手法などの大胆な和声的工夫によって、劇的な表現力が見事に発揮されています。