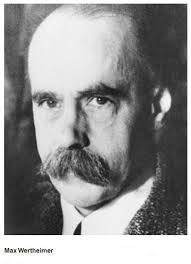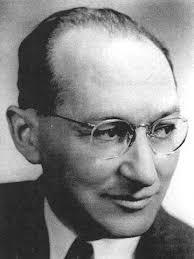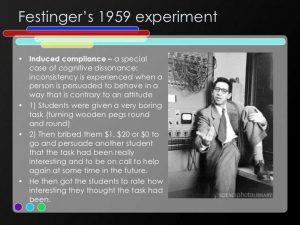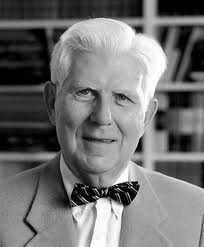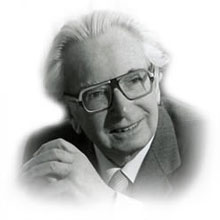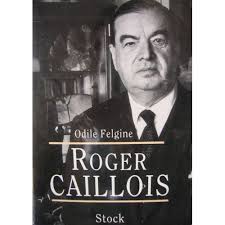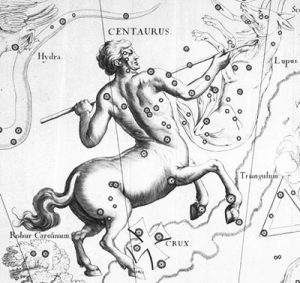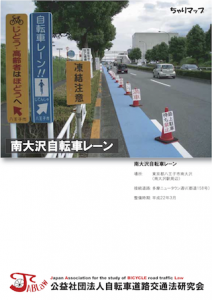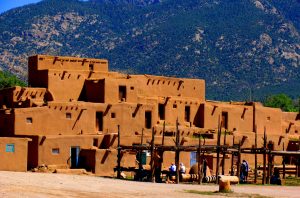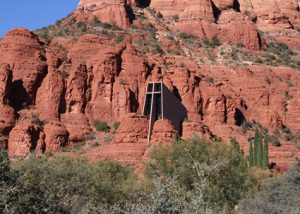認知心理学に関して、一人の心理学者を紹介します。1918年にウィスコンシン大学から学位を授与され、学内でしばらく教鞭を執ったクラーク・ハル(Clark Hull)です。ハルは人間の心や情感などの仕組みをモデル化して、そこから行動を説明するという発想をします。



それはどういうことかといいますと、行動ではないとされてきた心的な現象をデータ化して分析するという方法を考えたのです。心理学における一つの体系的な方法として、目に見える行動ではない人間の内側で起きている心とか感情の働きを分析できると唱えます。これは「方法論的行動主義」と呼ばれ、後の心理学に大きな影響を与える革命的なことといわれます。
行動主義心理学の創始者がジョン・ワトソン(John Watson)とすれば、行動分析学の創始者はバラス・スキナー(Burrhus Skinner)といわれます。この二人に共通することは、一口でいえば「心理学が科学的であるために客観的に観察可能な行動を対象とすべきだ」というテーゼでしょう。これは急進的行動主義(radical behaviourism)と呼ばれます。心理学の目的は、行動の法則を定式化し行動を予測しそれを制御することであるという主張なのです。あまりにも言葉足らずですがそういうことです。
しかし、ハルは「行動の原理」(Principles of Behavior) という著作の中でS-R理論を改良したS-O-R理論(Stimulus-Organism-Response Theory)を提示します。この理論における有機体(Organism)が刺激・反応に影響を与える媒介変数によって、どうして学習効果の個人差や同一刺激に対する反応の個体差が生まれるのか、という疑問に答えることができると提案します。