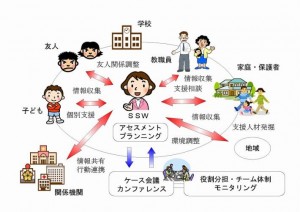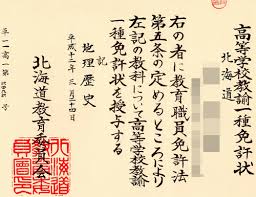筆者は、「歴史研究では、対象とすることは反復が不可能である」という前提に興味を抱いている。反復可能な一般的法則を追求する自然科学とは対極をなしている。しかし、新しい研究では歴史はより複雑で宇宙や生命にいたるものであることが提唱されている。これではなおさら歴史とは、を考えなければならなくなる。
1962年にエドワード・カー(Edward H. Carr)が書いた「歴史とは何か(What is History?)」が注目された。歴史の記述の中には著者による歴史観や経験にもとづいた「主観性」が入り込んでおり、むしろ時代背景などを理解することの重要性を指摘している。また、歴史小説家の陳舜臣は、「歴史は勝者によって書かれることが多く、勝者に有利な記述が行われる傾向にある。敗者の歴史記述や秘匿された文書の方が比較的信頼に足る」と言及している。なかなか興味深い指摘である。
最近、韓国は大邱市から友人が八王子にやってきた。彼は長年大邱教育大学校で歴史を研究して定年退職された。埼玉県日高市にある高麗神社や聖天院などにお連れした。聖天院は高句麗から渡来した高麗王若光の菩提寺である。在日韓民族無縁仏の慰霊塔がある。慰霊塔が建つ広場の周囲には、広開土王、太宗武烈王、王仁博士、申師任堂などの石像が配してある。いずれも韓国人の自尊心を高揚した偉人たちである。
それについてだが、ソウル市内にパゴダ公園を思い起こす。3.1.独立運動の発祥地である。そこに八角亭が建っている。聖天院の慰霊塔のそばには、韓国の建材を使用し同胞によって施工された八角亭が建てられている。友人は、日本の、それも埼玉の田舎にこのような建造物と施設があることにたいそう驚くとともに、日本人の懐の深さを感じると述懐していた。
韓民族無縁仏の慰霊塔の側には王仁博士の石像がたっている。百済から日本に渡来し、千字文と論語を伝えたとされるのが王仁である。王仁の姓である「王」は、姓からみて高句麗に滅ぼされた楽浪郡の漢人の王氏系の学者ではないか、韓国では民族史観によって「王仁は日本に進んだ文化を伝えた」といわれていると友人が説明してくれた。漢字と論語を伝えた王仁のことは、もっとわが国で知られてもよいのではないか。
この友人はアメリカ史を研究する歴史学者である。高麗神社や聖天院を案内しているときに、「Big History」–巨大歴史という概念を語ってくれた。そのことを紹介するのがこれからのブログである。
 聖天院
聖天院
 高麗神社
高麗神社