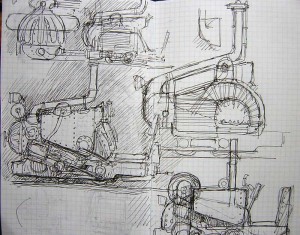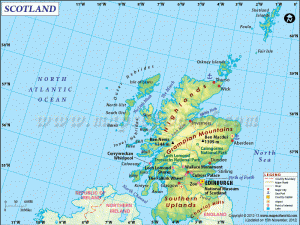シリーズもこれから佳境に入る。その前にちょっと珈琲タイムとしたい。
スコットランドへはまだ行ったことがない。だが、こうしてブログの話題にするのは、筆者が北海道育ちだからだと思っている。それは、この二つの地にはどこか共通点があることを「スコットランド文化事典」から学んでいるからである。この本は写真や図版が多く、読んで楽しめる。
人はその土地に住まなくとも、少なくとも想像力をかき立てられるものだ。不思議なことに、知らぬ土地のことについての活字や写真や音楽に触れることによって、それまで自分が育ってきた風土と重ね合わすことができる。そして未知の土地に対する想いと憧れがわいてくる。
小さいときから音楽という文化に触れたことも幸いしている。スコットランド民謡もそうである。アニー・ローリー、マイボニー、アフトンの流れ、ロッホ・ローモンドなど。どれも郷愁に満ちた旋律である。口ずさむとどこでいつ歌ったのかを想い出すことができるから不思議だ。
スコットランドの隣にあるアイルランドからも学ぶものがあった。それは自分の父親とつながっている。国鉄を退職後は、読書の虫であった。青年時代に読むことがなかった作品をもっぱら読んでいた。その中にジェイムス・ジョイス(James Joyce) の「ユリシーズ(Ulysses) 」がある。「何度読んでもわからない、、」と呟いていた。トルストイ(Lev Nikolayevich Tolstoy)の「戦争と平和(War and Peace)」もそう言っていた。小生は、スウィフト(Jonathan Swift)の「ガリヴァー旅行記(Gulliver’s Travels)」といった作品しか知らない。小人に取り巻かれたガリヴァーの冒険物語である。
ジョイスはアイリッシュであった。アイルランドの歴史はイングランドとの宗教や政治の複雑な経緯でもある。1100年代からのイングランドによる植民地化である。経済や貿易の中心がロンドンへと移りアイルランド経済は疲弊していく。ジャガイモ飢饉も起こる。そして北米大陸への移民によって人口が減少する。カトリック教徒が占めるアイルランド民族主義者とプロテスタント教徒が占める連合主義者との対立がたびたび激化する。この北アイルランド紛争は1998年まで続く。
小さい頃学んだ地理や人物、簡単な歴史の追体験が、やがてなんらかのことで蘇ってくるようなできごとに出会う。スコットランドやアイルランドは、司馬遼太郎の「街道をゆく」を読んで「かんかーん」と響いてきた。何故か身近な国のような気がした。