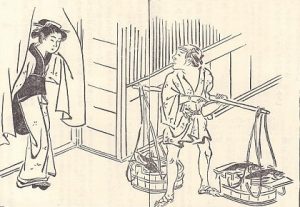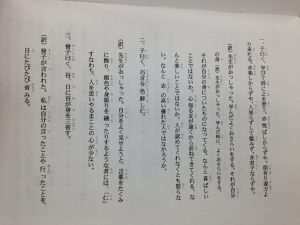山本周五郎の「小説日本婦道記」に収録されている「おもかげ抄」です。
浜松の裏街道にある家作へ引っ越してきたのが鎌田孫次郎です。年の頃は二十八、九。上背があり立派な体つきで色の浅黒い、眼の涼しいこのあたりでは珍しい美男です。家作とは借家のことです。
魚売りの金八が長屋の周りの者に云います。
「まあ、聞きね、」「表へでて洗濯をしているじゃねえか」、「奥様のお加減でもお悪うございますか」と訊いたんだ。「するとその返辞がふるってら、」
「いや別にとこも悪いと申すほどでもござらぬが、ちと我がまま、まあ朝寝がしたいのでござろうよ、とかくどうも女は養い難しでござる、、あはは、、」
長屋の女房達の間に孫次郎につけられた甘次郎、甘田甘次郎先生などの綽名がたちまち付近にひろまります。
二十日あまりが経ち隠居の六兵衛が孫次郎の浪宅を訪れます。
「ようこそおいで下された」と奥へ振り返って、「これ椙江、お客来じゃ、お茶をいれ申せ」とい云います。舌打ちをしながら「しようのないやつ、また頭でも病むと申すのであろう、我がままがつのって困る」
孫次郎がご用向きをきくと、空屋を寺子屋として子どもに素読の指南し、剣術も教えて欲しいというのです。孫次郎は二つ返事で引き受けます。初秋の昼下がり空き地で子ども達に剣の心得を教えていると、子どもが叫びます。
「向こうの原っぱでお侍が斬り合いをやっていますよ」
孫次郎も剣を持ってかけつけると、一対四の真剣勝負です。訊くと御意討となった侍の犬飼研作を四人が仕留めようというのです。犬飼の剣は鋭く四人の侍は歯が立ちません。孫次郎は助太刀し犬飼を倒します。そこに一人の老武士が馬で駆ってきます。「あっぱれ、お見事」と思わず声をあげます。子ども達も空き地の隅で固まってみていました。孫次郎が戻ると「お師匠さまは強いな、、」と歓声をあげます。
二、三日経たある日、さきの老武士が前触れもなく孫次郎を訪れます。
「椙江、お客様じゃ、、」
「ご覧の如き浪宅、何のお構いもなりませぬ、どうぞお許しを」
老武士の名は沖田源左衛門という家臣の大番頭をしているという。
「お手前のほど、先日篤と拝見仕った、ご流儀は梶派でござるな」
「実は拙者も壮年の頃、梶派一刀流をわずか学びなしたので、太刀懐かしく拝見いたしました」
倅の千之助に梶派を教えて欲しいというのです。
「未熟の拙者、とても人に教え申すことなど出来ませぬが、折角の思し召しを辞するは却って失礼、宜しかったら型だけでも」
「ところでご家内はご病気でござるか?」
「はあっ、、、」
孫次郎はなぜかうつむきやがて席を立つと「ご覧ください」といって合いの襖を開けるのです。
甘次郎という綽名をきいていた源左衛門は、甘次郎と呼ばせる妻はどんな美人かとみると、次の間には小さな経机がひとつ、仏壇のまえに据えられていて、ゆらゆらと線香の煙が立ち上っています。
「これは、、、、、」
「実は三年前に死去致しまして、、」
「すると先刻、奥へ声をかけられたのは?」
「お耳にとまって赤面仕る」
「仕合わせ薄き女にて、三年浪々の貧中死なせましたが、未練とお笑いくださるな」
「手前にはどうしても死んだと思い切ることができず、、」
「面影あるうちは生きているつもりにて、あのような独り言を申し始めたのが癖となり、今日までそのまま、、、」
「いや佳きお話を承った、亡き人へのそれほどの御愛、未練どころか却ってお羨ましゅう存ずる、拙者もご回向仕ろう」
綜合的な教育支援の広場