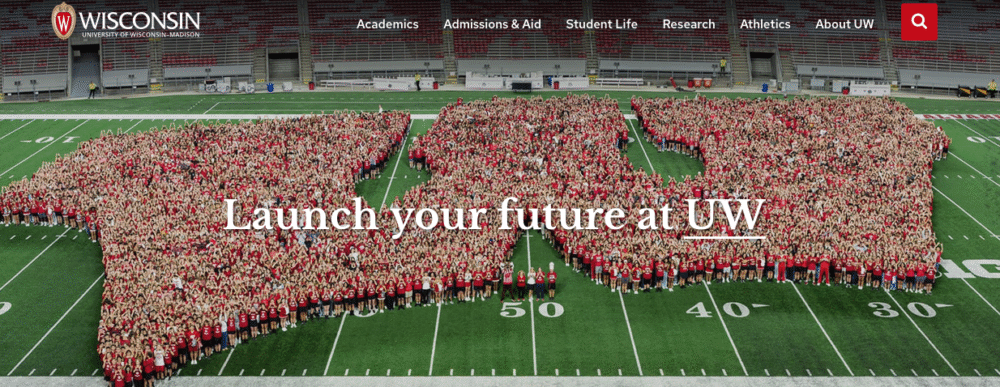いくら世界中の人々がクリスマスを祝うといえど、聖霊によるマリアへの受胎告知やイエスの誕生に納得できない人々がいるはずである。その後のキリストの受難と昇天、そして復活もそうであろう。キリスト教徒でない人々の中には聖書の中味を、「作り話」、「ファンタジ」、「空想」として捉えるから、受胎告知や復活といった奇跡にさしたる抵抗は感じない。だからクリスマスも、わだかまりもなく子供や家族と楽しむことができる。今回はその先のことを考えたいのである。
復活とか蘇りという出来事は、考えてみれば宗教の世界で通用する現象である。キリスト教徒は、そうした「出来事」にかつては困惑したり懐疑したことはあったにせよ、それを「吹っ切って」洗礼を受け信徒になったのである。こうした転機は奇跡といえることかもしれない。
「人知では到底計り知れない」ことは世の中にはいくらでもある。高い教育を受け、自然科学に触れ、進化論を知ったにせよ、こうした宗教上の現象は、この世界とは次元の越えた現象として受け容れるのである。そこには吹っ切れたという個人的な省察のような体験があったからだろうと察するほかはないのである。恐らく当人もこの内的な決断を言葉では説明できないだろう。理性には限界があるということでもある。
人の使う言葉には限界がある。愛するものの死に接したとき、哀しみを表現する言葉が浮かばない。どんな慰めの言葉も癒しにならない時がある。人間の言葉とはそいうものなのだ。語いが足りないではすまない。あまりにも表層過ぎるのである。
ヨハネによる福音書1章1節に「始めにことばありき」という章句がある。ここでの言葉は神のことばーロゴス(logos)ということである。この世界の根源として神が存在するという意味とされる。「ロゴスは世界の根幹となる概念であり、世界を定める理」とEncyclopaedia Britannicaにある。
幸いにして我々は死の哀しみの淵から立ち上がることができる。「世界を定める理」にある与えられた命を感じ、支えられていることを経験し、生きることの価値を「我と汝」との関係に見いだすことができる存在だからである。