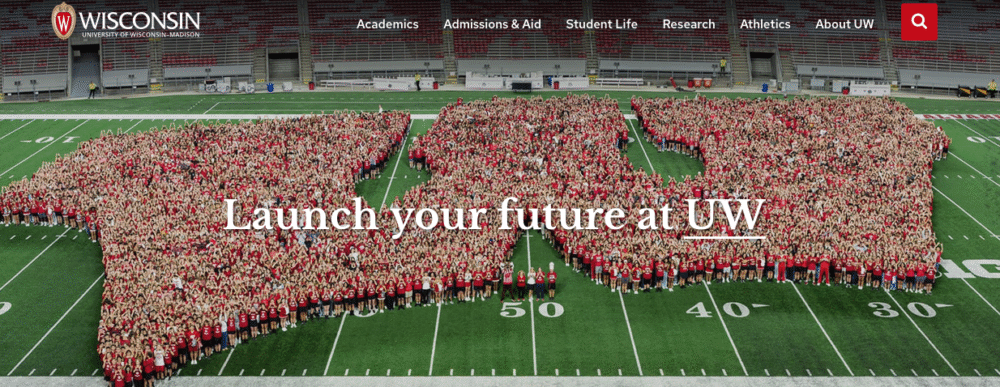甲斐の江戸の別宅は上野の近くの湯島にありました。江戸の海産問屋である雁屋信助が原田家の回米を受け持つこととなり、信助は日本橋の石町の家に甲斐を招待します。米の回送で雁屋は繁昌します。そのとき給仕をしたのが信助の妹おくみです。一目で甲斐にひきつけられ、信助はまた妹が甲斐に気に入られたと思い込みます。信助は甲斐に心服していました。
「保養のために控え家を持ってはどうか」と信助は甲斐にすすめ、自分の費用で湯島の家を手に入れます。そして「お側の用をさせてくださるよう」と云っておくみをつけたのです。

 この別宅を大老酒井雅楽頭が訪れたときです。甲斐はこの時身分を偽り浪人の身であると雅楽頭に告げるのですが、この嘘は見え見えでした。雅楽頭は八十島なる人物が原田甲斐であるのを見抜いていたのです。しかしあくまでも甲斐は偽名を使い「それがしは浪人八十島で御座います」と述べるのみでした。
この別宅を大老酒井雅楽頭が訪れたときです。甲斐はこの時身分を偽り浪人の身であると雅楽頭に告げるのですが、この嘘は見え見えでした。雅楽頭は八十島なる人物が原田甲斐であるのを見抜いていたのです。しかしあくまでも甲斐は偽名を使い「それがしは浪人八十島で御座います」と述べるのみでした。
この時、甲斐は時の最大権力者酒井から直につかわされた盃を受けようとしません。
「ここはそれがしの屋敷です。例えどなた様のお勧めでも盃はお受けできません」
甲斐のこの振る舞いは、酒井や兵部一味に取りこまれることを避けたうえでのものでした。甲斐のこの言葉に雅楽頭の顔がぱっと赤くなります。この場で無礼討ちにしても不思議ではありません。その時、二人の間に酌をしていたおくみが割って入ります。
「その盃、わたしがお受け致します」
 おくみの器量の良さと良妻ぶりのような仕草に、さすがの雅楽頭もかろうじて冷静さを取り戻すのです。そして云います。
おくみの器量の良さと良妻ぶりのような仕草に、さすがの雅楽頭もかろうじて冷静さを取り戻すのです。そして云います。
「そちたちはいい夫婦だ」
雅楽頭が帰ると、甲斐とおくみは次のような会話を交わします。
「どうしてあんなに強情をお張りになさいましたの」
「強情だって、、」
「お盃ですわ、どうしてあの盃をお受けにならなかったのですか、」
「候は怒りはしない」
「あたしあの盃をお投げになるかと思いました」
「えらいな」
「ですからあたしいそいで頂戴したんですわ」
「いい呼吸であった」
 甲斐は頷いて、おかげで酒井候は命びろいをしたよ、と云います。
甲斐は頷いて、おかげで酒井候は命びろいをしたよ、と云います。
「どういうわけですの?」
「舎人と丹三郎がいるのを忘れたのか」
「わたしが辱められれば二人は黙っていない、必ず候に斬りかかる」
「もっとも、わたしはそれを待ってはいないがね」
甲斐は頭巾をかぶり立ち上がります。おくみはにわかに別れが惜しくなり、袖や袴の裾などを直しながら、また逢うことの約束をせがむのです。