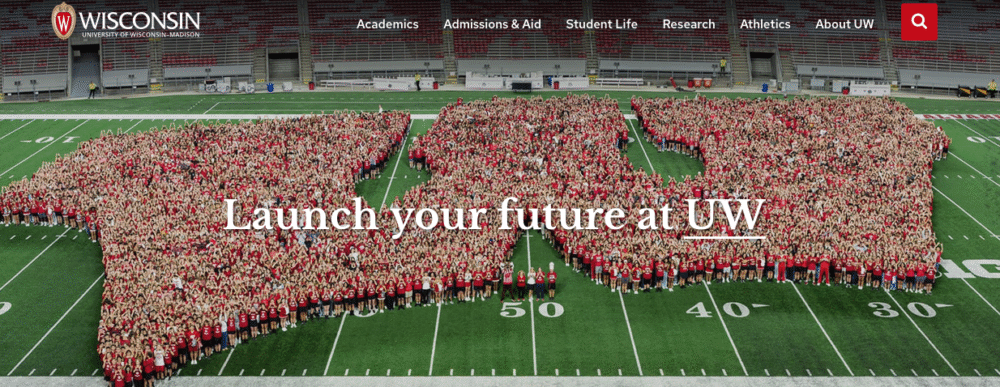主人公、お高の父は依田啓七郎という松代藩五石二人扶持です。二人扶持とは、1年間に二人分の生活費として米十俵の扶持米を貰える身分ということです。つつましい暮らしです。実直で温厚、しかし卒中で倒れ殆ど寝たり起きたりの生活をおくっています。十歳になる松之助という息子がいます。妻は松之助が三歳のとき亡くなります。
お高の実の父は西村金大夫で、松本藩の勘定方頭取をしていて五百五十石の身分です。実の母がお梶です。かつて西村家には子どもがたくさん生まれ、養育することにもこと欠くありさまでした。そのため松代藩の依田啓七郎にお高を遣ったのでした。その後、不思議なほど幸運に恵まれ西村金大夫は勘定方に出世したのです。
お高は依田家で木綿糸を紡いで生計のたしにしています。お高が織った糸束を会所に持って行くと係の老人が云います。
「わずかの間にたいそう上手になられたな、」
「そなたの糸は問屋でも評判になっているそうだ」
「ひとつには孝行の徳かもしれぬが、、」



 夜、父の肩をもんでいると父は云います。
夜、父の肩をもんでいると父は云います。
「おまえあした松本へゆくのでがな、」
「松本ではお梶どのがご病気だそうな、おまえさんに一目逢いたいから四五日のつもりで来てくれるよう、お使いの者がきたのだ」
お高が西村家に着くとお梶女が云います。
「依田どのからあなたにあてた手紙です」
こんど松本におまえを帰すにあたってはいろいろ考えた、西村からこれまでの養育料としてかなり多額のたいもつをくれる話があり、それだけあれば自分の田地を買って松之助と二人、安穏にくらしていける、おまえも西村のむすめとして仕合わせな生涯にはいれるだろう、という内容でした。
その手紙を読んで、お高は父から松本へゆけといわれた夜のことを思い浮かべます。お高に肩をもませながら、こちらに背を向けて自分の辛い顔をみせたくなかったのです。
実の母、お梶にお高は云います。
「思し召しはよくわかりました。ほんとうに有り難う存じますけれど、私はやはり松代へ帰らせていただきます」
「ただいま戻りました」
「どういうわけで帰った?」
「持たせてやった手紙は読まなかったのか、」
「拝見いたしました」
「おゆるしください、父上さま、」
「わかっておりますけれど、お高はいちどよそへ遣られた子でございます」
「乳ばなれをしたばかりで、母の懐からよそへ遣られたお高を父上さまは可哀そうと思ってはくださいませんか?」
「もし可哀そうだとお思いくださいましたら、ここでまたよそへ遣るようなことはなさらないでくださいまし」
「だが、西村はおまえにとって実の親だ、西村に戻ればおまえは仕合わせになれるのだ」
「いいえ、仕合わせとは親と子がそろってたとえ貧しくとも、一椀の粥を啜りあっても親と子が揃って暮らしていく、それがなによりの仕合わせです」
「お高にはあなたが真実のたった一人の父上です、亡くなった母上がお高にとってほんとうの母上です、この家のほかにわたしには家はございません」
「父上、」と叫びながら松之助が走り寄ってきます。表で二人の話を聞いていたのです。
「どうぞ姉上を家においてやってください!」
「西村どのには父から手紙を書く、もう松本には遣らぬからと」
松之助は姉の膝へとびつき、涙に濡れた頬をすりつけながら声をあげて泣き出すのです。