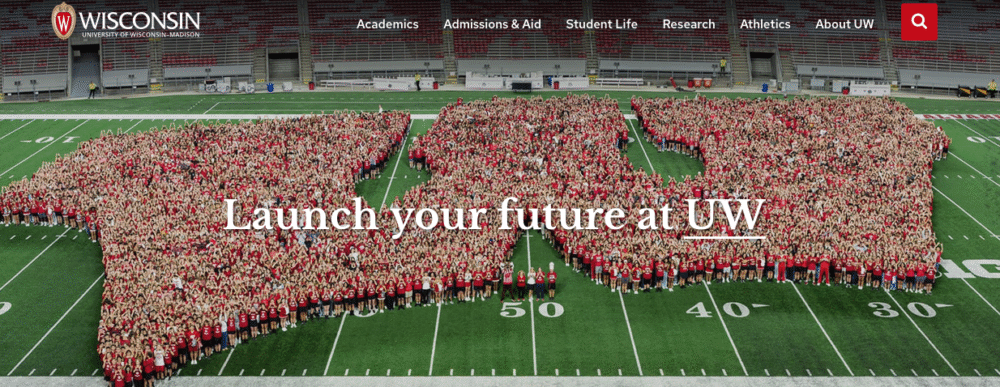由紀は、八百石の大寄合という恵まれた家に生まれます。世の中の辛酸暮らしを知りません。安倍休之助との祝言の日、仲人に連れられて安倍家に向かいます。乗物をおりて六畳ほどの部屋に案内されます。新しく張り替えられた襖や障子に燭台の灯がうつっています。休之助は三百石のお納戸役で気性は温和なことで定評がありました。
急に外がざわざわとします。
「なにごとでございますか?」
「休之助がけがをして戻った、、」
大藪のところで倒れている休之助が見つけられたというのです。休之助の母が由紀に家に戻るように云います。
「わたしは家へはもどりませぬ」と由紀は凜として云います。
「おそれいりますがわたしに着替えをさせてくださいまし、常着になりたいと存じますから」
常着とはふだんぎのことです。



「でも由紀どの、それは、」
「いいえ、まだ盃こそいたしませんけれど、この家の門をはいりましたからは、わたしは安倍の嫁でございます」
休之助はござを敷いた夜具の上に仰臥しています。医者がきて傷の手当てをしますが、傷は脇腹で三十針も縫ったほどでした。すべての人が去って、はじめて二人だけになったとき、老母はそっと由紀の手をとって云います。
「ありがとうよ」
「ふつつか者でございます、どうぞいろいろお叱りくださいまして、、、」
七日になってお納戸頭が休之助の家にやってきてしばらく話ししています。その夜、休之助は床の中で由紀に、勘定方へ急ぎ八十両を届けるように指示します。由紀は晴れ着などを売り、実家にも頼んでなんとか八十両を集め納戸に届けるのです。瀬沼弥十郎という同僚がお納戸の金、百両を費消していたのです。それを休之助は知ってしまうのですが、黙っていたのです。そして弥十郎は休之助を襲うのです。
費消した金がお納戸に戻り、事件はうやむやになります。そしてあるとき瀬沼弥十郎が家に訪ねてきます。
「あのとき、大藪のほとりで闇討ちをしかけたのは、そこもとに自分の不始末をみつけられたからで、」
「そしてそこもとを斬り、そこもとに罪をなすりつけようとしたのだ」
「そこもとは拙者の不始末をひきうけて呉れた、あれだけのたいまいの金を黙って返済し、自分の名を汚した体面を捨てて罪を着てくれた」
「拙者はそこもとがよからぬ商人にとりいられて、米の売買に手をだしているらしいということを聞いていた」
「人間は弱いもので、欲望や誘惑にかちとおすことはむつかしい、誰にも失敗やあやまちはある、あのとき意見をしなかった拙者にも半分の責任があると思った」
「それが幾らかでもそこもとの立ち直るちからになって呉れればよいと思って、、、」
少しも驕ったところのないたんたんとした言葉です。
休之助は弥十郎を励ますのです。
「そこもとは立ち直った、奉行所に抜擢され江戸詰になったそうだが、しっかりやってくれ」