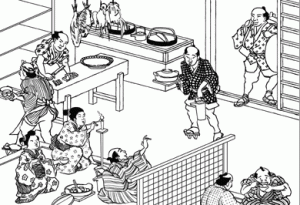山本周五郎の作品を読んでいくと、彼の生い立ちや家族関係、育った土地とそこにおける人間関係がどのようであったかということに興味が湧いてきます。こうした事情を知ることで、山本の作家としての矜持とか誇り、作品に流れるテーマも理解できそうな気がしてきます。「山本周五郎を読み直す」や「山本周五郎庶民の空間」、「人間山本周五郎」といった本などを参照しながら、彼の作家の人となりを数回にわたって探っていくことにします。



 山本周五郎の本名は清水三十六。「さとむ」と呼ばれたそうです。明治三十六年、山梨県北都留郡初狩村に清水家の長男として生まれます。祖父清水伊三郎がどうしても周五郎を引き取ることを許さなかったあります。事情はわかりません。そのため伊三郎の姉、斉藤まつの家で出生したようです。父の逸太郎は妻を失った後、若い女を二度嫁にもらいます。しかし、二人とも男を追って去ります。やってきた後妻のてるえは家事一切をよくこなし、病床の逸太郎や子どもの面倒をみます。
山本周五郎の本名は清水三十六。「さとむ」と呼ばれたそうです。明治三十六年、山梨県北都留郡初狩村に清水家の長男として生まれます。祖父清水伊三郎がどうしても周五郎を引き取ることを許さなかったあります。事情はわかりません。そのため伊三郎の姉、斉藤まつの家で出生したようです。父の逸太郎は妻を失った後、若い女を二度嫁にもらいます。しかし、二人とも男を追って去ります。やってきた後妻のてるえは家事一切をよくこなし、病床の逸太郎や子どもの面倒をみます。
初狩の生活では家運が傾き、同家所有の長屋に移転します。祖父母、叔父、叔母、逸太郎夫婦に周五郎を加えた八人家族の清水家は狭い生活で、そのため大月に転居したようです。父逸太郎の葬儀のとき、山本はなぜか立ち会っていません。そのため親族から非難が集中したようです。この一件を機に山本は故郷の山梨には来なくなります。とはいえ倒れた父に毎月二十円を送金し、韮山に墓地の墓石には清水逸太郎建立と刻印したと記録されています。その費用を負担したのが山本だったといわれます。血縁や地縁を問い直そうという作品を数々書き上げていく理由がこのあたりにありそうです。
昭和六年に大森は馬込の借家に入居するまで、山本はおおむね窮屈な居住事情の中で暮らします。それが作品に投影されているようです。山本周五郎は庶民の作家だと云われる所以です。日の当たらぬ吹き溜まりに身を寄せ合い、「一日いちにち、まっとうな暮らしをしようとする最大多数の人々に、親近感を抱き続けた出発点が借家であり長屋生活であった」と山本の研究家木村久邇典が書いています。