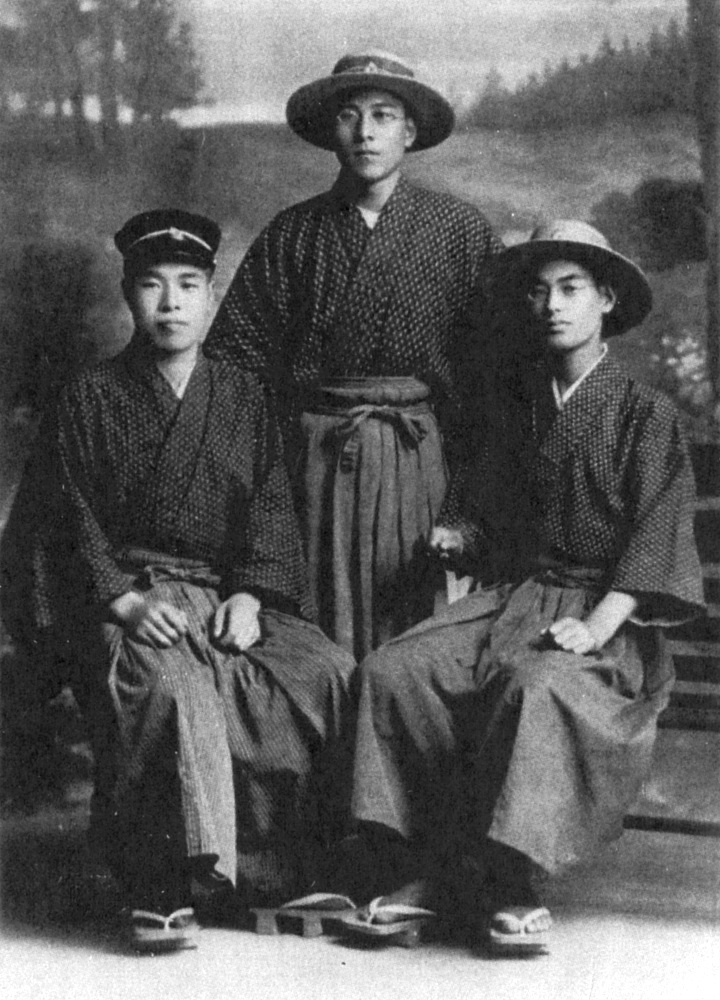戦後民主主義のオピニオンリーダー(opinion leader)の一人が東京大学総長であった矢内原忠雄です。彼は「続 余の尊敬する人物」岩波書店刊行において内村,新渡戸の二人を師とし、自らを「札幌の子」と言っています。1937年に中央公論の9月号にて「国家の理想」と題する評論を寄せます。矢内原はこれを書いた後にある主張のために,東京帝大教授を追われます。その主張とは、国家が目的とすべき理想は正義であり、正義とは弱者の権利を強者の侵害圧迫から守ることであること、国家が正義に背反したときは国民の中から批判が出てこなければならないことを訴えたのです。この論文は大学の内外において矢内原排撃の格好の材料として槍玉に挙げられます。1936年6月に岩波書店から発行されていた「民族と国家」は、1937年12月、矢内原が辞職した当日に内務省により発禁処分となります。
敗戦により矢内原は復帰して、南原繁に次いで二代目の東大総長となります。また戦後最初の文部大臣前田多聞,その後継者安部能成,さらに,天野貞祐,森戸辰雄と戦後歴代の文部大臣がすべて「札幌の子」だったのです。こうした人達は東京帝大経済学部または法学部出身であり,新渡戸の直接の教え子なのです。内村との接点はどこにあったのかです。
新渡戸教授の家には多くの教え子が押しかけていたのですが,その中にはキリスト教に強い関心をもつ者も少なくありませんでした。新渡戸は彼らに「その勉強がしたいのなら私よりずっと偉いやつがいる」と内村を紹介していたのです。こうして新渡戸→内村ルートを歩いた一群の一人、矢内原は「内村の柏木聖書研究会である「柏会」、聖書之研究の「白雨会」などのグループをつくり,自分たちを「札幌の子」と自認していきます。
彼らは,新渡戸の直接の後継者として植民政策学講座の教授となった矢内原がそうであったように,二人の師の亡き後それぞれの立場で軍国主義への抵抗を続けます。そして敗戦と共に戦後改革の先頭に立ち,戦後民主主義のオピニオンリーダーとなっていきます。上に挙げた名前以外にも経済学者の大塚久雄,最高裁判所長官田中耕太郎などがいます。彼らの活躍はまさに内村,新渡戸の思想,さらには札幌農学校の精神の力強い復活だったといわれています。
「札幌の子」は東大ルート以外からもたくさん生まれました。一例として後に総理大臣となった石橋湛山を挙げておきます。石橋は早稲田大学出身ですが,甲府中学時代の校長だった大島正健の強い影響を受けます。大島は札幌農学校の1期生で「クラーク先生とその弟子たち」と著作を発表し、自ら「札幌の子」と称しました。戦前は気骨のジャーナリストとして知られ「非戦論」、「小国主義」など内村と驚くほど似た主張を展開しています。1956年に総理大臣となりますが,間もなく病気のため総理を岸信介に譲ります。石橋が健康であったならば,その後の日本は今とはずいぶん異なった姿になっていたろうと言われています。