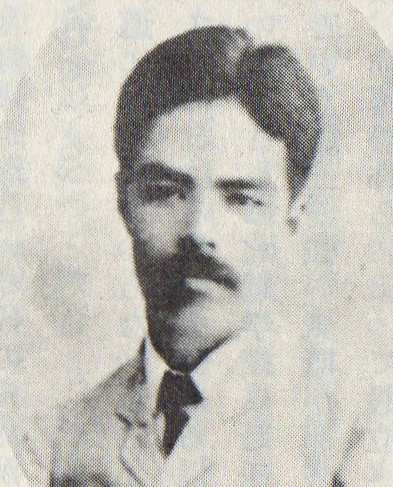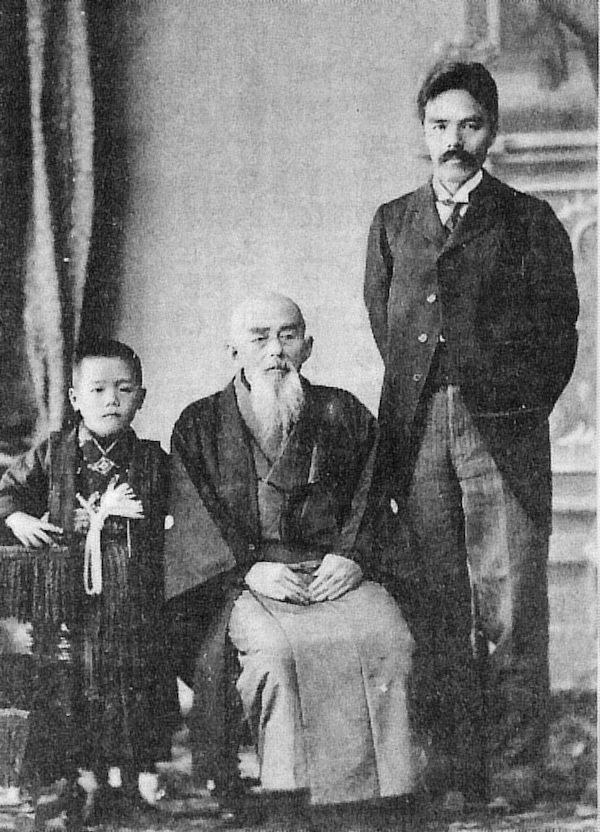内村鑑三に「救国論」というタイトルの著作はありません。ただ、彼の「代表的日本人」など、キリスト教の精神に基づき、日本と日本人のあり方を問い、独立と精神的進歩を訴える言論活動そのものが「救国論」と言われています。彼は国粋主義的な愛国心に批判的で、むしろ個人の良心に従い、精神的に成熟した日本人の集合体として国を救うことを目指したのです。
1894年に出版された「代表的日本人」は、日本の歴史上の偉人をキリスト教の精神と照らし合わせながら紹介し、日本人が普遍的な価値観を持つことで、自らを高め、国を救う道を示しました。彼は、Japan(日本)とJesus(キリスト)という二つのJ という愛すべきものを大切にすることを唱え、キリスト教の信仰と日本への愛が両立することを説きました。
日露戦争に際しては非戦論を唱え、足尾鉱毒事件で田中正造らとで公害問題を告発するなど、政府の政策や当時の風潮に批判的な言動が多く、一部からは「非国民」「国賊」と見なされることもありました。精神的独立の重視し、真の救いは外的な力ではなく、個人の良心に基づいた精神的な独立と自律性にあると考えました。この考え方は、国家の力に依存することなく、日本人一人ひとりが人間として成長することで国が救われるという信念に繋がっています。
内村の「救国論」とは、日本の真の救い(救国)とは、政治や軍事ではなく、個人の道徳的・宗教的な内面の改革によって実現されるべきだという思想を指します。これは、彼のキリスト教信仰、特に無教会主義と深く結びついており、西洋の「国家中心主義」や「権力主義」に対する鋭い批判を含んでいます。明治・大正期における日本の急速な近代化や、軍国主義的な傾向に強い危機感を抱いていました。
彼の救国論の主張は、「後世への最大遺物」のエッセイで以下のようにまとめられます。
国を救うのは「外的な力」ではなく「内的な力」であり、軍事力や経済力では真の国の安泰は得られない。国の土台を支えるのは「国民一人ひとりの道徳心と宗教的良心」である。「魂の改革」こそが国家の再生につながる。国を救う者は、政治家にあらず、軍人にあらず、実業家にあらず、教育家にあらず、宗教家にして、しかも真の宗教家なり。
キリストの教えという信仰に基づいた人格の養成が国家の礎である。プロテスタントの聖書主義に立脚し、形式的な宗教よりも「信仰の本質」を重視。国家のために命を捧げるよりも、真理のために生きる人格者こそが、結果的に国を救う。真理を行い得る者、義のために命を賭ける者、これこそ救国の士なり。
軍国主義・愛国主義の盲信へ警鐘を鳴らし「愛国」という言葉のもとに行われる国家主義的な動きに警戒。国家を神のように崇拝する「国家神道」的傾向に反対する。
個人の内面的成長が、結果として国の成長につながる。「国家のために個人がある」のではなく、「個人が成長することが国家の救いになる。」
内村鑑三の救国論の現代的意義ですが、軍国主義の時代や物質文明の危険性を批判し、精神・倫理の再評価の必要性を説いたことです。さらに国家中心の教育ではなく個人の良心を重視し教育の根本に「人格形成」を据えたことです。そして、政治への依存を脱却し、信仰と良心による改革を訴え、草の根的な社会改革の重要性を説いたことです。