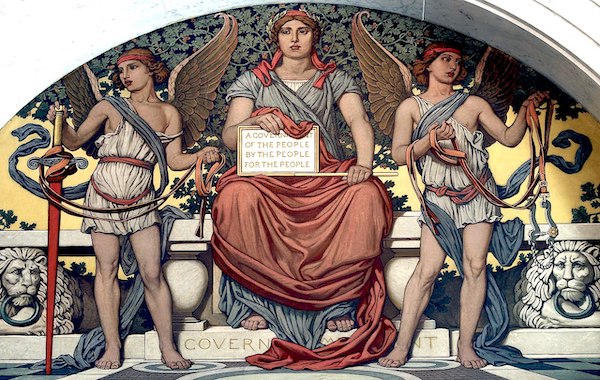どのような政策にも懸念とかリスクは考えられます。「責任ある積極財政」も例外ではありません。積極財政とは、主に国債の発行による景気上昇の財政政策です。その場合、財政赤字や国債残高の増加という側面があります。すでに政府債務は非常に大きい状態にはあらいます。財務省が間違って唱えてきた将来世代へのツケとか負担という懸念が言われています。ここで勘違いをしてはいけないことは、国債は政府の借金であり、国民の借金ではないということです。
国債の償還にあたっては、金利が上昇した場合、国債費の利払いが急増し財政を圧迫することも考えられます。どのような場合に金利が上昇するかについては諸説がありますが、将来的な可能性としてあることです。私には金利上昇理由がなになのかは分かりません。
国債による資金の利用は、どのような公共投資に充当するかであります。例えば、高速道路や整備新幹線の延長、老朽化した上下水道の工事、国土強靱化対策、宇宙開発など科学技術への投資といった積極財政が「バラマキ」に流れると、効果の薄い支出で財政負担だけが増える心配もあります。インフラへの投資などは質の確保や将来の需要予測が難しいこともあり、無駄な投資のリスクが存在するのも確かです。
政府が公共事業を増やしたり給付金を出したりすると、家計や企業の支出が増えます。つまり、経済全体としてモノ・サービスを「買いたい量」が増えるのです。労働者が確保できないとか、原材料が高騰しているとか、入手困難である場合、生産設備が不足している局面で追加の財政出動は、懸念される事態ともなりかねません。需要が増えて物価が上がり生活を圧迫する可能性もないではありません。
一度積極財政を採用すると、政治的理由で支出削減が困難になり、景気が好調でも財政が引き締まらないという問題も起こりえます。それを防ぐためには費用対効果を厳密に審査し、場合によって支出削減にも英断を求めることです。
まとめとして、責任ある積極財政の基本的な考え方は、短期では需要不足を補い、長期では成長の基盤を整えることで結果的に財政も健全化する”というものです。積極財政はメリットもリスクも大きい政策であり、最も重要なのは「何に、どのくらい、どの期間」投資するかという政策設計の精度にあると考えられます。