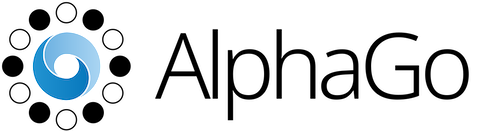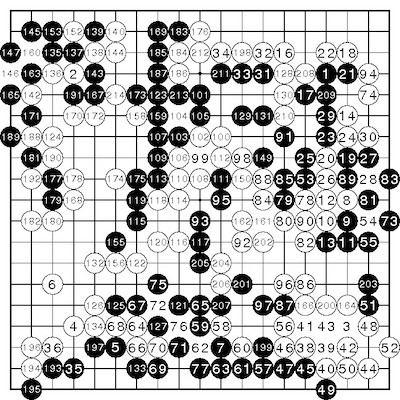私の「道落」の一つが囲碁。強いとはとてもいえないのですが、碁の深さや難しさに魅了されつつ、毎日練習するのを日課としています。囲碁には「定石」といわれる昔から度重なる研究と対局によって生まれた石の形があります。定石とは対戦者が最善を尽くして「部分的」に互角に分かれる石の形のことです。どちらかが有利な形となるなら、それは定石とはいいません。私も定石を何度も練習しています。ですがいざ実戦となるとその手順を間違えることがしばしばあります。対戦相手は定石にないような手を打ってきます。高段者は新しい定石を学び低段者を翻弄します。
2016年1月、Googleの完全子会社であるイギリスのGoogle DeepMind社が開発した、ディープラーニング(deep learning) の技術を用いた人工知能(AI)のコンピュータソフト「アルファ碁(AlphaGo)」が、2013年から2015年まで欧州囲碁選手権を3連覇した樊麾二段と対局しました。結果は5戦全勝し、それに基づく研究論文がイギリスの科学雑誌ネイチャー(Nature0)に掲載されました。囲碁界でコンピュータがプロ棋士に互先で勝利を収めたのは史上初のことでした。DeepMind社は「人間の棋譜を一切使わず、ルールだけを教えられた状態」からコンピュータ囲碁を強くする研究として「アルファ碁ゼロ(AlphaGo Zero)」を開発したのです。
さて、AlphaGoにまつわる話題です。それが、「定石と固定観念」というフレーズです。これが人工知能とどう結びつくかです。 囲碁はある程度の知識が無いと盤面を見ても優劣を判断できないのですが、囲碁AIによる形勢判断を数値で表示することで優劣を分かりやすく見せることが可能となりました。NHK杯テレビ囲碁トーナメントでも第69回(2021年度)から、AIによる%表示の形勢判断が画面上部に表示されるようになりました。
AlphaGoは従来のプロ棋士たちが「常識」として使ってきた定石の多くに対して、「必ずしも最善ではない」、「もっと勝率の高い手がある」ということを示しました。例えば、小目からの三々侵入です。かつては三々侵入は、中盤で打つものとされていましたが、AlphaGoは序盤から打つことで実利を先に確保する戦術を示しました。さらに、星の構えにおけるアプローチの順番や角の処理についても、今まで不利とされた打ち方が、AIによって再評価されました。