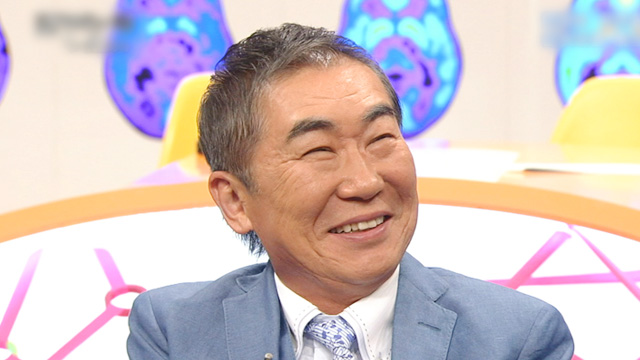ずうずう弁
小さいとき、稚内から始めて叔母が住んでいる札幌に出たときです。家族が暫く会話していると叔母が「シー坊、ずうずう弁を使わないで、、、」というのです。シー坊とは私の呼び名のことです。「ずうずう弁」はもともと福島地方の方言でそれが人々の北上により、稚内あたりで誰もが使う言葉です。濁音が多く、響きが強いのが特徴です。
私の家系は、青森の出なので、東北地方に特徴的な鼻音の強い話し方が当たり前だったのです。発音の「じ」「じゅう」が「ず」「ずう」と聞こえるところから、ずうずう弁といわれます。ずうずう弁は別名「浜言葉」で、日本海沿岸地方の港町、漁村などで話される言葉でもあります。「そうだ、そうだ、」と相づちをうつときは、「んだ、んだ、」とか「んだべさ、」というのです。関西弁では「せや、」が稚内あたりでは「んだ、んだ、」となります。
各地の方言は、地域ならではの特色があります。地元の人々の日常に根づいた文化です。NHKがニュースなどで使う「共通語」とは違って、単語や語尾、アクセントなどが違うところに面白みがあります。大阪弁はテレビのお笑い番組などでもよく登場し、親しみが感じられる方言です。ですがずうずう弁には、世間の話題となるようなおかしみがないようです。
大阪レジスタンス
新作落語に「大阪レジスタンス」というのがあります。6代目桂 文枝(三枝)師匠が演じています。大阪弁とか関西弁が全国言語統一令によって、標準語以外は使えなくなったという設定です。落語や吉本喜劇も全部標準語を使わないいけなくなります。「アホちゃうか~」という台詞も「馬鹿じゃありませんか」と標準語で言わねばなりません。
「言語警察」という組織が出来て、言葉の取り締まりを始めます。大阪弁を使うと2万円、そばにいただけでも共通語以外を許したというので罰金です。そんな世の中になります。根っからの大阪人で、どれが大阪の言葉が区別も出来ない人に淀川さんがいます。淀川さん、街でうっかり大阪弁を使ったため逮捕され、たっぷりと標準語を指南されます。指南がやっと終わってからの警察官と二人のやりとりです
警察:「帰ってよろしい」
淀川さん:「ほんまでっか」
これで最初から指南のやり直し。やっと終わります。
警察:「帰ってよろしい」
淀川さん:「おおきに」
またまた最初からやり直し。やっと終わります。
警察:「帰ってよろしい」
淀川さん:「ほな さいなら」
というわけで淀川さん、とうとう留置所に入れられてしまいます。警察曰く。「法令に従い適正に行っている」という、今も聞いたことにあるような説明をしています。 淀川さんは出所後、「大阪レジスタンス」という反権力運動をしている仲間に会うのです。その頃になると、各地の地名も代えられ、大阪は第32地方区となり、大阪の人も「第32地方区の人」となります。
大阪弁の台詞が入っている歌も、全て共通語で歌わなければならなくなり、歌の雰囲気も全く出ません。大阪の落語家も次々逮捕され死んでいきます。こうして淀川さん、レジスタンス活動を始め、大阪復活のために働くようになります。しかし、大阪復活の計画書を作ったために淀川さんは逮捕されます。そして「訛りは国の手形やないか、何でいけないんや」と叫んで銃殺されるのです。
10年後、大阪は日本国から独立し、ついに国連にも加盟します。テレビラジオも全て大阪弁、新聞も「朝日新聞でっせ」「読売新聞だんねん」「毎日新聞でおます」といった按配。教科書も「面積を出しなはれ」という具合に大阪弁が花盛りとなります。
壊された大阪城は前の3倍の巨大なものが再建され、町は出来るだけゴチャゴチャするようにという都市計画法がちゃんと守られます。高さ40mの「食い倒れ人形」も完成してアメリカの自由の女神と並び称されます。この人形が大阪国のシンボルとなったという、奇想天外の新作落語の名作です。「一度この落語、ききなはれ」、 「あんたらもうええかげんにしなはれや」