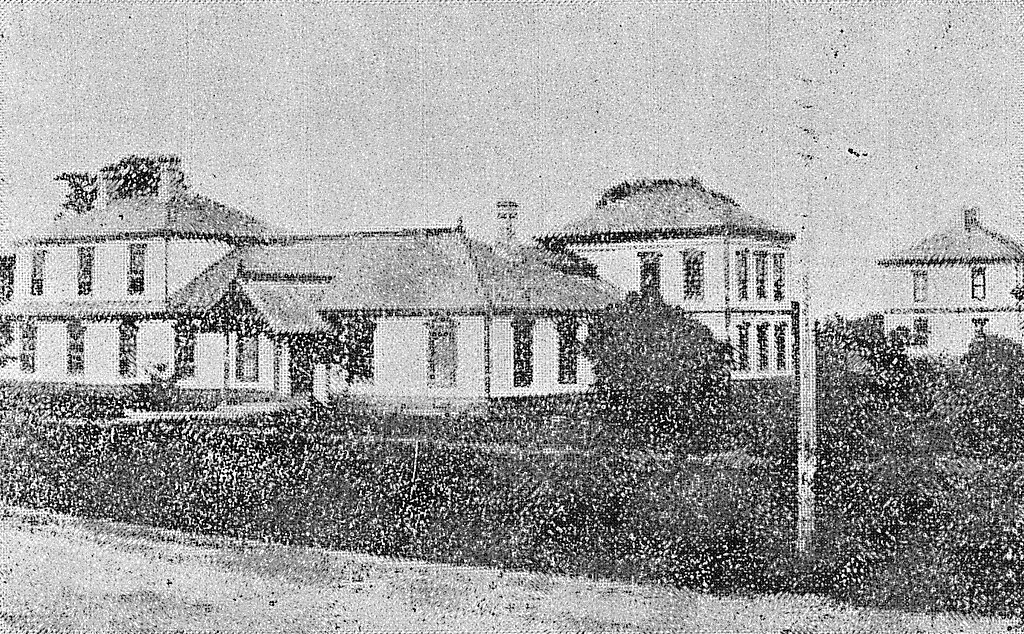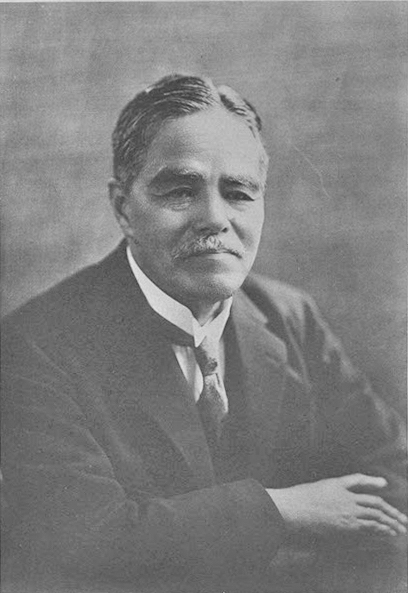『馬槽の中に』」というタイトルの讃美歌があります。別名(この人を見よ)と呼ばれています。この賛美歌から本稿のタイトルをいただきます。「馬槽の中に 産声上げ、大工の家に 人となりて 貧しき憂い 生くる悩み つぶさになめし この人を見よ」という歌詞です。作詞したのは由木 康という方で、日本の讃美歌の発展の中心的な役割を果たし、賛美歌「きよしこの夜」の訳者として知られています。
北海道大学の前身、札幌農学校の大先輩というと内村鑑三と新渡戸稲造、植物学者宮部金吾の名前が出てきます。新しい紙幣が出ていますが、これまで使われ今も通用している紙幣は1万円札が福沢諭吉,5千円札が新渡戸稲造,千円札が夏目漱石です。この3人の共通点は何でしょう。そのキーワードは「近代化」です。当然ですが、紙幣の人物を選ぶときには、テーマがあるのです。それ以前の紙幣は聖徳太子,伊藤博文,板垣退助で,このテーマは「憲法」でした。
明治期の日本にあって,日本の近代化はどうあるぺきかをそれぞれの立場から真剣に考えたのが福沢、新渡戸、夏目です。この3人が生きていた時代は、日本の近代化の推進であり、物質的で技術的な「文明開化」が先行していたといわれます。それを支える人間の精神が旧態依然とし、当時の人々は「和魂洋才」といって「文明開化」を正当化したのです。それでは本当の近代化は出来ないと考えたことです。
福沢が1872年に『学問のすすめ』をはじめとする多くの啓蒙書を書いたのも「文明開化」に共通する危機意識からです。夏目は1911年の有名な講演で「現代日本の開化は皮相上滑りの開化である」と言っています。日本の真の文明開化はもっと思想的なものでなければならないと言うのです。福沢も夏目も近代化を訴えるよりも、根源的な「近代精神」を問題にしていたと言ってよいようです。
そしてこの問題をさらに徹底して追及したのが新渡戸稲造です。新渡戸は札幌農学校,京都大学,東京大学の教授を歴任した学者,教育者として,また国際連盟の事務次長を務めた国際人として活躍しました。1899年に著書『武士道』を刊行します。流麗な英文で書かれ、長年読まれています。新渡戸がこの本を刊行した時、世界は日本人の道徳を賞賛したといわれます。日本人が近代国家へと歩みを続ける理由に納得したからです。こうした経歴を通して彼が一貫して日本国民に訴え続けたテーマが「近代精神」だったのです。そして彼の力強い同伴者が,札幌農学校の同期生で親友の内村鑑三でした。
私は内村鑑三、新渡戸稲造、宮部金吾の末席の末席、またの末席にいた北海道大学卒業生の一人です。