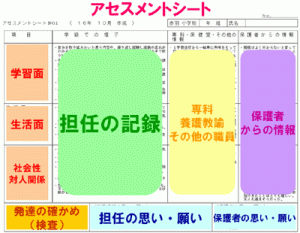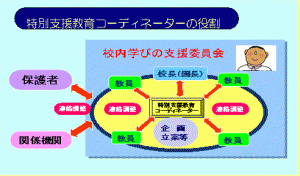Last Updated on 2025年3月6日 by 成田滋
沖縄国際大学人間福祉学科准教授の知名孝氏が「発達障害の診断が、学校を医療の場にしている!?〜教育の医療化」 という記事を書いている。http://www.okinawatimes.co.jp/cross/?id=188
知名氏の主張で興味あることは、「診断」という医療の営みが学校にも持ち込まれ、教職員が処方を求め、その結果「自らが考え試し発見する機会を奪っている」というのだ。現場の教師が、例えば「アスペルガーと診断された子どもの対応を教えて欲しい」といって「専門家」と呼ばれる人を尋ね歩く現状があるというのである。こうした姿を「教育の医療化」と呼んでいる。診断が下されたといっても指導は現場の仕事だ。保護者も親の会をつくり勉強する。こうした学びの機会で各学校の対応を共有しあい、行政に支援を要請している。
筆者は、こうした「教育の医療化」とか「教師の診断志向」は、アメリカ精神医学会のDSMや 世界保健機関のICD-10の影響にあると考えるのである。このような「精神疾患の分類と診断の手引」は、診断の基準を示すだけで、なんら教育上の処方箋を出しているわけでない。「診断も検査も結局は仮説」なのである。
これまで養護学校教職員、施設職員、医師などを主体とする団体が、すべての障害児はレベルに応じて発達可能であり、それを保障するための特別な教育が必要であると主張してきた。特別支援学級や学校の存在はそのためにあるという立場である。すべての子どもが統合や包摂された環境での学習を保障する人々、いわば分離教育からの解放とは鋭く対立してきた経緯がある。
今、共生社会の形成に向けた包括的な教育が進行しつつある。こうした実践の核心は子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある子どもに対して、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある『多様な学びの場』を用意しておくことが必要であるという考え方である。これが「インクルーシブ教育」である。
しかし、普通教室の中で多動で落ち着きのない子どもがいたとすれば、そうした子どもの対応に慣れない教師はおどおどするはずだ。普通学校への包摂や包容である「インクルーシブ教育」には、教師への支援が欠かすことができない。だが支援教育の軽視が取り沙汰されている。特別支援教育コーディネータの実力不足と不適切な配置が課題であることを現場から寄せられている。